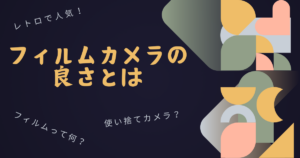死にゲーがこれから直面する問題点 ~自由度と高難易度の両立~

昨今、ゲームジャンルの中でも評価されてきた死にゲーというジャンル。
死にゲーがこれから直面するだろう課題を技術的な進化によって高まるゲームプレイの自由度と高難易度の両立という視点で分析。
それらの問題点の解決策をフロムソフトウェアの「ELDEN RING」を例に用いて解説していく。
ゲーマーが死にゲーに求める要素
〕-scaled.jpg)
近年、ビデオゲームと呼ばれるジャンルは広く展開され、多くの年代から支持を得ている。
中でも死にゲーと呼ばれるジャンルがあることはご存じだろうか?
フロムソフトウェアから発売されたデモンズソウルから端を発した死にゲージャンルは非常に重厚なプレイ体験とクリアした際に得られる濃密な達成感によってゲーマーの間では親しまれている。
〕-1024x683.jpg)
そんな中、6月21日にフロムソフトウェアから発売されたELDEN RINGのDLC、「SHADOW OF THE ERDTREE」が難しすぎると話題になっている。
死にゲーの難しさとは何か、難しさと理不尽の違いは何か、快適なゲームプレイと重厚なクリア体験との間で死にゲーに対するゲーマーの評価が変化してきている。
死にゲーとは?
〕-scaled.jpg)
ビデオゲームが数多持つジャンルの一つ、死にゲーとは2009年にフロムソフトウェアから発売されたデモンズソウルに端を発している。
基本的なゲームデザインはレベルを上げ、ボスを倒すという王道的なRPGだ。
しかし、従来のRPGにはない要素が多々あった。
ボスまでの道のりに多くの敵や、極悪なトラップを置いてみたり、やっとの思いで辿り着いたボスは何度もリトライして挑まなければならないほど強敵としてデザインされていたりした。
極めつけは死亡した際にレベルアップに必要な経験値を死亡した場所に落としてしまうことだ。
リトライした際に落とした経験値を拾うことができれば回収することは可能だが、拾うことができないまま敵に倒されてしまうと集めた経験値は全てロスト(失う)してしまう。
このシステムが凶悪な敵のデザインと相まってゲームの難易度を跳ね上げた。
死にゲーの流行
〕-683x1024.jpg)
従来のゲームとは難易度が格段に上がった死にゲーは、しかし、ゲーマーの間では評判だった。
何度も敵に倒されてしまう死にゲーはプレイヤーにストレスを与えるが、最後にボスを倒した瞬間に全てのストレスが解放される。
その得難い達成感が多くのゲーマーを虜にした。
デモンズソウル以後、フロムソフトウェアは多くの死にゲーを発売した。
「ダークソウルシリーズ」や「アーマードコアシリーズ」、「Blood borne」、「隻狼」など。これらすべてがゲーマーから高い評価を得た。
さらにはフロムソフトウェアが作成する高難易度のアクションゲームにインスピレーションを受けた他社が多くの死にゲーを開発し、販売していった。
それらは元祖であるフロムソフトウェアの「ダークソウルシリーズ」をリスペクトしているとされ、ソウルライクゲームと呼ばれるようになった。
「ELDEN RING」の発売
〕-1024x683.jpg)
数多くのソウルライクゲームが発売される中で、元祖であるフロムソフトウェアはオープンワールドRPGとして2022年に最新作の「ELDEN RING」を発売した。
歴代の死にゲーを彷彿とさせる高難易度のアクションをプレイヤーに要求しながらも、広大なフィールドを馬で駆けまわる爽快感、どこのフィールドマップからでも攻略できるという自由度が大きくユーザーに評価された。
高難易度のアクションということで今まで死にゲーを遊んだことがないというユーザーも自由度から与えられる攻略の多さ、難易度の調整により死にゲーをクリアした際に得られる多大な達成感味わうことができたのだ。
多くのファンを獲得した「ELDEN RING」は発売した年のゲームオブザイヤーを獲得することができた。
自由度が与えた難易度の低下

より幅広いプレイヤーに遊ばれて支持された「ELDEN RING」はゲームオブザイヤーを獲得するなどの高い評価を得る一方で、フロムソフトウェアの古参ファンに苦言を呈されることもしばしば見受けられた。
「ELDEN RING」はオープンワールドRPGとしてプレイヤーに様々な選択肢=自由度を与えていた。
その自由度の一つに「遺灰」というシステムが存在した。この「遺灰」はゲーム内のフィールド、中でも高難易度のゲームスキルが求められる場所やボス戦で呼び出すことができる助っ人NPCだ。
この存在がボス戦の難易度を大幅に低下させ、高難易度を求める古参ファンの中には受け入れられないプレイヤーも存在したようだ。
一躍人気になった「ELDEN RING」は多くの配信者がゲームプレイをYouTubeなどで配信を行っていたが、そのコメント欄でも「遺灰」の使用に関して敏感に反応する言葉が多く見受けられていた。
他にも「武器が強すぎる」「魔法(飛び道具)が強すぎる」など、高評価の裏では自由度による難易度の低下に納得できないユーザーがいたようだ。
待望されたDLC
〕-1024x683.jpg)
様々な意見が交わされる中、それでも全てのユーザーが待ち望んでいた「ELDEN RING」の大型拡張コンテンツ、「SHADOW OF THE ERDTREE」が2024年6月21日に発売された。
ゲーム本編の約半分程の値段でありながら、ソフト一本分のボリュームを備えた大型ダウンロードコンテンツだった。
ゲーム本編の広大なフィールド、美麗な景観、高難易度のアクションに魅了されたプレイヤーは期待以上のクオリティに心を躍らせたのだ。
〕-1-1024x681.jpg)
けれど、ダウンロードコンテンツとして破格の評価を受けながらも、ある問題が話題を呼んでいた。
それがボスの更なる高難易度化であった。
この事態にライトなユーザーは心を折られ、今までフロムソフトウェア作品を愛していた古参ファンの中でも、ついていけないプレイヤーが続出したのだ。
異様に強化されたボス
〕.jpg)
フロムソフトウェアが作成するゲームは手強くも回数をこなすことでクリアすることができるボス戦が非常に高い評価を受けていた。
けれど「ELDEN RING」の大型拡張コンテンツ「SHADOW OF THE ERDTREE」に登場するボスたちは過去の作品と比較しても格段に強いというユーザーの声が多くあった。
登場するボスたちに共通するユーザーの不満点として、「ボスが攻撃している時間の方がプレイヤーの攻撃時間よりも圧倒的に長い」「ボスの小さく素早い攻撃でもこちらの体力がすぐに無くなってしまう」「攻撃の回避方法が難しすぎてボスに倒されてしまう度にリトライしてみようという気持ちは湧かず、ストレスしか溜まらない」等という意見が噴出した。
前述に紹介した「遺灰」システムやボス攻略に適した強力な武器等、「ゲーム側が用意してくれた難易度の調整システムを使用すれば良いのでは」という意見もあったが、「プレイスタイルを狭めてしまうようなボスはそもそもゲームとして楽しくないのではないか」という対立意見も生まれた。
ここにきて自由度による難易度の調整がボスの異様な難易度上昇と相まって争論の火種となってしまったのである。
あまりにも強力なラスボス
〕--1024x745.jpg)
大型コンテンツに登場した凶悪なボスの中でもとりわけ強力だったボスを紹介しよう。
「SHADOW OF THE ERDTREE」のトリを飾るラスボスである。
「ELDEN RING」本編にも十分に強力なボスは登場したが、このラスボスは多くのユーザーを絶望に落とすほど凶悪だった。
ストーリー上における重要なキャラクターであり、格好の良いデザインであるが、その性能から嫌いになってしまったユーザーも多くいるだろう。
その凶悪な性能の一つとして非常に強靭な防御力が挙げられる。
広大なフィールドを探索し、尚且つレベルも上げた状態であるにも拘わらず単純な近接攻撃では微量なダメージしか与えることができないのだ。
また「ELDEN RING」には敵に対して様々な効果を与えることができる状態異常というシステムがあるが、このラスボスは状態異常システムに対する耐性値が異常に高いのだ。
近接攻撃で有効なダメージを与えられない場合は状態異常によってボスの体力を減らすことが定石であるのだが、ラスボスの耐性値が高いせいで中々状態異常にすることができない。
敵の体力を割合で減らす「出血」、割合で減らしながら防御力を低下させる「冷気」、徐々にダメージを与える「毒」や「腐敗」など、多くの攻略の糸口が用意されているように見せながら、その実、強靭なラスボスの耐性値によって状態異常は効果が薄い状態となってしまう。
状態異常に特化させたプレイヤーが操作するキャラクターは近接攻撃力が低下し、ただでさえダメージを与えられない近接攻撃が更に少ないダメージしか与えられないという状況に陥ってしまう。
極めつけはボスの体力が四割ほど削ったあたりで行われる第二形態への変化で訪れるムービーの挿入である。
〕-1024x692.jpg)
「ELDEN RING」本編や大型拡張コンテンツに登場するボスたちは特別な場合を除き、第二形態への変化にはムービーが差し込まれることはなく、プレイヤーにとってチャンスの時間になることも多かった。
しかし、ラスボスは違う。
第二形態へ移行する度にムービーが差し込まれることによってプレイヤーに与えられた僅かなチャンスが奪われることはおろか、強靭な耐性値に対して辛抱強くかけた状態異常が解除されてしまうのである。
長い間、微量な近接攻撃ダメージしか与えられない武器で攻撃をし続け、やっとの思いでラスボスに「毒」の状態異常を与えたとしてもムービーによって解除されてしまう。
更にラスボスの強さはこれだけではない。
次に上げられるのは連続且つ強力な攻撃方法だ。
ラスボスの攻撃パターンの一つを例に挙げるとするのならば、まず、ボスがフィールドの全範囲を対象とした引き寄せ攻撃を行う。
その次にラスボスを中心とした広範囲の爆発攻撃、それに付随した連続広範囲ダメージの衝撃波が繰り出される。
しかし、ラスボスの攻勢はこの程度では終わらない。
衝撃波を繰り出した後、ラスボスは上空に浮かび上がり、複数の分身体を連続でぶつけながら、動きが止まったプレイヤーに対して前述した広範囲の爆発攻撃と連続ダメージを与える衝撃波を再度繰り出す。
従来の「ELDEN RING」に登場するボスであればタイミングよく回避ボタンを押すことで攻撃を回避することができのだが、このラスボスの連撃はそうではない。
ただ回避すれば良いというわけではなく、背後に回避しなければならなかったり、その後の分身体の攻撃は回避ではなく後ろにダッシュしなければならなかったりといった特殊な回避方法を選択しなければならないのだ。
回避、攻撃、回避、攻撃、というようにシンプルな戦法でプレイしてきたライトなユーザーでは到底クリアできないような設計となってしまっている。
杜撰なカメラワークと視認性
〕-819x1024.jpg)
ラスボス自体が持つ強さの他にゲームそのものの問題点として杜撰なカメラワークと視認性の問題が挙げられる。
ラスボスで例を挙げると、第二形態以降後、あらゆる攻撃に光の柱が追撃としてプレイヤーを襲う。
あまりに避け辛いことはもちろんだが、なんといっても画面を大きな光で覆ってしまうという致命的な欠陥が問題視されているのだ。
「眩しくて敵の動きが見えない」「何を見ているのか分からなくなる」「単純に眼が痛い」などといった意見がユーザーから上がった。
また、カメラワークの問題としては巨大なボスと相対した際に顕著に見られた。
「ELDEN RING」には敵をカメラから見失わないようにするロックオン機能があるのだが、これを使用すると、巨大なボスが激しい動きをする度に画面がとても揺れる。
最早、自身のキャラクターは見えるわけもなく、画面いっぱいに現れるボスは身体の一部しか映らず、攻撃のタイミングに合わせて回避ボタンを押すなど至難の業となってしまった。
難しさと理不尽さ

ボスの異様な強化、杜撰なカメラワークなどによって、度々「ELDEN RING」の大型拡張コンテンツは難しいという評価ではなく、理不尽であるという評価をされることが多い。
特に派手なエフェクトによってカメラの視認性を著しく阻害していることに対しての不満が多い印象だ。
「ボスを強くするのと、ゲームの演出がプレイヤーを妨害するのはおかしい」「フロムソフトウェアは難しさと理不尽をはき違えている」などといった意見がある。
更にボスが繰り出す攻撃の回避方法についても「攻撃の種類が多くて回避方法が分からない」「どの攻撃をされているか分からない」などといった意見があった。
死にゲーには高難易度という要素は切っても切り離せないものだ。
しかし、難易度を上げるために何でもしてしまうことはユーザーに受け入れられないようである。
無闇な難易度調整は「難しさ」ではなく「理不尽」として捉えられてしまうようである。
自由度に対する難しさ

無闇な調整は理不尽として捉えられてしまうと記述したが、ここにこれからの死にゲーが直面する課題が現われているように思う。
自由度とはゲームにおけるプレイヤーが選択することのできる範囲を表す。
プレイヤーが「こうしたい」という願いをどれだけ叶えられるかが「自由度」と呼ばれるのだろう。
しかし、「自由度」を上げれば上げるほどプレイヤーが操作するキャラクターは強くなるのだ。
レベルを上げたいと思ったら上げることができ、ソロでもマルチのように戦いたいと思えばNPCと共闘することができる。
そのような中で手強いボスを用意するとなれば、理不尽と思えるようなボスを登場させてしまうことも必然であるのだろう。
より強力となったプレイヤーに対抗するためには更に強力なボスが必要なのだ。
加えて古くから死にゲーを親しんできたプレイヤーはゲームスキル自体も上がっている。
古参のユーザーが「ELDEN RING」のシステムをあますことなく使用すれば、最早、「ELDEN RING」は高難易度とは呼べなくなってしまうかもしれない。
だからと言って古参のユーザーにゲームを楽しみたければ縛りプレイを行えと強制するのも違うのではないだろうか?
この課題を解決するために用意されたのが今回のような理不尽にも捉えられるボスの登場だろう。
しかしその試みは「理不尽」とされ、ゲームの評価を下げる形となった。
おそらく死にゲーはゲームの進化によって求められる自由度と高難易度の両立が今後の課題になると考えられる。
しかし、今回のように自由度と高難易度を共存させてしまえば「理不尽」とされてしまう危険性がある。
であるならば、今後、死にゲーが向き合う課題はいかに制限がある中で自由度をプレイヤーに与えることができるかどうかであるように思う。
フロムソフトウェアの旧作のようにプレイヤー側に制限(キャラクターの操作性や、武器の強さ等)があれば、ボスを異常に強化しなくてもよくなるはずだ。
ただ、プレイヤー側の制限も、「SHADOW OF THE ERDTREE」のようなカメラの阻害であれば理不尽と捉えられかねないだろう。
難しいと感じながらもクリアの達成感を味わえる死にゲーはゲームが進化するほど、自由度と高難易度の調整に苦労していくことだろう。
しかしながら、死にゲーを愛するファンは多い。
これらの課題に真摯に向き合いさえすれば、彼らの心は離れていかないだろう。