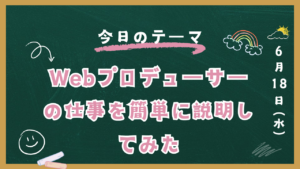映画としてみる宇宙戦艦ヤマトシリーズの魅力を徹底紹介します
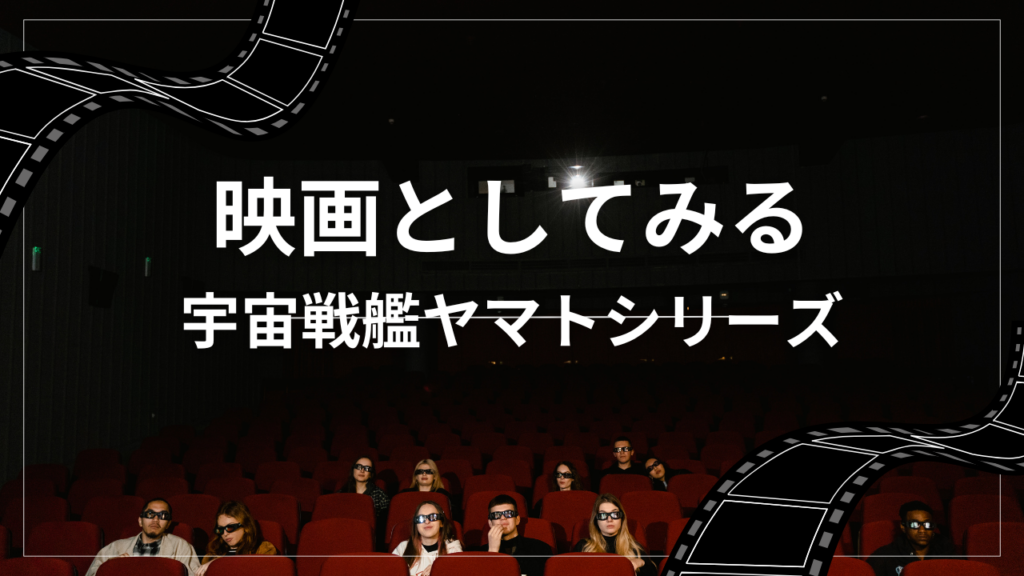
1977年8月5日夜……異様な光景を新宿や渋谷の映画館で人は目にすることなる。
『宇宙戦艦ヤマト』の公開前の大人や青少年たちの行列が映画館を取り巻いて異様な熱気に包まれていたという。

当時アニメ映画と言えば、あくまで「まんが映画」とよばれ、所詮は東映まんがまつりなどの分野で子どもたちを集めているというのがせいぜいの、全く映画界には歯牙にもかけられないような存在であった。
だがこの夜、日本映画界では初めての経験となる「徹夜組」の行列の出現と、それを構成するのが大人や青少年たちであるということが、後世の目から見るといかに重大な「事件」であったか、おそらく当事者たちにさえ、掴みきれていなかったに違いない。

1977年8月5日夜の徹夜組はアニメが『宇宙戦艦ヤマト』という作品が「大人の鑑賞」に耐えるものであるということを示し、のちのアニメや特撮、声優、音楽、ゲームなどのオタクカルチャーに大きく、そして、深甚たる影響を与えるに至ることを、この時だれが想像したであろうか?
そしてここに、オタク文化という20世紀末から21世紀に至るまで日本の文化の中心的存在となるオタク文化のあらゆる種子が埋め込まれていたということを、気がついたであろうか?
ひらめきや直感などによってセンスを広げる人間も確かにいたし、オタクカルチャーの元祖的存在は別のものになると唱える者も多いだろう、しかし、『宇宙戦艦ヤマト』の偉大さは、そのひらめきやアイデアにあるものではない。
その商業的成功によって、オタクカルチャーを陽の目に魅せた所が最大の功績であると筆者は考えているのである。
ゆえに1974年にテレビ放映され、その後の再放送を続けてファン層を広げ続けてきていたTV版『宇宙戦艦ヤマト』は多くのオタク的趣味を持った者たちの揺籃期であったと言えるのではないだろうか?
まだまだ『映画』というものが時代の映像芸術として花形的そんざいであった、1970年代、『宇宙戦艦ヤマト』という映画が興行収入21億円(1970年代の21億という数値の大きさを見よ)と大成功を収めたこと。
そして、徹夜組になるほど多くの大人たちや青少年たちに足を運ばせたことに世の中は震撼したのである。
『アニメはもうこども向けのエンターテインメントではない。立派な社会人や青少年の鑑賞に耐えるエンターテインメントである』と。

さらに『宇宙戦艦ヤマト』は後のオタクカルチャーに大きな影響を与える功績を残している。それがアニメ声優のアイドル化と音楽サウンドトラックである。
ヤマトの主人公である古代進の声優富山敬は、なんと収録に出待ちが表れるほどの人気であり、彼のラジオやコンサートでは黄色い声が飛び交ったという。
現代のアニメ声優の人気は男女ともに凄まじい物があるが、声優のアイドル化という意味では富山敬が元祖的存在では無いだろうか?
またこちらのほうが重要かもしれない。
ヤマトの音楽は当時の人気歌手デュオであったザ・ピーナッツの作曲を手がけるなどヒットメーカーであった宮川泰が担当しており、当時のアニメからすると破格の力の入れ方でオーケストラのサウンドを起用したのである。
このヤマトのオーケストラサウンドに感動したファンたちは争ってヤマトのサウンドトラックを買い込んだものであった。
そして、いつしかヤマトのテーマ曲は吹奏楽の定番となり、またヤマトがきっかけで音楽家を目指した人間も数多いという。
また主砲の発射音や爆発音などの柏原満による効果音も忘れてはならない。
ヤマトの効果音は、それ専用に作られ、も後々まで使われることとなったそれを聞くだけでファンなら、なんの効果音かはっきりと分かるほどの耳に馴染んだ効果音となっていくのである。
実際、ヤマトファンであったアニメ監督庵野秀明は、ヤマトの主砲音が好きなあまりに自分の作品の『ふしぎの海のナディア』のノーチラス号の主砲音として、わざわざ許可を取って使用しているのである。
こうしたヤマトシリーズの音楽や効果音などのサウンドトラックの累計販売数はなんと1000万枚にものぼったという。

この『宇宙戦艦ヤマト』が成功するにあたっては、総監督の松本零士や音楽宮川泰といったクリエイターたちにスポットを当てていくべきなのだろうが、ここで注目したいのは、『宇宙戦艦ヤマト』のプロデューサーである西崎義展という人物である。
とにかくこの人物は胡散臭い。
元々が音楽プロデューサーをして食いつないでいた頃、創価学会の創価学会系の民主音楽協会(民音)のイベントを手伝うことによって糊口をしのいでいたという。だが、ここで創価学会に大きな人脈ができたことが後の伏線となる。
彼は手塚治虫の虫プロダクションが経営不振に陥っていた時、その立て直しをするために手塚プロダクションに雇われるが、その権利調停や独断でアニメ化をしてしまうをして手塚治虫と折り合いが悪く決裂してしまった模様だ。
ただ、この頃に作られた『海のトリトン』や『ワンサくん』の完成度などをみるにつけ、手塚治虫と「原作者とプロデューサー」という関係を築けていれば、もっと幸福な未来があったのではないかと、少し残念に思う。
そういった虫プロ時代を経てオフィスアカデミーとして、長年企画を温めていた『宇宙戦艦ヤマト』の企画を進めていく。
有名な『宇宙戦艦ヤマト』の主題歌を作詞した阿久悠によれば、彼は企画の説明をしていくうちに感動のあまり涙を流しながら、主題歌の作詞を頼んだという。
この頃から、死ぬまで西崎にとって『宇宙戦艦ヤマト』は彼の夢であり自らが乗り込みたい船であったのであろう。

だが、こうして1974年にテレビ放映した宇宙戦艦ヤマトであるが、そのTV版は視聴率の関係、予算の関係、納期の関係などで52話のところを26話のところを打ち切られてしまう。
一説には『アルプスの少女ハイジ』『影の軍団』などの裏番組が強かったという話もあるが、一番大きかったのが、『宇宙戦艦ヤマト』の作画が間に合わなくなってきたという説が現場では一番大きかったようだ。
しかし、『宇宙戦艦ヤマト』は再放送のときに子どもたちやオタク気質のある青少年たちの心をガッチリとつかみ人気コンテンツとして成長していくのである。
西崎義展という人物は、毀誉褒貶ある人物であるが、この時期に彼がとった行動については、やはりこの人こそが「宇宙戦艦ヤマトの父」であると言わざるを得ない。
彼はオフィスアカデミーの単独配給を覚悟に『劇場版宇宙戦艦ヤマト』を作らせると同時に全国を回ってファンクラブの結成と盛り上げ、全国の興行関係者にあい上映をとりつけるなど、まさに日本中をヤマト行脚していったのである。
ちなみにそれだけでは実績のないアニメが上映されるはずもなく。西崎は、創価学会との古いパイプを利用して「100万枚のチケットを引き受けますから」という口説き文句で全国の興行関係者を説得したのである。
こうしてオフィスアカデミーの自主興行でありながら全国規模での『劇場版 宇宙戦艦ヤマト』の大ヒットは、映画業界における西崎にヒットメーカーとしての不動の地位を与えることになる。そして物語はまだ続くのだ。
おそらくはこの成功により西崎は(『宇宙戦艦ヤマト』の本編は映画だ)と強固に思っていたのではないだろうか? 『宇宙戦艦ヤマト』シリーズは頑なに劇場版にこだわって作られている。
空前の大ヒットを示した西崎と『宇宙戦艦ヤマト』は当然のことながら続編の作成を可能にする。
それが『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』である。
1978年8月5日に東映系で放映されたこの映画は興行収入43億円という、のちに1991年公開の『魔女の宅急便』が興行収入43億円を記録するまで、アニメ映画の興行成績(金額ベース)の記録を保持した。インフレ率を計算すると、さらに莫大な収入になる。
白色彗星帝国というシリーズでも最大の敵役として名高い敵に加え、その恐怖を煽る『白色彗星のテーマ』のパイプオルガンの音色に映画館の観客たちは圧倒された。
余談だが、このアニメやゲームのラスボスたちのテーマがパイプオルガンの荘厳な響きとなるという「お約束」まで作った『白色彗星のテーマ』。
この当時はパイプオルガンを演奏できる場所が一つしかなく、その武蔵野音楽大学のベートベンホールで泰の息子、宮川彬良がパイプオルガンの経験もないまま必死で演奏したという。
このあたり『宇宙戦艦ヤマト』の音楽にかける予算と人々の手間暇のかかりようは他のアニメとは一桁違っていると行っていいだろう。こと音楽については、常に最先端を行っているのは間違いない。

『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』の大きな特徴に、登場人物が死にまくるというものがある。
『さらば』と名づけた以上、当初はこの作品をもって『宇宙戦艦ヤマト』を完結するつもりであったらしい。
多くの主要人物の死の連鎖の果てに、ヤマトは主人公古代進とヒロイン森雪と反物質の女テレサともに敵の最終形態である巨大戦艦に特攻を仕掛け、ともに宇宙の星のような爆発とともに消え去るのである。
筆者もこの映画をリアルタイムで見ていたが、幼い心でも映画館が異常なテンションになっているのに気づかざるを得なかった。
すすり泣く人、食い入るように画面を見つめながら涙を流している人などなど、あまりの人々の殺気とも言えるテンションに、夜中にひきつけを起こしたほどであった。
そして最後のテロップで
「ヤマトを愛して下さった
皆さん・・・・さようなら。
もう、二度と 姿を
現すことはありません
でも きっと 永遠に
生きているでしょう
あなたの胸に
心に
魂の中に」
流れるのである。確かに映画の感動そのものもあったろうが、このテロップによって「もう、『宇宙戦艦ヤマト』は見られなくなってしまうのだな」という作品世界への決別を惜しむ人も多かったに違いない。
そして、それは裏切られた?
いや裏切られなかったのかもしれない。
映画に続いて始まった『宇宙戦艦ヤマト2』では明らかに別な世界線で展開されて地球は白色彗星帝国との戦いを進んでいくのである。
そして終盤、最後の敵に特攻するのは反物質の女テレサのみであり、ヤマトや主だったキャラクターはほぼ全員帰還するのである。
この変化についてはスタッフの一人安彦良和が「儲かっちゃったので続編作りたくなっちゃったんだよ」と言っているが、おそらくは事実だろう。
何より当時の換算で興行収入43億円を稼いだコンテンツである。
これを「作品的に完結したから」といって捨てられる人物はそうそうに存在しないだろう。
いや、いたとしても周囲に43億円のコンテンツ規模にあやかりたい人物が多数存在するのである。

西崎義展も松本零士も自分一人のものではなくなっていたのではないだろうか?
日本屈指の巨大コンテンツとなった『宇宙戦艦ヤマト』は『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』では終われなかった、終わることを許されなかったとも言えるだろ。
確かに多くのヤマトファンからすると『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』で終わっていれば伝説のアニメ作品として歴史に名をのこしたであろうという意見は多い。
そもそも、コンテンツというものは生き物であって、その生命活動を停止するとすぐに風化してしまうのも事実なのである。ここから『宇宙戦艦ヤマト』というコンテンツは見事なまでに迷走を続けていく。
だが、その迷走があったからこそ、『宇宙戦艦ヤマト』というコンテンツは延命され、後に奇跡的な復活を見せるコンテンツになったと筆者は思っている。
「死んだ伝説」よりも「老耄しつつも生きたコンテンツ」としてその後40年以上も延命されていくのである。
まだ『さらば宇宙戦艦ヤマト』の感動と人気が残っている時期にフジテレビ系列で特別番組枠として放映され、後に劇場公開もされた1979年7月31日の『宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち』は、生き残りと新メンバーを加えて、『宇宙戦艦ヤマト』シリーズでは貴重な平時での発進を行なった作品だ。
次なる敵は暗黒星団帝国という存在で、古代率いるヤマトとデスラーの残存艦隊が共闘するというのが見せ場となっている。
全体的に手堅く作られており、けっしてヤマトファンの評判も悪くない作品である。
そのためか最高視聴率も30%を超える数字を叩きだしたという。
本来なら『宇宙戦艦ヤマト』は日テレや読売系列で放映される作品だが、特に決裂もしていないままフジテレビ系列で特別番組を組まれるというあり、当時のヤマトブームの凄まじさが伺えるというものである。
だが、この『宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち』の続編として作られた、1980年8月2日に公開された劇場版の『宇宙戦艦ヤマト ヤマトよ永遠に』がひどかった。
せっかくイスカンダルから帰れた古代守があっさり死に、その子であるサーシャは1年で16歳ぐらいの女の子になっていたり、あまりにもさらにメカニック的に強化されたヤマトが強すぎて無双シーンばかりになっていたり、枚挙に暇がない。敵はヤマトを恐れるあまり「我々は100年後の未来の地球なのだ」などと名乗りだして偽装工作にのりだすが、ロダンの「考える人」の手の位置が違っているというだけで見破られてしまうのだ。
そして波動エネルギーが暗黒星団帝国に致命的な打撃を与えるため、暗黒星雲ごと波動砲を吹き飛ばしてしまい、新たな銀河が生まれた! というオチに終わるのだ。
しかし、このめちゃくちゃなシナリオなのだが、悔しいことに当時最高のアニメーターたちが起用されているため、戦闘シーンは実に迫力があり、あらゆるシーンが1980年の作品なのに今見ても作画が素晴らしいとわかる一品なのである。
その美しい作画と、宮川泰の爽快感あふれる名曲「新銀河誕生」を聞きながらだと、エンディングに感動させられてしまうのである。本当アニメーションって音楽が大事である。
筆者は悟ったのであった「宇宙戦艦ヤマトはSFでもスペースオペラでもない宇宙大歌舞伎」なのだと。
ところがそういった内容にもかかわらずやはりヤマトは劇場版では強いのである。興行収入25億円をたたき出している。
1980年10月1日 、『宇宙戦艦ヤマト』は原点に帰り、テレビシリーズ『宇宙戦艦ヤマトⅢ』を放映する。
銀河をデスラーが作った「ガルマン・ガミラス帝国」、ソ連をモチーフにした新たな敵「ボラー連邦」が存在し、銀河の覇権を争い、地球連邦は例によってその戦いに巻き込まれてしまうという、銀河を舞台にした戦記モノの色を濃くした期待作であった。
だが当時はすでに『機動戦士ガンダム』ブームで「ヤマトなんて古臭いよな」という声をよく聞いた時代でもあった。
また、視聴率の比較対象とされるのが、当時はまだまだ視聴率の王様であったナイター巨人戦であったのも不幸であった。
全52話であったが、視聴率が15%と「低迷したため」半年2クールに短縮されてしまったのである。
前述したが、すでにこのころになると『宇宙戦艦ヤマト』は「古臭いもの」とアニメファンたちからはそっぽを向かれていたのは否めなかった。
それから3年間、『宇宙戦艦ヤマト』シリーズは沈黙を続ける。
そして1983年3月19日、ついにシリーズ最終作と銘打って『宇宙戦艦ヤマト 完結編』が上映される。とはいっても、もはやこの頃のアニメファンたちのメは冷ややかで「どうせまた復活するでしょ」という声が多かったのも事実である。
しかし、この完結編は宮川泰に加えて羽田健太郎が音楽担当に加わり、また「原画袋に現金が貼り付けてあった」と言われるほどの制作費をかけて作られた作画のクオリティーは極めて高かった。

それは現代の目で見ても遜色ないほどであり特にエンディングのアクエリアスが地球に接近したときに飛来する水滴と水柱の表現は、凄まじいものがあった。
また宇宙戦艦に突撃する騎馬兵という、前代未聞のシーンがあるが、これが音楽と作画のクオリティーの高さも相まって珍シーンと思われるものが、きちんと名シーンとして見られるようになっているのが見事であった。
とはいえ、シナリオ面に関してはとても褒められたものではなく、いきなり冒頭で二重銀河によって銀河系の文明が崩壊。
そう『宇宙戦艦ヤマトⅢ』で好評であったガルマン・ガミラス帝国とボラー連邦の国家設定を一度おじゃんにしてしまっているのである。
その割に地球には何の影響もなく、ただ単にシナリオ上のご都合主義として、Ⅲの設定を白紙に戻すという荒業でしかないことがよくわかる。
そして、今度の敵はアクエリアスという水の惑星をワープさせて、地球を水没させて征服しようとするディンギル帝国である。
これに対向するためにヤマトが出撃するわけだが、シリーズ最終作と銘打ったためか、シリーズ1作目の『宇宙戦艦ヤマト』で感動的な死を遂げた初代艦長沖田十三が、「誤診」であったとして復活してしまうのである。
これには悪い意味で驚いた観客も多かったが、前述の二重銀河による文明崩壊とともにあまりのご都合主義でシナリオ面に期待するのは諦めた人も多かっただろう。
そうなのだ、この『宇宙戦艦ヤマト 完結編』は、ストーリーを全体的に見てしまうとそのご都合主義ぶりに目を覆いたくなるのだが、シーン単位で見てみると1983年当時の最高技術の作画と、本格的なオーケストラの編成で録音するためにコロムビアレコードのスタジオをふたつぶちぬいてひとつにしてしまったというエピソードからも伺える音楽の豪華さの要素をもって、実に素晴らしい映像に仕上がっているのである。
つまりはシナリオの整合性やご都合主義に目を惑わされることなく、何度も書くが「宇宙大歌舞伎」として見る分には最高の映画として仕上がっているのである。
そのように見ていたファンも多かったのではないだろうか?
かなり宇宙戦艦ヤマトブームは去り、ヤマトが飽きられ、ヤマトが古臭いものとして見られていた1983年ごろのアニメファンの世相ではあったが、興行収入は17.2億円と健闘している。
そして、たいていのアニメファンたちが「どうせまた『復活』する」と冷ややかに見ていたのとは裏腹に、『宇宙戦艦ヤマト』は2009年まで、なんと26年以上も復活することはなかったのである。
実際には『宇宙戦艦ヤマト復活篇』は1994年に外伝的作品『YAMATO2520』とともに制作発表がなされたが、資金難で頓挫してしまっている。
その後、1997年にはプロデューサーの西崎義展が覚せい剤所持、1999年には銃刀法違反により現行犯逮捕される。2003年には懲役5年6月が確定し収監されてしまう。

さらには、この間に松本零士が1999年に『宇宙戦艦ヤマト』などの著作物の著作者が、松本零士であることの確認を求めて、松本が西崎を提訴する。
これらの不祥事と西崎・松本裁判によって、ただでさえ過去のもの、古臭いものと思われていた『宇宙戦艦ヤマト』というコンテンツのイメージは地に落ちたといってもよかったであろう。
西崎・松本裁判は『宇宙戦艦ヤマト』の著作者人格権は西崎に帰属するという判決が出て、西崎も刑期を終えて出所する。その上で『宇宙戦艦ヤマト 復活編』が制作されるのである。
2009年12月12日『宇宙戦艦ヤマト 復活編』は上映される。
26年ものブランクがあり、しかも西崎の不祥事や裁判があったにもかかわらず全国233館で上映されたというのは、『宇宙戦艦ヤマト』というコンテンツがこれまでの興行成績で積み上げた実績であろうか?
だが、この間にヤマトを支えてきた偉大なる音楽家宮川泰、羽田健太郎が没し、声優の富山敬も病没していた。
そのため、『宇宙戦艦ヤマト 復活編』はクラシック音楽がBGMとして使われ、「宇宙大歌舞伎」としての醍醐味も何もあったものではなくなってしまう。
なによりファンたちをがっかりさせたのが柏原満の主砲の発射音や爆発音などの効果音も変更されていたことであろう。
ヤマトはヤマトの音と音楽があってこその「宇宙大歌舞伎」ヤマトであるということを思い知らされた作品でもあった。
後に効果音と音楽を出来る限り『宇宙戦艦ヤマト』シリーズのものを使用した『宇宙戦艦ヤマト復活編ディレクターズカット版』はファンにも好評である。
『宇宙戦艦ヤマト 復活編』の興行収入はわずか3.8億円という、これまでの『宇宙戦艦ヤマト』シリーズの興行収入としてはさびしい物におわってしまう。
不祥事、裁判に続く、頼みの劇場版の不振、多くの人が、これで『宇宙戦艦ヤマト』というコンテンツは終わりか? と思ったに違いない。
頼みの綱は意外な所からやってきた。
2010年12月1日に公開された『SPACE BATTLESHIP ヤマト』である。
なんと実写版の『宇宙戦艦ヤマト』シリーズという、誰もが時期的にも「これは失敗するだろう」と思われていた作品である。
木村拓哉が主人公古代進を演じていたため『キムタクヤマト』などと口の悪いヤマトファンには言われていたが、初代のストーリーに『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』の要素を加えたストーリーは、決して出来の悪いものではなく、純粋にエンターテインメントとしてよく出来ていた。
今でも頑固なヤマトファンの中にはその存在すら認めていない人も多いが、虚心坦懐に見て「わかりやすい」ストーリーと展開は、ヤマト入門者にとってはよかったのだろう。
ヤマトファンやアニメファンだけでなく一般人の観客も集めたこの作品は、近年のほうがからすれば大成功の部類に入ると言えた。
なんと興行収入は40億円。時代や物価から単純には比べることはできないものの、数字だけをみれば『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』以来の数字である。
これによって『宇宙戦艦ヤマト』というコンテンツは息を吹き返す。
続いて登場するのが『宇宙戦艦ヤマト』シリーズの真の後継者とも言える存在、初代宇宙戦艦ヤマトのリメイク作品『宇宙戦艦ヤマト2199』である。
元々は2007年当時から動いており、『宇宙戦艦ヤマト 復活編』、『SPACE BATTLESHIP ヤマト』とともに平行して進んでいた企画であったが、『宇宙戦艦ヤマト 復活編』の興行的大失敗を思うと、『SPACE BATTLESHIP ヤマト』の興行的成功がなければ進まなかった企画でもあったろう。
ともあれ40年近く昔の作品のリメイクである。
もはや多くの声優やスタッフが引退もしくは鬼籍に入っているため、声優やスタッフは当然新しく変わっているが、その総監督の出渕裕を始めとして、スタッフの多くが「宇宙戦艦ヤマトを見て育った」という世代になっているのが特徴的であると言えるだろう。
かつてのヤマトファンがアニメの現場に入り、そしてかつて憧れた夢の戦艦「宇宙戦艦ヤマト」に乗り込むことになったというわけである。
当然スタッフの士気は高く、そのテンションは作品を見ていてもわかる。
そのスタッフたちの愛がひしひしと感じられるのが、特報として流れた主砲の音が柏原満の「ヤマトの主砲音」だったことである。
これでファンたちは「スタッフはわかっているな」と安心したものであった。
そして、続いて発表されたのが音楽担当は、宮川泰の息子で、『マツケンサンバ2』など独自に音楽家としての才能を発揮している宮川彬良であるということであった。
おそらくは宮川泰、羽田健太郎亡き後、ヤマトの音楽を任せるには最高の人物であることは間違いない。
やはりファンたちは「スタッフはわかっているな」と安心したものであった。
そして2012年4月7日、『機動戦士ガンダムUC』が端緒となり、後にアニメ業界では流行する「先行イベント上映」という形で『宇宙戦艦ヤマト2199』が7章にわたって上映される。
このイベント上映は、実に好評のうちに終わり、ヤマトのDVD/ブルーレイの販売も三万枚近くに販売している。
その後2013年4月7日にTBSのテレビ放映が始まり、賛否両論はあったものの概ね好評のうちに終わる。
賛否両論とはいうが、なによりも『宇宙戦艦ヤマト 復活編』が終わった当時の「宇宙戦艦ヤマトというコンテンツは終わったな……」というような時代と比べれば賛否両論がある事自体が幸せと言えるだろう。
実際、先行上映の観客数、テレビ放映の録画率、DVD/ブルーレイの販売数から言っても『宇宙戦艦ヤマト2199』は好成績を収めたアニメと言ってもよく、まずはコンテンツとしては『復活』したと言ってもよい。
そんな『宇宙戦艦ヤマト2199』は初代ヤマトと同じく総集編的劇場版『宇宙戦艦ヤマト2199 追憶の航海』が10月11日に公開された。
こちらはアニメの総集編として作られているが、その思い切ったカットについて賛否両論ある模様である。
また12月6日には完全新作アニメ劇場版『宇宙戦艦ヤマト2199 星巡る方舟』もまた公開された。
全く予想しなかった展開と、メカニックについてもこちらは好評の模様である。
興行収入はこの原稿を書いている時点では明らかになっていないが、是非とも成功して今後も『宇宙戦艦ヤマト2199』としてのシリーズ展開を行ってもらいたいものである。

40年という長い年月において、何度も挫折しながら不死身の宇宙戦艦ヤマトのように息を吹き返し続けてきたコンテンツ、『それが宇宙戦艦ヤマト』であり、そういう視点でDVDやブルーレイなどで時系列をたどりながらみてみてはいかがであろうか?
日本のアニメ史というものの中軸にあり続けてきたシリーズだけに、趣深いものがあるに違いない。ぜひともオススメする。