キャリア官僚への道のりとは?国家総合職試験に一発合格する方法
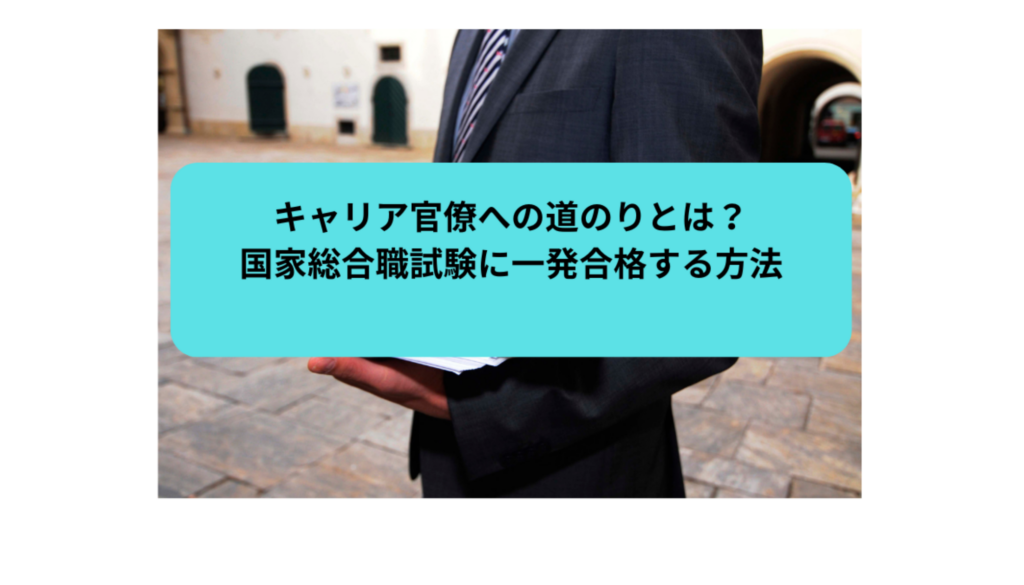
この記事では、キャリア官僚として働くことを目指す方に向けて、国家総合職試験(大卒程度試験)【法律区分】の概要や科目ごとの効果的な勉強法、最終合格までの流れについて紹介します。
自身の合格体験を踏まえて具体的に解説しているので、これから勉強を始めてみようという方や勉強に行き詰まっている方、最終調整に入った方、法律区分以外の受験を考えている方にも参考になる内容となっています。
ぜひ、最後までご覧ください。
キャリア官僚という仕事

キャリア官僚とは、国の中枢を担う霞が関にある中央省庁で、政策の企画立案や法案の作成に携わる人たちを指します。
官僚は国の中核となって重要なプロジェクトに携わる職であるため、非常にハイレベルな競争を勝ち抜いたうえで、中央省庁に採用される必要があります。
求められる基礎能力や専門性が高度な分、その仕事には行政として国民生活の基盤を担い、重要な意思決定を行うやりがいがあります。
さらに、行政のマネジメントに携わることで、幅広く専門的な知識や経験、スキルを得ることができるというメリットも存在します。
また、採用試験の難易度が低いノンキャリア官僚に比べて出世スピードも早く、国政に直接かかわる仕事に携わることが可能です。
そこで、キャリア官僚として働くために必要不可欠なチケットとして、まずは国家総合職試験の合格を勝ち取らなければなりません。
試験の難易度・合格者の出身大学

国家総合職試験は専門に応じた11の試験区分に分かれる「春試験」と、教養区分の「秋試験」に分けられ、いずれかに合格することで希望省庁への官庁訪問(採用面接)への参加資格を得られます。
2024年春試験の申込者数は「法律区分」が7325人と一番多く、次いで「政治・国際・人文」区分が1649人となっています。(人事院調べ)
法律区分が人気な理由としては。採用人数の多さ、対策のしやすさ、官僚になってからの有用性などが挙げられると言われています。
法律区分の合格者数は296人で、その倍率は24.7倍となっており、非常に難易度の高い試験であることがわかります。
出身大学を見ても、1位が「東京大学」の189人であり、2位が「京都大学」の120人で、合格者の65.2%が国立大学を占めています。(院卒者・大卒程度を合わせた数字)
このように、非常にハイレベルな試験であることは確かですが、効果的な学習計画を立て、着実に過去問を解いていけば、遅くから勉強を始めたとしても十分合格が可能です。

たしかに倍率は高いですが、申込者の中には民間企業を併願している人も多いため、申込んだ上で受験を断念する人や、1次試験合格後に辞退する方も一定数存在するからです。
また、以前は東大出身者が圧倒的多数を占めていましたが、採用試験が見直されたことで近年では東大以外の大学の地方国立大学や私立大学が合格者数を伸ばしてきています。
さらに、受験の費用は無料で、合格した場合の資格は3年間継続します。
そこで、少しでも試験に挑戦することを考えている方は、この記事を読んだ今すぐにでも勉強を開始することを強くおすすめします。
以下に、教養区分を除けば、最も申込者数の多い法律区分の試験科目と効果的な勉強方法を紹介します。
国家総合職・法律区分の試験科目

国家総合職・法律区分には一次試験と二次試験があります。以下に、それぞれの試験科目と勉強法を紹介します。
試験科目(2024年度のもの)
・一次試験 選択式(マークシート方式)
基礎能力試験 (30題) 試験時間:2時間20分
- 知能分野(24題) 文章理解 (10題)、判断・数的推理 (14題)
- 知識分野(6題) 自然・人文・社会に関する時事、情報
専門試験 (40題) 試験時間:3時間30分
必須問題
憲法 (7題)、行政法(12題)、民法(12題)
選択問題 (9題)
商法(3題)、刑法(3題)、労働法(3題)、国際法(3題)、経済学・財政学(6題)の18題から任意の9題解答
・二次試験 記述式
選択問題 (2題) 3時間
憲法、行政法、民法、国際法、公共政策の中から2題を選択
政策論文試験 2時間
人物試験
※この他に、英語試験(TOEICやTOIFL等)の加点があります。
最終合格のためには、選択式の一次試験合格が鬼門と言えます。一般的には、例年、基礎能力試験で約50~60%以上、専門試験で約70~80%以上の正答率が合格の最低ラインと言われています。
基礎能力試験の知能分野で必要とされる能力は、高校でいう現代文、英語、数学であり、中でも判断・数的推理は範囲が幅広いうえに難しく、文系出身の受験生には苦手とする人も多いです。
専門試験は似た内容の問題が繰り返し出題される傾向があるため、過去問を繰り返し解くことが突破のカギとなります。
一方、一次試験を合格してしまえば記述式の二次試験で落されることは少なく、専門記述、政策論文試験、人物試験で約60%以上の点数を取ることができれば合格可能と言われています。
また、二次試験の記述式は一次試験の勉強をしっかりと行っていればそれほど多くの時間をかけることなく合格基準に達することができます。
合格に必要な勉強時間とスケジュールの例

合格ライン到達に必要な時間は、一般的には約1500時間といわれています。1年で行うとすれば、週28時間1日当たり4時間という計算になります。
しかし、大学3~4年の時期は就職活動の時期と大きく重なっているため、特に民間企業と併願する場合、勉強との両立が大きな課題となります。
また、国家公務員一本に絞るとしても、最終的に採用されるためには説明会や採用担当者との面談など官庁訪問(採用面接)に向けた事前準備にかける時間も考えて勉強のスケジュールを立てなければなりません。

そこで、最もおすすめするのは、試験勉強を本格的に進める前に、民間就活を行っておくという事です。これには2つのメリットがあります。
- もし内定(内々定)をもらえれば、精神的に安心材料になるうえに、自己PRにもなる
- 就活に必要な自己分析や業界研究を行う事ができる
周囲が続々と就職先を決めていく中、内定をもらえないまま勉強に集中するのは難しいうえに、心理的にプレッシャーを感じてしまう可能性があります。
また、春試験合格後から官庁訪問までは、1か月ほどしかなく、自己分析や業界研究に使える時間がほとんどありません。
そして、就活に必要な力を身に着けるためには実際にエントリーシートを出してみて、面接を経験するのが一番です。
就職活動を進めていくと、仕事に求める事や自分の価値観、志向がわかってきて、「なぜ民間企業という選択肢がある中で公的セクターを選ぶのか」という志望動機がより明確化するというメリットもあります。
もちろん、他の公務員試験を併願したり、秋試験にトライしたりするのも非常に有効であると言えます。
そこで、理想的なスケジュールを以下に紹介します。
~合格までのスケジュール~
大学1年~3年の春
国家公務員を志したら、計画を立ててすぐに勉強を始める。
興味のある省庁の説明会やインターンシップに参加する。
試験科目と被る大学の授業があれば、積極的にとる。
大学3年の夏~秋
知識を整理し、理解できていない範囲に重点的に力を入れて勉強する。
行きたい省庁や、興味のある民間企業のインターンシップに参加する。興味がある省庁の説明会には、何度でも足を運んで、採用担当者に覚えてもらう。
(参考:官庁訪問で回れる省庁は第一希望~第三希望までの3つ)
早く募集を行っている企業の面接に参加し、内定(内々定)を得られるように努める。
一次試験直前は一次合格に注力する。それまでは二次試験の勉強も同時に進める。
大学3年の冬
一次試験が終わったら二次試験の勉強に本格的にシフトする。
大学4年の春
二次試験合格後、官庁訪問
このようなスケジュールで勉強を進めていくと良いでしょう。
特に、2次試験の人物試験の得点比率が増加したり、出身大学欄を削除し、学歴にとらわれない面接が行われたりと、公務員試験に人物面で優れたものを持った人を積極的に採用しようという機運が最近高まってきていると言われています。
このような傾向からも、勉強を進める中で自己分析や業界研究を疎かにしないことが求められているといえます。何をするにしても、早めの行動は肝心です。
独学と通信講座どっちがいい?独学で合格を目指す場合の注意点

どちらの教材を基に進めるにしても、メインは過去問演習です。ですので、過去問題集を手に入れることは必須と言えるでしょう。
そして、合格は独学でも可能ですが、効率的に学習を進めたい方は、通信講座をお勧めします。
通信講座を用いるメリットとしては、次のようなことが挙げられます。
- 法律を初めて勉強する方でも基礎知識や論文の書き方を詰め込める
- 多くの場合、模試を行っていたり、面接対策を行ってくれたりする
- 自習室を活用できる場合がある
- 模試や本番の試験での自分の位置を把握できる
よって、通信講座を用いると、蓄積された情報を基に、内定まで手厚くサポートしてくれるため、効果的に着実に合格基準に達することができると言えます。
また、国家総合職試験は幅広い範囲から出題され、試験の形式や把握しておかなければならない情報が複雑なので、独学で行う場合は予備校や人事院のHPで最新の情報をチェックする必要があります。
特に、国家総合職試験は配点の把握と、どこで何点取るかの計画を立てて勉強を進めていくことが必要なので、前年度から出題範囲や配点の変更があった場合、注意しなければなりません。
そして、教材での勉強とは別に、人事院面接や官庁訪問の情報も仕入れておく必要があると思われます。
それでは、試験ごとの勉強法について具体的に解説していきます。
第一次試験(選択式)の勉強法

基礎能力試験
配点を見るとわかるように、基礎能力試験は知能試験が8割を占めています。そして、知識分野は出題範囲が広い割に、残りの2割しか出題されません。
よって、自分の学習状況や試験までも残り時間も踏まえたうえで、知識分野に使える時間を計算するべきでしょう。
そして、知能試験については、学生時代に培ってきた現代文、英語、数学の能力が物を言わせます。現代文と英語については趣旨把握、空欄補充、文の並べ替えといった問題形式ごとに解答のコツをつかんでおきましょう。そのためには、過去問を繰り返し解いて慣れておく必要があります。英語については、英語試験の学習の際に、大学受験レベルの単語で覚えていないものがあれば覚えておきましょう。
判断・数的推理については、多くの問題が高校受験レベルの知識があれば解ける内容となっておりますので、文系の学生でも十分突破可能と言えます。
分野ごとに出題数が大体決まっておりますので、解ける問題を増やしていくイメージで勉強すると良いと思います。
専門試験
どの科目も過去問から同じ論点が7割ほど出題され、残りの3割は新しい論点を問うものになっていると言われています。よって、専門試験の過去問を繰り返し解くことは、合格に欠かせません。
また、出題される問題の多くは判例の考え方に基づいて解答するものになっているため、判例の考え方の理解が必要となります。
そして、全40題中必須問題が31題、残り9題が選択問題となっているため、必須問題の憲法、行政法、民法に重点的に力を入れなければならないことは言うまでもないでしょう。
残り9題については、過去に大学の授業で履修したものがあれば、その科目で点を取るための勉強を行いましょう。履修登録時に、該当する科目を積極的に登録してみるのもいいかもしれません。
第二次試験の対策

専門試験 記述式
専門試験は、選択式試験で覚えた論点や判例を基に論文を展開します。よって、選択式試験の勉強をしっかり行っているかどうかがポイントとなります。
さらに過去問を解いていくのですが、その際は模範答案や、合格者答案を参考に自分の答案を見比べて、書き落としている点がないかどうかチェックしましょう。この時、可能であれば誰かに自分の答案を添削してもらうことをお勧めします。
憲法、行政法、民法、国際法、公共政策の中から2題を選択する形となっており、多くの受験生は憲法、行政法、民法の中から選びます。
政策論文試験
採点者は法律の専門家ではないため、書き方のポイントを押さえて文字数制限を守れば一定の点数はとれると思われます。
人物試験
多くの受験生が中間の評価に集中します。二次試験までに自己分析や省庁分析を行ったり、面接を経験しておいたりするとよいでしょう。
まとめ

キャリア官僚は社会の在り方の最善を追求できる仕事です。「公共のために働きたい」、「国家の基盤を担いたい」といった志を少しでも持つ方は、まずは省庁の採用HPを見てみたり、説明会等に参加してみたりすることをおすすめします。
そして、採用されるためには登竜門である国家総合職試験に合格しなければなりません。
倍率が非常に高く、出身大学も難関大学の学生が多いハイレベルな試験ですが、あきらめずに効率的な学習を続ければ、十分合格基準に達することが可能であると言えます。
また、勉強を始めるのが遅れてしまったと感じているとしても、多くの場合すぐに取り組めば間に合います。この記事を読み終わった今すぐにでも行動を起こしましょう。
最後に、忘れてはならないのが民間就活同様、自己分析や業界研究を行う必要があるという事です。試験直前期に入る前に済ませておくことをおすすめします。


