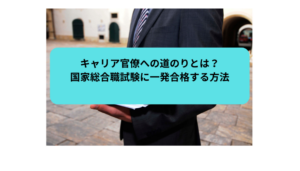学生必見!誰でも簡単にTOEIC 760以上取るための勉強法

TOEICという英語試験をご存じでしょうか。
英語の語学試験の中で最もポピュラーで、資格試験などの際に、しばしば用いられる英語の資格です。
また、就職・転職活動や昇進の場面でも重視されるため、ぜひとも高い点数を保持しておきたい資格となっています。
中でも、TOEIC L&Rは、日常生活やグローバルビジネスで活きる「英語で聞く・読む能力」を測定するテストとされ、毎年多くの学生や社会人が受験しています。
そこで今回は、そもそも何点取ればいいのか、具体的にどのような場面で役立つのか、760点以上取るために私が行った勉強法など、TOEIC L&Rについて詳しく解説していきます。
TOEICを受けるメリットは?他の英語試験との比較

TOEICを受けるメリットを明確にするために、他の英語試験との比較を行ってみたいと思います。
まずは、TOEICを除いたポピュラーな英語資格試験を以下に示します。
・実用英語技能検定(英検)
文部科学省後援の検定で、試験は年3回行われます。5級から準1級、1級まで習熟度に応じた7つのレベルがあり、幅広い層に人気で定評があります。
・TOEFL iBT
大学で講義を受けられるレベルで正しく英語を使える能力を図る英語テストで、最大120のスコアで評価します。
欧米の大学や大学院に出願するときに必要となる資格で、アカデミックな内容が多いです。
・IELTS
海外の大学・大学院進学や移住申請に使われることが多い英語テストです。1.0から9.0までのスコアで評価されます。
・ケンブリッジ英語検定
日本ではあまり有名ではありませんが、海外では非常に知られている英語テストです。よって世界での認知度と信用度はとても高いです。
・GTEC
ベネッセコーポレーションによる英語試験です。主に大学入試に活用されます。

日本で最もポピュラーである英検と比べてTOEICの差別化できる点として、合否ではなくスコアで判定されるため、自分が今どこの位置にいるかを把握できることが挙げられます。
また、同じ試験を何度もトライする形になるため、試験形式に慣れ、前よりも英語力が上がった状態で挑むことで、徐々に点数が上がっていく達成感を得られます。
さらに、毎月試験が実施されており、いつでも受けることが可能です。
他の英語試験と異なり、ビジネスシーンに特化した実践的なコミュニケーションが出題されるのも魅力的な点です。
そして、大学入試や採用・転職、昇進時など継続的に使えるため、是非ともとっておきたい資格と言えるでしょう。
TOEICは何点とればいい?高得点の基準は?

実用英語技能検定、いわゆる英検を受けてきた方は戸惑うところかもしれませんが、TOEICには合格基準というものがありません。
TOEICは990点満点で、リスニング495点・リーディング495点で構成されています。
目安としては、英検2級がTOEICの550点となります。
国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)によれば、2023年度のTOEIC Listening & Reading Testの受験者数は、74万6178人で、平均点は612点でした。
そこで、スコアが必要なシーンに合わせて目標点を以下に示してみましょう。
企業が求めるTOEICスコアの平均(IIBC調べ)
・採用・・・新卒545、中途620
・昇進・昇格・・・係長・主任515、課長530、部長565、役員600
・海外出張者・赴任者選抜・・・海外出張者620、海外赴任者635
一般的に、履歴書に書けるのは、600点以上が目安と言われています。
よって、高校生なら、600点を取れれば十分優秀です。
大学生~社会人であれば、高得点はビジネス英語レベルとされる700点以上と言われています。
また、TOEICを作成したETS英語でのコミュニケーション能力とTOEICのスコアの相関関係を調査した結果に基づいて作成したA~Eの5段階評価によれば、730点以上がBランクとされ、「どんな状況でも適切なコミュニケーションができる素地を備えている」とされます。
このような5段階評価を基に要件を設定する企業や学校も多いと考えられます。ただし、応募先の企業や職種によって求められる要件は異なるので注意しましょう。
これらのことから、高得点を目指す方は730点以上を目標にすると良いでしょう。
また、グローバル化が進む中、日本企業の採用・昇進の場面で今後要求される点数がさらに上がっていくことが予想されます。
TOEICの出題形式と配点を知ろう

TOEICに限らず、資格試験において出題形式や配点を知っておくのはとても重要です。
ここで、TOEICの中身を具体的に知っておきましょう。
ちなみに、初めて受ける人は驚くかもしれませんが、TOEICは問題用紙への書き込みが一切できません。
これは、実践的な英語力を測定する試験であるため、実際のビジネスシーンで英語を聞き取る時にメモを取っている暇がないことが要因であると言われています。
英語のリスニングやリーディング時にメモを取って問題を解いてきた方にとっては、これが意外な落とし穴になる可能性があります。
そこで、実際の試験に合わせた模試の演習を普段から行っておく必要があります。
TOEICは、リスニングセクション100問、リーディングセクション100問の合計200問で構成されています。
先ほど、TOEICは990点が目安と申し上げましたが、それでは1問5点だとしても計算が合いません。どういうことでしょうか?
実は、スコアは正答数そのままの素点(Raw Score)ではなく、スコアの同一化(Equating)と呼ばれる統計処理によって算出された換算点(Scaled Score)とされています。
つまり、複雑な処理を経て得点が出されるため、1問何点という決まりがないという事です。

一般的に、600点をとるためにはリスニングセクションで66~70問、リーディングセクションで56~60問正解すればよいと言われています。
そして、730点を取るためには、例えばリスニングで78問、リーディングで66問正解する必要があります。
これは、同じ正解数でもリスニングの方が、スコアが高く出るからです。
よって、高得点を目指す方はリスニングを重点的に勉強するべきだと言えます。
さて、それではセクションごとの問題内容を具体的に見ていきましょう。
①リスニングパートの形式と攻略法

TOEICはPart1~Part4までがリスニング、Part5~Part7がリーディングで、全てマークシート式になっています。
詳しく問題傾向と対策を見ていきましょう。
・Part1 写真描写問題
写真が与えられ、4つの英文の中から状況に合う文を選ぶ形式となっています。
全6問です。音声は一回だけ読まれます。
比較的簡単で、落とせない問題となっています。
・Part2 応答問題
最初に発言または質問の音声が流れ、続けてそれに対する3つの応答の音声が流れます。
全25問です。音声は一回だけ読まれ、問題用紙には何も印刷されていません。
徐々に難易度が上がっていくため、最初の方は簡単なので、落としたくない問題です。
ポイントは2つです。
①疑問詞を落とさないようにする。
②単語を聞き落とさない。
初心者はこれを意識することで一気に英語が聞き取れるようになります。
全ての文を完璧に聞き取る必要はないので、文の最初の疑問詞と単語を聞き落とさないようにしましょう。
また、問題集を繰り返し解くことで会話のパターンを覚えることも有効な勉強法です。毎回出題される会話文の形式は大体決まっているからです。
・Part3 会話問題
2人もしくは3人による会話の音声を聴き、その後に流れる質問の答えを4つの選択肢から選ぶ問題です。
音声は1回だけ流れます。4つの選択肢は音声では流れません。問題用紙には、質問と4つの選択肢が印刷されています。
1つの会話につき、3つの問題が出ます。全部で13の会話が出題されるので、Part 3は全部で39問あります。
Part3の攻略法は、Part2同様会話のパターンを覚えることが有効です。
そして、Part3は質問が印刷されていることが特徴です。
一度しか音声が流れないので、会話文を聞いてから質問を見たのでは、多くの場合間に合いません。
そこで、会話文が流れる前に質問をチェックしておくのがおすすめです。
そうすることで、何が聞かれるのかを身構えた状態で会話文を聞くことができます。
ただし、数秒しか時間がないので、試験までに瞬時に英文を読む力をつけておく必要があります。
また、問題集を繰り返し解くことでよく聞かれる質問を覚えておくことも一つの手です。
例)What does the speaker say he will next to do 話し手は、次に何をすると言っていますか。
・Part4 説明文問題
1人によるアナウンスやナレーションなどの音声を聴き、その後に流れる質問の答えを4つの選択肢から選び、マークシートに記入する形式の問題です。
音声は一回だけ流れます。1つの説明文に3つの問題が出て、全部で30問あります。
攻略法としては、Part3とほぼ同じです。
最後の数問は、図表を使った問題が出るので、解く練習をしておく必要があります。
②リーディングパートの形式と攻略法

・Part5 短文穴埋め問題
Part 5の短文穴埋め問題は、1センテンス(1文)の抜けているところに入る単語や語句を、4つの選択肢から選びマークシートに記入します。
全30題出題されます。単語や文法を覚えていれば解ける、英検と似たような形式となっています。
ポイントは、落とさないように素早く解くことです。
リーディングパートはじっくり解いていると大抵の場合、後半に行くにつれ時間が足りなくなります。
後半の方の長文は分量が多く複雑なため、初めの方の比較的難易度の低い問題に時間をかけたくありません。
文法については、ほとんど高校レベルの文法で解けるものとなっています。
・Part6 長文穴埋め問題
Part 6の長文穴埋め問題は、メールや案内などの長めの文章の抜けているところに入る単語や語句、一文を、4つの選択肢から選びマークシートに記入する形式の問題です。
一つの文章に4つの問題が出ます。全部で4つの文章について解くので、全16問解くことになります。
ここもPart5同様、時間をかけずに解きたいところです。問題のタイプは、文法問題と文脈に合う文を選ぶ問題に分かれます。
・Part7 読解問題
Part 7の読解問題では、新聞などの記事やeメールなどの文章の内容について、4つの選択肢から一つを選ぶ形式です。
文章が1つの問題と2つセットの問題、3つセットの問題と、大きく3つに分かれます。
文章が1つの問題は比較的文が短いので、全文を読んだ上で問題を解くことがベストです。
しかし、文章が2~3つの問題は、とにかく量が多いので、全てを読むことが難しいです。
そこで、選択肢をざっと見てから答えがある箇所を探す方法で解くことが求められます。

ここで意外と大事なのが、eメールの文章を読む際、メールの宛名や差出人、件名を確認することです。
先ほど会話のパターンを覚えるのが大事と申し上げましたが、ここを見ればどのパターンに当てはまるのが大体わかります。
例えば、よくあるのは、お店側が何らかのミスをしてしまい、お客に対して謝罪文と代替措置の提示をする話です。
この場合、To: All customers、From:○○ (会社名)のようになっています。
このような会社toお客の他に、会社to従業員、会社to求職者など様々なパターンがあります。
文章の大体の内容がわかれば、答えを探すスピードが大きく向上します。
高得点を取るためには?効果的な勉強法

ここまでそれぞれのパートごとの攻略法をお話してきましたが、どのパートにせよ語彙力やリスニング力、長文読解力など、ベースの英語力は必要になってきます。
そこで、ここでは必要な力と、勉強法を紹介していきます。
①語彙力と文法力
単語については、単語帳を使って勉強するのが最適です。おすすめは、TEX加藤さんの『TOEIC 出る単特急 金のフレーズ』です。
TOEICは毎回同じような単語が繰り返し出るため、よく出る単語を重点的に覚えておく必要があります。
この本を読んでおけば、TOEICを受験するために必要な単語をカバーすることができます。
文法については、大学受験や高校で使っていた文法書で十分であると考えます。
②リスニングの力
公式が出している、『公式TOEIC Listening&Reading 問題集』シリーズなどを使って、本番と同じ形式でリスニングを行いましょう。
音声を聴きながら聞こえる文を書いていく「ディクテーション」という勉強法もおすすめです。
そして、おすすめの勉強法が、『abceed』というスマホアプリを使って通学・通勤時など移動時に『TOEIC 出る単特急 金のフレーズ』の単語を繰り返し聴くことです。
なんと、音声再生だけなら無料で聴くことができます。日本語と英語が交互に再生されるので、覚えるまで何度でも聴きましょう。

③長文読解力
公式の問題集を使って、本番と同じ形式で長文読解を行いましょう。
また、セクションごとによくある文章のパターンを覚えて、対策を行いましょう!
まとめ
TOEICは、就職や転職、大学入試で有用な英語資格です。
高得点を目指す方は、730点以上を目標に勉強・受験を行いましょう。
そして、高得点を取るためには問題の形式と傾向、対策を知ることが不可欠です。
対策法がわかったら、本番に向けて効果的な勉強を行いましょう。