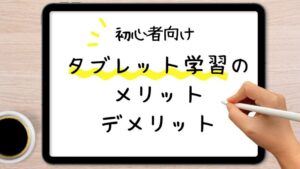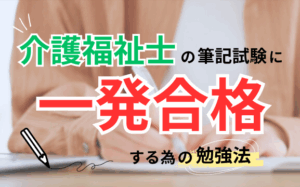第一種電気工事士に一発合格するための勉強法~効率良く学ぶ戦略~

第一種電気工事士の資格は、電気設備の設計・施工・管理を行うために必要な国家資格です。
しかし、第一種電気工事士の筆記試験は範囲が広く計算問題も多いため、何から手をつければいいのか分からないと悩む方も多くいます。
本記事では、一発合格を目指すための効率的な勉強法や計画の立て方、合格者の体験談を解説します。記事を読めば、第一種電気工事士の資格試験に一発合格できる可能性を高められます。
第一種電気工事士の資格に一発で合格するためには、勉強の計画を立て、継続的に学ぶことが重要です。
第一種電気工事士筆記試験とは

第一種電気工事士について、知っておきたい基礎知識は以下の通りです。
- 試験概要と受験資格
- 出題範囲と出題形式
- 合格ラインと合格率
- 実技試験との関係性
第一種電気工事士は、一般住宅からビル・工場といった高圧受電設備の電気工事を行うために必要な国家資格です。
高圧・特別高圧の電気設備工事を行うにはこの資格が必須となるため、電気工事の現場では重宝されます。
試験概要と受験資格
第一種電気工事士試験は、筆記試験と実技試験の2つがあります。
受験手続きは例年6月頃から開始され、筆記試験は10月上旬、実技試験は12月中旬に実施されます。受験資格については特に無いため、筆記試験・実技試験ともに年齢・学歴・実務経験を問わずだれでも受験可能です。
電気工事の実務経験がなくても受験できるため、転職希望者や未経験者でも資格取得を目指せます。資格を持っていても実務を行うときには、実務経験が求められるため、注意が必要です。
出題範囲と出題形式
筆記試験の出題範囲は幅広く、以下の9科目があります。
- 電気に関する基礎理論
- 配電理論及び配線設計
- 電気応用
- 電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
- 電気工事の施工方法
- 自家用電気工作物の検査方法
- 配線図
- 発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
- 一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令
問題形式は、四肢択一のマークシート方式で50問出題され、試験時間は140分です。
合格ラインと合格率

第一種電気工事士の筆記試験は、50問中30問以上の正答で合格できます。
年度による難易度の違いによって、合格点の調整はあるものの、基本的には60%の正答目標に学習を進めましょう。
合格率は例年50〜60%前後となっているため、比較的合格者の多い試験です。過去問対策と問題演習の学習を積み重ねていけば、合格は十分に可能です。
実技試験との関係性
筆記試験に合格した人は、実技試験を受験する流れになります。
実技試験では、実際に行った配線作業の正確性と安全性が評価されます。筆記試験に合格しないと実技試験を受ける資格が得られないため、まずは筆記試験の合格が最優先です。
実技試験の課題は事前に公表されるため、試験前に練習することが可能です。公表から実技試験までの間に、公表課題を繰り返し練習すれば、スムーズに合格できます。
筆記試験で学んだ図記号や配線設計の知識は、実技試験の施工図読解にも役立ちます。
合格を目指す勉強計画の立て方

第一種電気工事士筆記試験は出題範囲が広く、計算問題・法規・機器の特徴などバランスよく得点しなければなりません。
第一種電気工事士の合格を目指すためには、以下の3つのポイントが重要です。
- 勉強スタート前の心構え
- 試験日から逆算したスケジュール作成
- 苦手分野の洗い出しと優先順位付け
闇雲に勉強を始めるのではなく、しっかりと計画を立てて効率良く学習を進めることが、合格への近道です。
勉強スタート前の心構え
資格試験の勉強は長期間の継続が必要になるため、なぜ自分はこの資格を取るのかを明確にすることが重要です。
目的意識が曖昧なままだと、途中で挫折しやすくなります。具体的な目標を掲げることで、日々の学習のモチベーションが維持することが可能です。
第一種電気工事士の筆記試験は6割の得点で合格できるため、すべての問題を解く必要はありません。得意分野を確実に得点し苦手分野は基本問題だけに絞る、堅実な戦略を意識しましょう。
試験日から逆算したスケジュール作成

効率的な学習を進めるには、試験日から逆算して計画を立てるのが基本です。
第一種電気工事士の筆記試験は、例年10月上旬に実施されるため、6月〜7月頃に受験申込をしたらすぐに学習を始めましょう。
スケジュール作成では、出題範囲を把握して1週間〜2週間単位で学習する範囲を分けるのがポイントです。
7月〜8月ごろには基礎学習を終え、9月〜10月直前は過去問と模試を中心に実戦力を高め、苦手分野を復習するのがおすすめです。
試験日から逆算すれば、いつまでに学習を終わらせればよいかの目標が明確になり、計画的に学習を進められます。
苦手分野の洗い出しと優先順位付け
効率良く得点力を上げるためには、自分の苦手分野を明確にすることが必須です。
苦手分野を把握せずに勉強を進めると、得意な範囲ばかりに時間を使ってしまい苦手な分野を残したまま試験を迎えるリスクがあります。
テキストと問題集を一通り解き、どの科目・分野で得点が取れないかを記録しましょう。出題頻度が高い科目の苦手な分野を、優先的に学習するのが効率的です。
より得点につながりやすいところを選んで学習するのが、限られた時間で合格するコツです。
科目別の効率的な勉強法

第一種電気工事士筆記試験の筆記試験では、9科目が出題されます。
- 電気に関する基礎理論
- 配電理論及び配線設計
- 電気応用
- 電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
- 電気工事の施工方法
- 自家用電気工作物の検査方法
- 配線図
- 発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
- 一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令
それぞれ出題傾向や学習方法に特徴があるため、科目ごとに勉強法を工夫すれば、効率的に得点力を伸ばせます。
電気に関する基礎理論
電気に関する基礎理論は、計算問題が中心の科目です。
オームの法則や電力・電力量計算などの公式を暗記し、問題を繰り返し解くことで計算方法を定着させましょう。
基本公式の導き方と単位変換の流れも理解しておけば、応用問題でも対応できます。
過去問の反復演習で出題パターンを覚え、ミスしやすいポイントをノートにまとめると効果的です。
配電理論及び配線設計
配電理論及び配線設計では、配線設計の計算や、図記号・配線図の読解が中心となります。
JIS記号や電線の許容電流値を暗記して、配線図の基本的な読み方を習得しましょう。
配線図が読めるようになったら、実際の配線図問題を解いて慣れるのがおすすめです。
配線ルートやブレーカー選定の根拠を、自分の言葉で説明できるように理解を深めましょう。
電気応用
電気応用の科目では以下の機器の基礎知識と応用が問われます。
- モーター
- 照明
- 電熱器
それぞれの特徴や用途、接続方法を整理し、イラストとセットで覚えるのが有効です。
図解入りの参考書や過去問の解説を活用し、出題頻度の高い機器の動作原理・特性を重点的に学習しましょう。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備

電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備の科目は、覚える量が多くなります。
機器・工具の写真やイラストと名称・用途を、セットで暗記するのが基本です。
それぞれの機器や工具の特徴を自分の言葉で説明できるようまとめ、ノートを作成しましょう。
電気工事の施工方法
電気工事の施工方法は、工事方法や施工の手順、注意点を理解する科目です。
配線工事の基本工程を図解で確認し、各工程でのポイントを覚えましょう。
施工方法による違いや、法令上の制約も習得しておく必要があります。
配線の方法や接地工事、防爆工事などは、まとめて暗記カードにすると復習しやすくておすすめです。
自家用電気工作物の検査方法
自家用電気工作物の検査方法では、電気設備の点検・試験方法と判定基準が出題されます。
検査方法ごとに、以下の3つのポイントをまとめておきましょう。
- 目的
- 試験値
- 異常時の対応
実務経験がない人でもイメージしやすい図解付き参考書を活用するのが効果的です。
試験手順と判定基準は特に頻出なので必ず暗記しておきましょう。
配線図
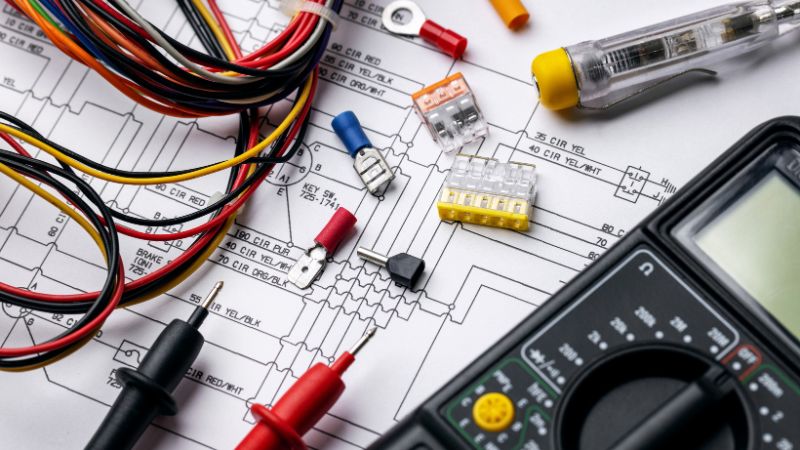
配線図の科目では記号の意味や配線ルート、機器接続方法を正確に把握することがポイントです。
JIS記号を完全暗記し、過去問の配線図を数多く解いて慣れておきましょう。
機器配置から回路図、配線図の流れを理解し、問題ごとにミスしやすいところを記録して復習するのが効果的です。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
発電施設、送電施設及び変電施設の科目では、設備構成や機器の役割を図解で整理するのが効率的です。
設備の種類と特徴、変圧器や遮断器の動作特性はよく出題されるので、覚えておくと得点源になります。
設備ごとの用途・特性の違いを暗記カードにまとめ、比較表で整理すると記憶に残りやすいです。
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令
法規範囲の学習では、条文の暗記が中心となります。
出題傾向の高い条文・数値・用語を絞って覚えるのが効率的です。
過去問で繰り返し出る部分にマーカーを引き、数値問題は一覧表にすると覚えやすくなります。
暗記カードアプリなども活用し、移動時間やスキマ時間に反復するのがおすすめです。
過去問と問題集を活かすテクニック

第一種電気工事士筆記試験の合格には、過去問の活用が最も効果的な勉強法です。
過去問を効果的に活かすテクニックとして、以下の3つのポイントを理解しておきましょう。
- 過去問を活用する3つのコツ
- 解くべき年数と回数の目安
- 模試や予想問題の使いどころ
試験は毎年似た形式・出題パターンで構成されているため、過去問から試験の傾向や出題パターンをつかむことで、確実に合格率を高められます。
過去問を活用する3つのステップ
過去問は単に解くだけではなく以下の3つのステップを実践することで、学習効果を高められます。
- 制限時間を設けて通しで解く
- 間違えた問題をチェック
- 間違えた問題のみを何度も繰り返す
本試験と同じ時間配分で解くことで、今の実力と苦手分野が確認できます。必ず時間を計り、問題を飛ばさず全問解くことが重要です。
間違えた問題は解説をしっかり読み、なぜ間違えたのかを分析しましょう。間違えた問題をノートやアプリにまとめ、反復学習します。
3回解いて3回正解できるまで反復すると、確実に得点力が上がります。
解くべき年数と回数の目安
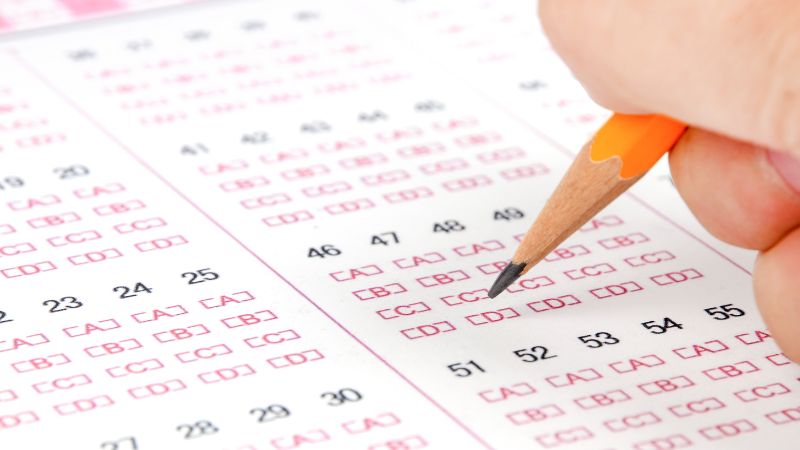
第一種電気工事士の筆記試験では、過去問5年分を3周以上解くのが目安です。
過去5年分の問題を網羅すると、出題パターンやよく出る問題を把握できます。電気理論や法規に関する問題は、数字や言い回しが少し変わるだけで、基本的な問題構成は同じです。
過去問演習を重ねれば、本試験でも同じような問題が必ず答えられます。年度によって難易度の差があるため、複数年度の問題を解くことで試験本番の波に左右されにくくなります。
間違えた問題はピックアップして、重点的に復習しましょう。
模試や予想問題の使いどころ
過去問を一通り解き終わったら、模擬試験形式の問題集や予想問題に取り組みましょう。
模試は本番を想定した問題構成と制限時間で行うため、実際の試験時間の使い方や問題の取捨選択の練習になります。
模擬試験は最新の出題傾向に合わせて作られた問題なので、過去問ではカバーできない新傾向問題にも対応できます。
模試や予想問題で苦手分野を再確認し、残りの期間でピンポイントに復習するのも大切です。
過去問と予想問題を組み合わせれば、合格ラインの6割得点を安定して超えられる力が身につきます。
忙しい人向け・短期間で効果を出す勉強のコツ

第一種電気工事士筆記試験の合格を目指す方の中には、仕事や家庭の都合でまとまった勉強時間が取れない方も多くいます。
忙しい方でも合格を目指せる、効率良く成果が出る勉強のコツは以下の3つです。
- スキマ時間の活用法
- 時間帯別・効率的な学習法
- モチベーション維持のコツ
スキマ時間の活用法
忙しい社会人はまとまった勉強時間を確保するのが難しいので、スキマ時間学習が効果的です。
日常のちょっとした以下の空き時間を有効活用することで、総学習時間を大幅に増やせます。
- 通勤の電車内
- 昼休み
- 待ち時間
- 寝る前の10分間
スマホアプリの問題集やYouTubeの解説動画を活用すれば、スキマ時間でも効率良く学習できます。
1回5〜10分の小さな積み重ねが試験直前に大きな差を生むので、意識的に活用しましょう。
時間帯別・効率的な学習法

学習の効率は、時間帯によっても変わります。
集中力の高い時間帯に重要な勉強を割り当てるのが、効率アップのコツです。
朝型の人なら起床後の30分間が最も頭がクリアで吸収力も高いので、計算問題や暗記を行うのがおすすめです。
夜型の人なら、仕事後の就寝前の時間を活用しましょう。
集中力が低い時間帯は、動画で学ぶ図記号の確認や問題集の軽い復習など、負担の少ない内容にすると習慣化しやすくなります。
休みの日などまとまった時間が取れる日は、模試形式の問題演習や苦手分野の学習を行うと効果的です。
時間帯ごとに学習内容を振り分ければ、無理なく継続できて短期間でも効果的に知識を定着させられます。
モチベーション維持のコツ
試験勉強は数ヶ月に及ぶため、途中でモチベーションが下がるのはだれにでもあります。
モチベーションが下がったときは、目に見える目標を設定するのが効果的です。
今週は計算問題を30問解くなどの具体的な数値目標を立て、達成したらカレンダーや手帳に○をつけることで達成感が得られます。
SNSや資格取得を目指すコミュニティに参加するのも効果的です。
同じ目標を持つ仲間がいると励みになり、モチベーションが高まります。
勉強した後に小さなご褒美を用意するのも良い方法です。
自分の気持ちがリフレッシュできる時間を設けることで、勉強とリラックスのバランスが取りやすくなります。
一発合格した人の体験談と成功パターン

実際に第一種電気工事士の試験を一発合格した人たちの学習法や試験当日の過ごし方は、これから受験する人のヒントになります。
一発合格するのに役立つポイントは、以下の3つです。
- 学習時間とスケジュール
- 苦手科目の克服方法
- 試験当日の過ごし方と注意点
学習時間とスケジュール
第一種電気工事士筆記試験の一発合格者は、計画的かつ継続的に勉強時間を確保している共通点があります。
実際に合格した人は、平均して3〜4ヶ月前から学習を始め、1日1〜2時間の勉強を継続しています。
具体的なスケジュールは以下の通りです。
- 1ヶ月目:基礎学習と過去問演習を中心に学ぶ
- 2〜3ヶ月目:問題集と過去問を繰り返し解く
- 試験直前の1ヶ月:苦手分野を集中して復習、模試形式で通し練習を行う
平日は1時間でも良いので継続することを意識し、週末は2〜3時間ほどまとまった時間を確保した方が多く見られます。
苦手科目の克服方法

合格者の多くが苦手としていたのが、電気理論の計算問題と法規です。
計算問題は公式を暗記するだけでなく、繰り返し解いてパターンを身につける方法が効果的だという声が多くあります。
過去問5〜10年分を3周以上解けば、出題傾向を把握できて計算問題に慣れることが可能です。
法規は範囲が広く、暗記が中心になるため、図表やまとめノートを作成し、要点を整理する学習法を採用した人が多くいます。
苦手科目を放置せず、毎日の勉強に少しずつ組み込んでいくことが、一発合格者たちの成功パターンです。
試験当日の過ごし方と注意点
試験当日は緊張して思わぬミスをしやすいため、一発合格した人たちは事前にしっかり準備を整えて本番を迎えています。
前日の夜は徹夜を避け、軽く復習したら早めに就寝し、当日の朝は普段と同じ時間に起きて朝食をきちんと取りましょう。
試験会場では、開始前に法規や重要な公式を確認するなど、直前まで記憶を呼び起こす工夫も有効です。試験中は難しい問題で立ち止まらず、後回しにして解ける問題から着実に得点するように意識しましょう。
時間配分を守り、計算ミスを防ぐために見直しの時間も確保するのが、一発合格した人に共通する戦略です。
一発合格するには「計画」と「継続」が重要

第一種電気工事士筆記試験に一発合格するためには、計画的な学習スケジュールと日々の継続が何より重要です。
まずは試験の概要と出題傾向を理解し、自分の苦手分野を早めに洗い出しましょう。
過去問を中心に、効率良く得点源を増やしていけば、初めての受験でも合格することは十分可能です。
忙しい方でも、スキマ時間の活用や1日1時間の積み重ねで合格は目指せます。
合格者の体験談を参考に、自分に合ったペースと方法で学習を続けましょう。