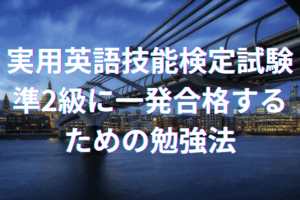なぜか不調…その原因は?見直すべき5つの現代食と健康の新常識

はじめに:その「なんとなく不調」、食事が原因かもしれません
「しっかり寝ているはずなのに、日中いつも眠い」「肌の調子がずっと良くない」「理由もなくイライラしたり、気分が落ち込んだりする」。多くの現代人が抱える、こうした原因不明の「なんとなく不調」。
あなたは、これを年齢や仕事のストレスのせいだと諦めてしまっていないでしょうか。しかし、その不調の根源は、あなたが毎日無意識に口にしている「食事」にあるのかもしれません。
私たちの食生活は、この数十年で劇的に変化しました。安価で手軽、そして美味しい加工食品が溢れる一方で、古くからの伝統的な食事が食卓から姿を消しつつあります。
この便利な食生活が、気づかぬうちに私たちの心と体のバランスを蝕んでいるとしたら…。
この記事では、現代の食生活に深く根差し、様々な健康リスクが指摘されている5つの食品 -「砂糖」「小麦粉」「植物油」「乳製品」「加工肉」-に焦点を当てます。
目的は、これらの食品を「絶対悪」として断罪し、ストイックな食事制限を推奨することではありません。それでは長続きせず、かえってストレスになってしまいます。
大切なのは、それぞれの食品が私たちの体にどのような影響を与えるのかを正しく理解し、情報に振り回されることなく、自分自身の体と相談しながら「賢く選択する力」を身につけることです。
この記事を読み終える頃には、スーパーの食品棚が今までとは違って見えるはずです。さあ、あなたの不調の謎を解き明かし、真の健康を取り戻すための食の新常識を学ぶ旅に出かけましょう。
第1章:見えない甘味料の罠「砂糖」

甘いものは心を癒し、幸福感を与えてくれます。
しかし、現代社会における「砂糖」は、その甘い魅力の裏に、心身を蝕む深刻な罠を隠しています。特に問題となるのが、お菓子やデザートだけでなく、あらゆる加工食品に潜む「見えない砂糖」です。
なぜ砂糖は問題視されるのか?
砂糖、特に精製された白砂糖や清涼飲料水に多用される異性化糖(果糖ぶどう糖液糖など)の過剰摂取は、体に様々な悪影響を及ぼすことが知られています。
第一に、「血糖値の乱高下(血糖値スパイク)」です。砂糖を大量に摂取すると血糖値が急上昇し、それを下げるためにインスリンというホルモンが大量に分泌されます。その結果、今度は血糖値が急降下し、低血糖状態に陥ります。
この乱高下は、強い眠気、集中力の低下、疲労感、イライラといった精神的な不安定さを引き起こす原因となります。食後、猛烈に眠くなる経験がある方は、血糖値スパイクを疑ってみる価値があるでしょう。
第二に、「体の糖化」による老化の促進です。体内で過剰になった糖は、タンパク質と結びついて「AGEs(終末糖化産物)」という老化物質を生成します。
このAGEsが皮膚のコラーゲンに蓄積すればシワやたるみの原因に、血管に蓄積すれば動脈硬化のリスクを高めるなど、全身の老化を加速させてしまうのです。
さらに、砂糖は腸内の悪玉菌の格好のエサとなり、腸内環境を悪化させます。腸は「第二の脳」とも呼ばれ、免疫機能や精神安定にも深く関わっているため、腸内環境の乱れはアレルギーや気分の落ち込みにも繋がる可能性があります。
どこに砂糖は隠れている?

私たちが注意すべきなのは、ケーキやチョコレートといった分かりやすい甘いものだけではありません。
むしろ、一見すると健康的、あるいは甘くないと感じる食品にこそ、多くの砂糖が隠れています。
・清涼飲料水、スポーツドリンク、野菜ジュース:角砂糖10個分以上の砂糖が含まれることも珍しくありません。
・菓子パン、総菜パン:パン生地そのものにも、中のクリームやフィリングにも大量の砂糖が使われています。
・調味料:ケチャップ、焼肉のタレ、ドレッシング、めんつゆなどにも、味を調えるために相当量の砂糖や異性化糖が添加されています。
・加工食品:レトルト食品、冷凍食品、練り物など、多くの加工品に保存性や味の均一性を高める目的で砂糖が使用されています。
砂糖との賢い付き合い方
砂糖を完全に断つのは困難ですが、摂取量をコントロールすることは可能です。
まずは、最も手軽で効果が大きい「飲み物」から砂糖を断つことから始めてみましょう。ジュースやお茶のペットボトル飲料を、水やお茶、無糖の炭酸水に変えるだけでも、1日の砂糖摂取量は劇的に減少します。
次に、買い物の際に「原材料表示」を見る習慣をつけましょう。「砂糖」「ぶどう糖果糖液糖」「果糖」といった表示が原材料の上位に記載されているほど、その製品に多く含まれていることを意味します。
甘みが欲しい時は、精製された白砂糖の代わりに、ミネラルを含むてんさい糖や黒糖、血糖値の上昇が緩やかなメープルシロップ、羅漢果(ラカント)、オリゴ糖などを少量使うのがおすすめです。
また、果物やさつまいも、かぼちゃといった素材そのものが持つ自然な甘みを活かす料理を心がけることも、味覚をリセットし、過剰な甘みへの依存から脱却する助けとなります。
第2章:食感の裏側にある「小麦粉」

パン、パスタ、ピザ、ラーメン、うどん、ケーキ、クッキー…。
私たちの食生活は、小麦粉なしでは成り立たないと言っても過言ではないほど、小麦製品で溢れています。
そのふっくら、もちもちとした独特の食感は多くの人を魅了しますが、その裏側で体への負担となっている可能性が指摘されています。
なぜ小麦粉は問題視されるのか?
小麦粉が健康問題として議論される際の中心にあるのが「グルテン」です。グルテンは、小麦に含まれるタンパク質の一種で、水を加えてこねることで粘りと弾力性を生み出し、パンや麺類のあの独特の食感を作り出します。
一部の人には、このグルテンが腸に炎症を引き起こし、様々な不調の原因となることがあります。
代表的なものが、自己免疫疾患である「セリアック病」や、そこまで重篤ではないもののグルテン摂取によって不調が起こる「非セリアック・グルテン過敏症」です。
症状は、腹痛、下痢、便秘といった消化器系の問題から、頭痛、倦怠感、肌荒れ、「ブレインフォグ」と呼ばれる頭にモヤがかかったような感覚まで多岐にわたります。
また、グルテンは腸の粘膜の結合を緩め、本来体内に吸収されるべきでない未消化物や毒素が血中に漏れ出す「リーキーガット症候群(腸管壁浸漏症候群)」の一因になるとも考えられています。
これが全身の慢性的な炎症やアレルギー、自己免疫疾患の引き金になる可能性も指摘されているのです。
さらに、精製された白い小麦粉は、砂糖と同様に糖質が多く、食後の血糖値を急激に上昇させます。朝食に菓子パンや白い食パンを食べると、昼前には強い空腹感や眠気に襲われるのはこのためです。
小麦粉との賢い付き合い方

もしあなたが原因不明の不調に悩んでいるなら、一度「グルテンフリー」を試してみる価値はあるかもしれません。
2週間程度、小麦製品を完全に抜いてみて、体調にどのような変化があるかを観察するのです。もし不調が改善されるようであれば、あなたの体はグルテンを苦手としている可能性があります。
とはいえ、ストイックなグルテンフリー生活は大変です。まずは、小麦製品を食べる「頻度」を減らすことから始めてみましょう。
・主食を米にする:3食パンや麺類という日があるなら、そのうち1食、2食をご飯(できれば玄米や雑穀米)に変える。日本には米という素晴らしい主食があります。
・パンの選び方を変える:精製された白い小麦粉のパンではなく、食物繊維やミネラルが豊富な「全粒粉」や「ライ麦」のパンを選ぶ。
・代替粉を活用する:最近では、米粉を使ったパンや麺類、お菓子も増えています。米粉はグルテンを含まず、もちもちとした食感が楽しめます。料理によっては、そば粉や大豆粉なども活用できます。
・「ハレの日」の楽しみにする:大好きなパスタやケーキを我慢し続けるのはストレスです。普段は小麦を控えめにし、友人との外食や特別な日には心から楽しんで食べる、といったメリハリをつけるのが長続きのコツです。
第3章:誤解されがちな「植物油」

健康のために「油は控えめに」という考え方は、もはや時代遅れです。
油(脂質)は、細胞膜やホルモンの材料となる、生命維持に不可欠な栄養素です。問題なのは「油の量」ではなく、その「種類」と「質」です。
特に、現代人が無意識のうちに過剰摂取している特定の「植物油」が、体内の炎症を引き起こす元凶となっている可能性があります。
なぜ特定の植物油は問題視されるのか?
油の主成分である脂肪酸には、様々な種類があります。中でも重要なのが、体内で作ることができず食事から摂る必要のある必須脂肪酸「オメガ6」と「オメガ3」です。
・オメガ6脂肪酸:サラダ油、コーン油、大豆油、ごま油などに多く含まれる。適量であれば必要だが、過剰摂取すると体内で炎症を促進する物質に変わる。
・オメガ3脂肪酸:亜麻仁油、えごま油、青魚(サバ、イワシなど)の油に多く含まれる。体内の炎症を抑制する働きがある。
理想的な摂取バランスは「オメガ6:オメガ3 = 2:1〜4:1」程度とされていますが、現代の食生活では、外食や加工食品、家庭での炒め物などでオメガ6系の油を多用するため、その比率は「20:1」や「50:1」にまでなっているとも言われます。
この極端なアンバランスが、アレルギー、動脈硬化、生活習慣病、精神疾患といった、あらゆる慢性的な炎症性疾患の温床となっているのです。
さらに、マーガリンやショートニング、それらを使用したお菓子やパンに含まれる「トランス脂肪酸」は、「食べるプラスチック」とも呼ばれる非常に危険な油です。
悪玉コレステロールを増やし、心臓病のリスクを高めることが科学的に証明されており、多くの国で使用が規制されています。
油との賢い付き合い方

健康のための油選びの基本は、「減らすべき油」と「増やすべき油」を明確に区別することです。
<減らす・避けるべき油>
・オメガ6系の油:サラダ油、コーン油、大豆油などの使用頻度を減らす。
・トランス脂肪酸:「マーガリン」「ショートニング」「ファットスプレッド」「植物油脂」と表示された菓子パン、クッキー、スナック菓子、安価な揚げ物は極力避ける。
<積極的に摂りたい油>
・オメガ3系の油:熱に弱い亜麻仁油やえごま油は、ドレッシングや納豆にかけるなどして生のまま摂取する。また、週に2〜3回はサバやイワシ、サンマといった青魚を食べる。
<調理に使うならこの油>
・炒め物や揚げ物など加熱調理には、酸化しにくいオリーブオイル(特にエキストラバージン)、米油、ごま油(香りのない太白ごま油など)、菜種油(圧搾一番搾りのもの)が適しています。
調理法自体を見直すことも有効です。揚げ物や炒め物を減らし、「蒸す」「茹でる」「煮る」といった油を使わない調理法を増やすことで、自然とオメガ6の摂取量を減らすことができます。
ドレッシングやマヨネーズも、良質なオリーブオイルなどを使って手作りすれば、添加物の心配もなく、安心して食べられます。
第4章:「体に良い」は本当?「乳製品」

「牛乳は骨を強くする」「ヨーグルトは腸に良い」。牛乳や乳製品には、長年「健康的」というイメージが定着しています。
カルシウムやタンパク質が豊富な優れた食品であることは事実ですが、一方で、日本人の体質に合わず、不調の原因となっているケースも少なくありません。
なぜ乳製品は問題視されるのか?
第一に、「乳糖不耐症」の問題です。乳糖とは牛乳に含まれる糖分で、これを分解する酵素が「ラクターゼ」です。多くの日本人は、成人するとこのラクターゼの分泌量が減少し、乳糖をうまく分解できなくなります。
牛乳を飲むとお腹がゴロゴロ鳴ったり、下痢をしたりするのはこのためです。自覚症状がなくても、腸に慢性的な負担をかけている可能性があります。
第二に、牛乳のタンパク質の約8割を占める「カゼイン」の問題です。カゼインは非常に粒子が大きく、消化しにくいタンパク質で、人によってはアレルギー反応を引き起こしたり、腸内で炎症を起こしてリーキーガットの原因になったりすることが指摘されています。
特に、鼻炎や喘息、アトピー性皮膚炎といったアレルギー症状が、乳製品をやめることで改善したという報告は数多くあります。
また、いわゆる「カルシウム神話」にも再考の余地があります。確かに牛乳はカルシウムが豊富ですが、吸収率が特別高いわけではありません。
小魚、海藻、緑黄色野菜(小松菜など)、大豆製品、ごまなど、日本人が伝統的に食べてきた食品からもカルシウムは十分に摂取可能です。むしろ、これらの食品とバランス良く摂ることが大切です。
乳製品との賢い付き合い方

もしあなたが原因不明の肌荒れや鼻炎、お腹の不調に悩んでいるなら、小麦と同様に、2週間ほど乳製品を完全に断ってみることをお勧めします。
牛乳、ヨーグルト、チーズ、生クリーム、バターなどを一切やめてみて、体調の変化を観察するのです。完全に断つのが難しい場合や、代替品を探している場合は、以下のような選択肢があります。
・植物性ミルクを活用する:牛乳の代わりに、豆乳、アーモンドミルク、オーツミルク、ライスミルクなどを試してみましょう。それぞれ風味や栄養価が異なるので、好みに合わせて使い分けるのがおすすめです。ただし、製品によっては砂糖や添加物が多く含まれているものもあるため、原材料表示の確認は忘れずに行いましょう。
・発酵乳製品を賢く選ぶ:ヨーグルトやチーズは、発酵の過程で乳糖やカゼインが一部分解されるため、牛乳よりは消化しやすいと言われます。もし食べるのであれば、無糖で添加物の少ない質の良いヨーグルトや、ナチュラルチーズを少量楽しむ程度に留めるのが賢明です。
・バターの代わりに:料理に使うバターの代わりには、ギー(Ghee)という選択肢もあります。ギーはバターを精製してカゼインや乳糖などの不純物を取り除いた純粋なオイルで、風味も豊かです。
乳製品は嗜好品と捉え、毎日大量に摂取するのではなく、自分の体調と相談しながら上手に付き合っていくのが現代的なアプローチと言えるでしょう。
第5章:手軽さの代償「加工肉」

朝食のベーコンやソーセージ、お弁当のハム、おつまみのサラミ。加工肉は安価で調理も手軽、そして子供から大人まで人気の食品です。
しかし、その手軽さと美味しさの裏側には、無視できない健康リスクが潜んでいます。
なぜ加工肉は問題視されるのか?
最大の懸念点は、製造過程で使用される「食品添加物」です。
特に、色を鮮やかに見せ、食中毒菌の繁殖を防ぐために使われる「亜硝酸ナトリウム(発色剤)」は、肉に含まれるアミンという物質と反応して「ニトロソアミン」という強力な発がん性物質に変化する可能性が指摘されています。
また、食感を良くし、保存性を高めるために使われる「リン酸塩」は、ミネラル(特にカルシウムや鉄)の吸収を阻害したり、過剰摂取が腎機能の低下や動脈硬化のリスクを高めたりすることが分かっています。
こうしたリスクから、2015年には世界保健機関(WHO)の専門組織である国際がん研究機関(IARC)が、加工肉を「人に対して発がん性がある」グループ1に分類しました。
これは、タバコやアスベストと同じ、最もリスクが高い分類です。これは、加工肉を食べると必ずがんになるという意味ではありませんが、日常的に食べ続けることで大腸がんなどのリスクが統計的に上昇することを示唆しています。
さらに、加工肉は一般的に高脂肪・高塩分であり、生活習慣病のリスクを高める一因ともなります。
加工肉との賢い付き合い方

WHOの発表は衝撃的ですが、加工肉を二度と口にしてはいけない、ということではありません。リスクを理解した上で、食べる「量」と「頻度」をコントロールすることが重要です。
・食べる頻度を減らす:毎日のように食卓に上るのであれば、それを週に1回、あるいは特別な日の楽しみにするなど、意識的に頻度を減らしましょう。
・「無塩せき」製品を選ぶ:スーパーで加工肉を選ぶ際は、パッケージに「無塩せき」と書かれたものを探してみてください。「無塩せき」とは、製造工程で亜硝酸ナトリウムなどの発色剤を使用していない製品のことです。色はくすんでいますが、より安全な選択と言えます。
・加工されていない肉を選ぶ:タンパク源としては、できるだけ加工度の低い肉を選ぶのが基本です。新鮮な鶏肉、豚肉、牛肉などを自分で調理するのが最も安全で健康的です。特に、高タンパク・低脂肪な鶏むね肉やささみ、鉄分豊富な牛の赤身肉などは積極的に活用したい食材です。
・魚や大豆製品も活用する:タンパク源は肉だけではありません。前述した青魚や、日本の伝統的な健康食である豆腐、納豆、味噌といった大豆製品をバランス良く食事に取り入れることで、加工肉への依存度を自然と減らすことができます。
おわりに:自分の体の声を聞き、選択する力を
ここまで、現代の食生活に潜む5つの食品について、そのリスクと賢い付き合い方を見てきました。
砂糖、小麦粉、植物油、乳製品、加工肉。これらは私たちの食を豊かにしてきた一方で、過剰摂取が心身の不調に繋がる可能性がある、両刃の剣のような存在です。
繰り返しになりますが、この記事の目的は、これらの食品を完全に排除する「完璧な食生活」を強いることではありません。
大切なのは、これまで「なんとなく」口にしてきたもの一つひとつに意識を向け、その正体を知り、自分の体調を観察しながら「今日の自分にとって、何がベストか」を主体的に選択していくことです。
完璧を目指す必要はありません。まずは、何か一つ、できそうなことから始めてみませんか。
「明日の朝のジュースを水に変えてみる」
「週に一度、パン食をご飯にしてみる」
「お菓子の代わりに、ナッツを一掴み食べてみる」
その小さな一歩が、あなたの体の声を聞く第一歩です。
食生活の見直しは、単なる健康法ではなく、自分自身と向き合い、大切にするための素晴らしい旅路です。情報に振り回される「受け身の健康」から、自分で選び、コントロールする「攻めの健康」へ。
この記事が、その旅の羅針盤となれば、これほど嬉しいことはありません。