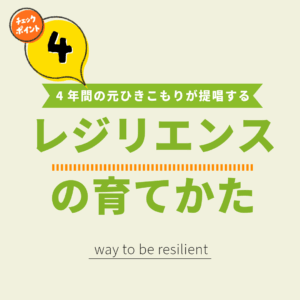介護タクシーの許可申請を最短・最速で開業するための裏技&開業後の有料級営業先について

はじめに
本記事は、2025年7月末に法人で介護タクシーの許可を申請しようとしたが、幅員証明が取れず、やむを得ず個人で関東運輸支局内にて自力で介護タクシーの申請を行った経験をもとに各要点や注意事項を織り交ぜながら記事に落とし込んでいます。
なるべく早く介護タクシーの許可申請をパスしたい人向けの内容となりますが、抑えるべきポイントは細かく解説しておりますので、余裕を持って申請される方にも参考になるように内容を盛り込んでいますので、拝読頂きたくさんの方のお役立て頂けたら幸いです。
1.申請段階では法人か個人どちらで申請するか迷う必要なし!

介護タクシーの許可申請をする上で法人、個人どちらで申請するべきか悩まれる方が多くいらっしゃると思います。
私は株式会社を経営しているので法人で申請しようとしましたが、私市道且つ前面道路の所有者が7人で集団所有されている30年以上前の住宅地の中に本社がある為、使用承諾書を得られず幅員証明書でつまづき法人での申請を断念しました。
費用的・手間的、事業展開的に考えれば勿論、最初から法人として申請した方がメリットがありますが、法人と個人では揃えるべき必要書類の種類も異なる為、申請だけで見れば間違えなく早く簡単に申請出来るのは個人で申請する方法です。
私自身、介護タクシーの業界は初めてですし、知見や知識は全くないですが、長く運輸業には携わってきたので業界の先輩や様々なプラットフォームなどで情報収集をし、スタート段階では個人スタート、その後法人に移行する方法で問題ないと感じましたので、お困りの方はまずは個人から申請してみてはいかがでしょうか。
2.残高証明書と幅員証明書の手続きを最優先しましょう

残高証明書

残高証明書を発行してもらうには、直接銀行に本人が出向き身分証明書と届出している印鑑、通帳又はキャッシュカードを持参する必要があります。
残高証明書を発行するのに記入すべき書類を記入した後、支払手数料880円(銀行により手数料は前後します)を支払い、手続きに1週間程時間を要します。最低でも1週間なのでこの手続きは最優先ですべき手続きとなります。
後日、支払手数料を支払った用紙を銀行窓口に持参し、残高証明書を店頭窓口で受け取る流れとなります。
ここで注意するべき点は、残高証明書を申請した日の翌日までは口座の中のお金を引き出さない事です。あくまで記載日の最終残高が残高証明書に記載されるので、手続きが終わった瞬間などに現金を引き出すと残高証明額が下回ってしまうので、引き出すなら翌日以降に引出して下さい。
ここをミスすると申請書類の様式例3-1事業開始に要する資金及びその資金の調達方法という書類で「合計」の50%相当額の部分がクリア出来ず再提出しなければいけなくなるので、本当に注意して下さい。
幅員証明書

幅員証明書を取得するにはまず法務局で構図を入手する必要があります。幅員証明書を取りたい場所の住所を記載し支払手数料500円(取得方法等により金額は前後します)を支払って構図を取得します。私も手こずりましたが、構図の申請用紙の書き方が非常に分かりにくいので窓口の方に聞きながら記載するのが手っ取り早いです。
構図自体はその日にすぐ取得できますがこの構図と案内図(最寄駅から幅員証明の住所地までの経路)と車の諸元表を持参して幅員証明書を取得したい市町村の土木課等で申請します。
最初、法人で申請しようとしたときは構図、案内図、車の諸元表が必要と言われましたが、個人で幅員証明書を取る際は構図と案内図のみで申請出来ました。
事前に市町村に電話で何課に行けばいいか且つ必要書類は何かを確認してからいく事をお勧めします。また、費用は450円前後かかります。無料で発行してもらえないので注意しましょう。
また、幅員証明書の発行には1週間~2週間かかりその市町村の混雑状況に左右されるため、残高証明書の手続きと同時に行いましょう。
この幅員証明書の申請書の中に申請理由を書く欄がありますので、必ず介護タクシーの許可申請に使用する為と記載して下さい。この文言がないとせっかく時間も費用もかけたのに申請書類として却下されます。そうなってしまうと、やり直しとなりまた数週間時間と手数料が無駄になりますのでよく記載内容に不備がないか確認してから申請しましょう。
+αの豆知識(余談)

個人の戸籍抄本は本籍地の市役所(町役場)でしか発行してもらえないので注意して下さい。私はこのトラップに引っかかってしまいました。人によっては本籍地がものすごく遠くてこれこそ時間も費用もかかる可能性があるので+αの豆知識として記載させて頂きます。
3.申請に必要な必要書類と分かりにくい記載事項の書き方について

ここでは分かり易く一発で介護タクシーの許可申請を行う為の方法を詳しく解説します。まずは下記の書類順に並べてみて下さい。
●【自動許可運賃様式】一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金(福祉輸送サービス)認定許可申請書
※注意点
①タクシーメーターは必須ではないので時間制料金にすればタクシーメーター代約16万円が必要なくなります。
②1台スタートでも特定大型車、大型車、普通車すべてに運賃を記載しましょう。また、時間制の場合には迎車回送料金の設定は出来ないので迎車回送料金の場所は空欄で提出します。
●一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書
●事業計画
※注意点
①面積や収容能力の求め方は素直に縦×横です。場合によりkmをmに直したりする必要がある場合があるので注意しましょう。
②自動車車庫の営業所からの距離を記載する欄は営業所と自動車車庫が隣接する場合には0kmと記載してOKです。
③車両を購入前に申請する場合には見積書と諸元表を提出することで許可申請を行えますが、自己所有の車だとしても車両の形状が福祉車両ではないケースが殆どだと思います。貨物車以外の乗用車で申請する時は、車両の形状欄はセダンでなくてもセダンにチェックを入れて申請しましょう。その際は、指定されている介護系の資格が必要となります。指定された資格を所持していれば福祉車両でなくても許可申請はパス出来るので問題ありません。
●案内図(Googleマップ等を活用し、最寄り駅から営業所、車庫、休憩施設等が分かるように作成)
●平面図(建築時の設計図を活用し、各対象場所をマーカーで囲み、面積等の計算式を記載します)
●様式1 宣言書
●賃貸契約書等(家族所有等の場合には建物・土地使用承諾書という書類でも代用できます)
※注意点
①建物・土地とそれぞれ記載があること。
②面積や収容能力等計算式を交えて記載すること。
③一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)の文言や、営業所、自動車車庫、事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設という文言が抜け落ちないように記載すること。
●幅員証明書(道路有効幅員証明申請書)
●構図
●車検証・任意保険の見積書(リースの場合には契約書及び諸元表、購入前の場合には見積書及び諸元表で代用可能です)
●福祉車両以外又はセダン車の場合には指定福祉系の資格証明書(居宅介護系や介護福祉士資格など)

●事業用自動車の運行管理等の体制
※注意点
①一人で申請する場合には、すべて自分の名前で記載する事が出来ます。
●様式例3-1 事業開始に要する資金及びその資金の調達方法
※注意点
①ここの記載方法の差し戻しが殆どの確率であるので申請提出前に残高証明書を受け取った時点で、直接最寄りの運輸支局に出向いて不備がないかなど間違えがないか直接職員の方に確認してもらった方がスムーズに後の処理が進みます。
②自己資金額が「合計」の50%相当額を下回っているか要確認しましょう。下回っていたら計画を練り直して下さい。
●様式例3-2 資金の調達方法
●残高証明書
※注意点
①なるべく発行日から1週間以内に窓口にて申請を行いましょう。遅くなると発行し直すことになりかねます。
●様式例4 宣言書
●様式例5 宣言書
●様式例7 宣言書
●資産目録 (残高証明書の金額のみ記載でも受理されます)
※注意点
①作成日、作成者の記載は必須となります。
●戸籍抄本
●履歴書(簡単な経歴や資格が分かるような履歴書且つ写真は不要です)
●運転免許証(両面コピー)
上記が個人で介護タクシーを申請する必要書類となります。よく注意事項を確認して分からなければ都度、電話や窓口に行って確認する作業が必要となります。ここを怠ると、許可が下りるまで時間がかかりますので注意しましょう。
4.最速で介護タクシーの許可が下りる期間について
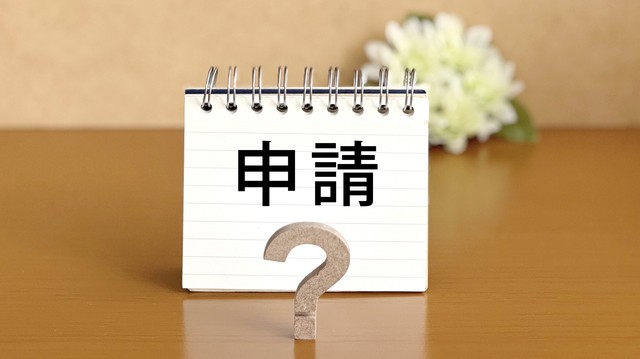
ここまで早く必要書類を揃えて申請する方法について触れてきました。皆さんが一番知りたい情報として結局申請してから結果的にどれくらいで介護タクシーの許可が下りるのかということ。答えは最短約2カ月で許可が下ります。
運輸支局の窓口では許可が下りるまで約2カ月~3ヵ月程度みて下さい。こう言われるはずです。ここには、書類不備による再提出などによる遅延も含め長めに伝えられていると認識して下さい。
なので、不備を無くせば最速約2カ月で許可が下りるということになります。勿論、行政が処理を行うので一般的な繁忙期や人員の状況、他の許可申請者の増加等による混雑等によって前後はあるかもしれませんが、提出書類に不備がない。これに尽きます。
不備が無い必要書類を作成する為には、提出前にしつこく運輸支局窓口職員さんに確認してもらいましょう。また、記載方法が分からないところや疑問に感じた箇所は曖昧にしないで何度もしつこく確認しましょう。あたりまえの事ですがあたりまえにクリアする事が重要です。
申請前の準備~申請迄全て計画性を持って準備することが最速で介護タクシーの許可が下りる絶対条件となります。
関東運輸支局内で許可を取れば法令試験はありません!
何と言っても他の県ではありえないですが、関東運輸支局内で介護タクシーの許可申請を行うと法令試験の実施はありません。ビックリですよね。でも、事実として法令試験がありませんので関東運輸支局内で介護タクシーの許可を申請される皆さんはとても運がよくラッキーです。
5.許可申請が終わってから許可が終わってからすべきこと

市役所にて助成金が活用できないか確認する
各市町村によって介護タクシー開業における助成金が活用できる場合があります。事前に電話で助成金に対応しているかどうか確認するのもいいですし、直接出向いて確認してもいいですし、ご自身のやり易い方法で確認を行ってみて下さい。
万が一、助成金が活用できるのに使用しなかった場合には、数十万円以上損してしまう可能性があるので申請後すぐ動きましょう。
営業ナンバーをつけられる車両を用意する
許可が下りた後、6か月以内に運輸開始届を提出しなければならないので申請時に一旦仮の車、トヨタのKINTOという個人でリース契約した車両、購入予定で申請した場合など、車両を新たに購入しなければならない方にとってはなるべく早くめぼしい車両を見つけて購入しなければなりません。
また、民間救急事業をされる予定の方は寝台等に対応した構造の車両を用意する必要があるので、なかなか良き車両が見つからないのが現状の課題です。
中古車の相場が高く、ちょっと出せば新車が買えてしまう。リセールを考えても新車の方がいいかもしれない。様々思うこともあるかもしれませんが250万円前後で買える低走行車で程度が良い福祉車両があれば一旦買ってしまって大丈夫です。
結局、新車で福祉車両を購入するには車両が届くまで6か月以上かかるケースが殆どなので営業開始後、事業が軌道に乗ってから新車を購入する事をお勧めします。また、居宅介護系の資格があるから車両は何でもいいと思う方もいらっしゃると思いますが、事業領域が狭まるのであまりお勧めは出来ません。最低限福祉車両は購入した方が良いです。
6.介護タクシー開業後にやるべき営業先や営業方法について

ここさえ押さえられれば暇なく忙しく介護タクシーの経営が出来るようになる営業先や営業方法をご紹介します。但し、競合他社も当然営業をかけているので自社の強みは何かちゃんと考えて業務に落とし込んで下さい。営業スキルには個人差があるので相手先に不快な気持ちにさせる事がないように注意しましょう。
①自社のホームページの作成、SNSの開設、営業チラシ及び営業用の名刺を作成する
②無料で掲載できるウェブ集客サイトに片っ端から登録する
➂病院やクリニックのソーシャルワーカーに営業する
④居宅介護支援事業所のケアマネージャーに営業する
⑤地域包括支援センター、ヘルパーステーションに営業する
⑥高齢者施設の相談員やケアマネージャーに営業する
⑦行政機関の市役所や町役場で福祉輸送の補助制度がある福祉課や障害福祉課に営業する
⑧特別支援学校や支援学校・教育委員会の担当者に営業する
⑨薬局・整骨院・接骨院・マッサージ店に営業する
⑩同業者と仲良くする
7.他社の差別化をするためのアドバイス

他社との差別化や自社の強みとは何かを追求する上でのヒントやアドバイスをここではご紹介したいと思います。
民間救急の認定証の交付を受ける

消防機関の行う患者等搬送事業者の乗務員基礎講習を受講後、適任証の交付を受けた後に患者等搬送事業者の認定証の交付を受け、民間救急事業者として業務拡大を行う。
また、より重篤な患者様へのサービスとして酸素ボンベの提供ができるようになるメリットがあります。取扱いには注意事項があり対応には決められたルールがあるので注意が必要ですが、まだまだ歴史は浅く今のうちに認定証を受けるメリットは非常に大きいと思います。
通院等乗降介助に係る申請をする

個人で介護タクシーを開業し、事業が軌道にのると法人化を意識するようになると思います。法人化し大規模化を視野に入れ始めることでしょう。その際に、株式会社やNPO法人等を視野に入れてみてはいかがでしょうか。法人化し、所定の手続きを行うことで通院等乗降介助を提供することが出来ます。
流れは下記の通りです。
①NPO法人等の法人格を取得しする
②都道府県又は市町村町へ訪問介護又は居宅介護の指定申請を行い、指定を受ける
➂地方運輸局支局等で、介護タクシーの許可申請を行い、許可を受ける
④訪問介護又は居宅介護の指定を受けた都道府県又は市町村町へ、通院等乗降介助の算定届を行う
⑤地方運輸局支局等へ訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可申請を行い、許可を受けること
上記の手続きを経て許可を取る事で、他社との差別化に繋がります。意外と地域によっては競合他社が少ない地域もあるので個人から法人化も視野に入れて事業拡大してはいかがでしょうか。
まとめ

ここまで本記事を拝読頂きありがとうございます。介護タクシーの許可は確かに必要書類を揃えるのがめんどくさいですし、実際に自分で申請して本当に許可が取れるのか不安になる方もいらっしゃると思いますが、わざわざ専門家の方に申請を依頼し高いお金を支払わなくても自分で申請できます。
事前準備をしっかり行って、順序通り行えば申請から最短約2カ月程で許可が下りるので心配しなくて大丈夫です。
集客についても営業先や営業方法を上手く工夫して他社との差別化や自社の強みを発揮できれば何十年先も成長し続ける経営が出来ると思います。
人の命に関わる仕事なので謙虚な気持ちを持って仕事に取り組みましょう。同じ業界の同業者となり得る皆様とどこかでお近づきになれたら嬉しいです。
本記事が皆様のお役立てたなら幸いです。では、一歩踏み出して頑張りましょう!