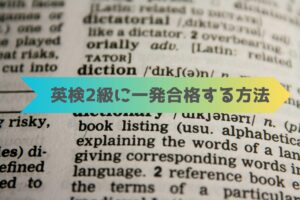【持っているだけで即戦力】労働衛生コンサルタント資格に一発合格する為の勉強法

この記事では労働衛生コンサルタントの資格試験で合格を目指す方に、過去の出題傾向から勉強しておくべきポイント、おすすめテキストや問題集を紹介しています。
これから労働衛生コンサルタントを目指して勉強を始めようと思うけど、何から始めれば良いのか分からないといった方は必見です。
また、労働衛生コンサルタントに興味があるけど、よく分からないといった方にも参考になる内容となっています。
ぜひ最後まで読んでみてください。
1、労働衛生コンサルタントとは?

労働衛生コンサルタントは、資格を取得して登録した人のみができる職業です。
労働者の働く環境の衛生面について、事業所の診断や指導を行う職業のことです。
事業所からの依頼に基づき、第三者の立場から事業所の衛生水準を向上させて快適な職場環境を整えるためのアドバイスをします。
労働衛生コンサルタントは「保健衛生」と「労働衛生工学」の区分で分かれています。
保健衛生の区分では、看護師や医師などの医学の知識を持った方も多く登録されていて、中には産業医として働いた経験を活かし、労働衛生コンサルタントとしても活躍されている方もいます。
労働衛生工学の区分では、有害ガスや粉塵などの体に害のある物質が発生するような職場環境でも、安全に働けるようにするための分野です。
労働衛生コンサルタントになるためには、国家試験に合格して国家資格を取得し、厚生労働省の「労働安全衛生コンサルタント名簿」に登録する必要があります。
資格試験も区分に分かれていますが、どちらに合格したとしても仕事の内容が制限されることはありません。
登録する名簿に「登録区分」として合格した区分が記載されます。
2、合格率や受験資格などの試験概要

2−1、労働衛生コンサルタントの受験資格とは
労働衛生コンサルタントの資格試験は誰でも受けられる試験ではありません。
受験資格のある資格試験です。
この受験資格は、例えば歯科医師、医師、薬剤師、一級建築士などの特定の免許を受けている方や受けられる方、保健師や作業環境測定士として特定の年数以上従事した方、理系の学科を修めた後に衛生の実務に従事した経験のある方などです。
受験資格の要項は約30あります。
また、それに伴い、試験科目が免除になる要項もあります。
該当する要項によって提出する証明書なども違いますので一度確認してみてください。
少し話は逸れますが、受験者の中にはあえて免除を受けずに受験する方がいるようです。
それは、筆記試験合格後に口述試験があるからです。
免除された科目もしっかり理解していないと口述試験で合格できません。
結局、全ての科目を勉強しなくてはならないという事が理由の一つです。
また、この後詳しく書きますが、問題一つ一つのウエイトが大きくなってしまうというデメリットもあります。
他にも免除を受けている方に対する口述試験の評価が厳しくなるのでは?という意見もあるようです。
受けられる免除は全て受けた方が良いという考えの方もいますし、免除を受けない方がメリットがあると感じている方もいます。
いくつかの受験資格の要項に該当し、免除を受ける、受けないが選択できる場合には、免除を受けないで受験するということも一つの選択肢にあるということを覚えておくと良いかもしれません。
2−2、労働衛生コンサルタントの試験科目と合格基準、合格率
労働衛生コンサルタントの試験は「保健衛生」と「労働衛生工学」のどちらか一つの区分を受験します。
受験科目はどちらも共通で「労働衛生一般」と「労働衛生関係法令」の2科目(択一式)と保健衛生の区分の場合は「健康管理」(記述式)、労働衛生工学の区分の場合は「労働衛生工学」(記述式)を選択し合計3科目の筆記試験を受験します。
総得点が概ね60%以上です。
しかし、1科目40%未満の科目があると不合格となってしまいます。
科目の免除を受けると、間違えられる問題数が減ってしまいます。
そのため、免除を受けない方が有利なのでは?といった考えもあるようです。
筆記試験に合格した場合、口述試験があります。
口述試験は4段階で評価され、上位2つのランクの評価が合格、下位2つの評価が不合格となります。
合格率は例年、筆記試験で30%前後、口述試験で50%前後です。
筆記試験の合格率は他の国家試験の合格率と比較してもそこまで低くないですが、口述試験までの合格を考えると難しい試験の一つと言えるでしょう。
3、「労働衛生一般」と「労働衛生関係法令」の筆記試験対策

ここではどの科目も免除を受けず、全て受験する方向けのおすすめ試験対策をご紹介します。
労働衛生コンサルタントの試験勉強の時間は長く見積もった方が良いでしょう。
なぜなら、出題範囲が広く幅広い知識が必要な上に、細かい部分を問われる問題が出題されているため、浅く広い知識でも狭く深い知識でも合格するのが難しいからです。
労働衛生コンサルタントには幅広い知識と、プロフェッショナルとしての深い知識が求められています。
何も免除を受けずに受験する方、特定の科目だけ免除をして受験する方、口述試験のみ受験の方にも読んでいただける試験対策、おすすめの勉強方法をご紹介します。
筆記試験を受ける方は、勉強方法としてはテキストと過去問集を購入して過去問集を解きながら、理解できていないところをテキストで確認する勉強法がおすすめです。
この勉強法を繰り返すことで定着させることや理解を深めることに繋がります。
おすすめのテキストや過去問集については、あとで紹介します。

最初に「労働衛生一般」を勉強するのがおすすめです。
この科目は基本的な知識で解答できる問題が出題されやすい傾向にあります。
得点源であるため幅広く知識をつけることが重要です。
また、衛生の現場で実務経験のある方なら取りかかりやすい科目かと思われます。
知識を言語化することや、間違えて理解している事柄などがないかに注意して勉強すると良いでしょう。
次に取り掛かるおすすめの科目は「労働衛生関係法令」です。
覚えることが多いこと、細かい部分まで出題されやすい傾向にあることから、時間をかけて勉強するのがおすすめの科目となっています。
過去問と同じ問題になることはほとんどありませんが、出題されやすいポイントを知って、そのポイントの理解をより深めることが合格への近道になります。
過去の合格者の中には、過去問を解きながらわからないキーワードやポイントとなる数字をノートなどに書きまとめて、試験の対策をしている方もいるようです。
後で調べて要点をまとめることで、理解を深めることができますし、試験直前に見返すことができたり、合格後の実務でも役に立っているようです。

出題傾向から、筆者が特に勉強しておいた方が良いポイントと思う点をまとめておきます。
衛生管理者、産業医、衛生工学衛生管理者の専任と専属については頻出です。
事業所の労働者の人数毎の配置人数や、有害業務の中で衛生管理者の業務に含まれる業務と含まれない業務についてなどの理解を深めておきましょう。
暗記するべき事柄が多い内容ではありますが、問題に紛らわしい言い回しで出題されることもありますので、しっかり区別がつけられるようにしておくと良いでしょう。
電離放射障害防止、熱中症対策、高気圧作業、振動などについてもよく出題されています。
その内容や、政府から出されている指針についても勉強しておくと良いでしょう。
保護具についての問題も頻出のため、理解を深めておくことが必要です。
また、粉塵についての問題も必ずと言っていいほど出されています。
範囲も広く、こちらも覚えることの多い内容です。
苦戦する方も多い内容になっています。
勉強時間は長めに配分して見積もっておくと良いでしょう。
4、記述式問題の試験対策

記述式問題は受ける区分によって異なります。
保健衛生区分で受験した場合は「健康管理」、労働衛生工学区分で受験した場合には「労働衛生工学」が出題されます。
出題数は4問で、そのうちの2問を選択して解答します。
4問全てに解答したからといって全てを採点してもらえるわけではなく、3問以上解答してしまった場合には採点して欲しい問題に印をつけて意思表示しなくてはならないようです。
運良く得意分野からの出題であればそれを選択すれば良いのですが、そうではない場合も多く、「問題の選択をするだけでも時間がかかってしまった」といった体験談もありました。
対策としては満遍なく解答できるように知識を増やしておくことが一番ですが、選択に迷った場合には時間をかけないことを意識して、パッと決めてしまう決断力も必要かと思います。
なるべく解答する時間に回した方が得策です。
労働衛生工学区分の記述式問題には計算問題が出題されます。
例えば振動に関連した問題では、異なる振動工具を使用した作業や作業時間を仮定し、1日の振動ばく露量の限界値から作業時間を答える問題などが出題されたことがあります。
数値や計算方法を暗記して理解しておくことが対策として必要です。
また、局所排気装置などに関連する計算問題も頻出しています。
健康管理区分の記述問題では、説明を求められる問題や、改善点を挙げるなどの問題が出題される傾向があります。
例えば、高齢労働者の休業4日以上の労働災害を、若年者と比較して特徴を説明する問題などが出題されました。
テキストに書いてあるような知識で解答できる問題もありますが、しっかりと理解を深めておくことが対策として必要です。
5、口述試験対策

筆記試験に合格すると、口述試験に進むことができます。
筆記試験の合格発表から1ヶ月程度で口述試験になります。
採点基準や合格基準が公表されていないため、具体的な試験対策が難しいのですが、筆記試験のために勉強した知識に基づき、それに対しての受験者の考えを伝える力が必要です。
最初に労働衛生に関する経歴を聞かれることが多いようです。
労働衛生コンサルタントとしてどう活躍していきたいのか?ということが答えられると良いでしょう。
労働衛生コンサルタントとして事業所に関わりたいのはなぜなのか?
例えば、産業医のままではダメな理由などです。
志望動機などを整理しておくことをおすすめします。
次に「労働災害が起こってしまった時の企業の責任とはどんなものですか?」など知識について問われるような質問をされます。
それについて深掘りするような質問がされ、知識に基づき自分の考えなどもプラスして答える…
また違う質問がされ、深掘りされ…というのが口述試験の大体の流れのようです。
その中で、労働衛生コンサルタントとしての資質をどれだけアピールできるかが合格のポイントでしょう。
また、YouTubeなどの動画でも口述試験対策ができます。
自分の考えをまとめることと、それを簡潔に喋れるようにしておくことが対策になります。
実務を想定しておくことも、試験対策として有効です。
「例えばこんな相談をされた時に、どのように答えますか?」といった質問と解答のバリエーションをたくさん想定しておくのも良いでしょう。
6、おすすめのテキスト

「わかる わかる 第一種衛生管理者試験」オーム社出版
このテキストは労働衛生管理者試験の受験者用のテキストと問題集です。
しかし、労働衛生コンサルタントを受験した合格者からの口コミもとても良いテキストでした。
労働衛生についてとても分かりやすく書かれていて、受験者の中には使っている方も多いようです。
「スッキリわかる 衛生管理者 テキスト&問題集」TAC出版
このテキストも衛生医管理者向けのテキストです。
しかし、イラストが多くあり読みやすいテキストです。
労働衛生とは?というところから勉強を始める方にはとてもおすすめのテキストになっています。
取りかかりやすく、労働衛生のイメージをつかむためには最適なテキストです。
「職場の健康がみえる 産業保険の基礎と健康管理」メディックメディア出版
こちらもイラストが多めで読みやすく、最初に読むと良いテキストです。
合格後の実務でも参考になるため、合格後も参考書のように使うことができます。
労働衛生コンサルタント向けのテキストではないものの、労働衛生の基礎から法令まで分かりやすい本です。
「労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント試験問題集」
日本労働安全衛生コンサルタント会の過去問集です。
インターネットでも過去問はみることができますが、問題だけで解説などがありません。
こちらは解答と解説がついていますので、試験対策にはこちらを使う方がおすすめです。
2年分が1冊にまとまっています。
最新版は令和5年度版ですが、令和6年度版は令和6年6月に販売される予定となっています。
「労働衛生のしおり」中央労働災害防止協会出版
こちらは最新版が令和5年度版となっています。
受験の際は一度は読んでおいた方が良い本です。
最新版は令和5年度版ですが、例年8月末に発売されています。
令和6年度版ももう少し待てば発売されることが予想されます。
口述試験の対策にも役に立つ本です。
「これで完成!口述試験対策 労働衛生コンサルタント問題集」岩見謙太郎(著)
口述試験の予想問題など、分かりやすく書かれています。
2024年の最新版もすでに販売されており、最新の出題傾向も載っています。
筆記試験合格から口述試験まであまり時間のない中での試験対策にとてもおすすめです。
7、講習会などの活用もおすすめ

労働衛生コンサルタントは、自力で合格を目指すこともできる資格ではあります。
しかし、範囲がとても広いことや、深い知識が必要な資格でもありますし、インターネットの情報も少ないのが現状です。
限られた時間の中で勉強を効率よく進めるために、講習会などを活用しながら合格を目指すのもおすすめです。
おすすめの講習会などを紹介します。
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会が実施する「労働衛生コンサルタント受験準備講習会」は、会場での受講とオンラインでの受講も可能です。
過去の試験の傾向や最新の傾向も網羅した内容になっており、ポイントの絞った勉強をすることができます。
過去には労働衛生コンサルタント受験者向けのセミナーが他にも開催されていたようですが、毎年の開催ではなかったり、最近は開催されていなかったりするようです。
労働衛生コンサルタント向けではありませんが、まずは労働衛生管理者向けの講習会に参加するのもおすすめです。
講師の方に労働衛生コンサルタントの資格をお持ちの先生が登壇される講習会もありますので、参考になるかもしれません。
8、まとめ

事業所の内部の人ではなく、外部から問題を抽出することができる労働衛生コンサルタントは、労働環境の向上のために必要な人材です。
コンプライアンス向上を意識している企業が増えていることや、労働環境向上の意識が高まっていることから、何か問題が起こってからだけではなく、問題が起きないようにアドバイスや指導ができる貴重な人材のニーズが増えていくことでしょう。
ぜひ取得を目指してみてください。