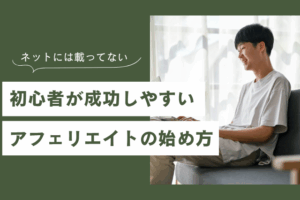【2025年7月最新】労働衛生コンサルタント試験に一発合格するための勉強法

本記事は、独立やキャリアアップのために「労働衛生コンサルタント」の資格を取ろうとお考えの方に読んでほしい、労働衛生コンサルタント試験に合格するための勉強法を紹介する内容です。
自身の状況や環境を考慮しながら、時間効率・コストパフォーマンスを踏まえた、最善の勉強法や合格するために必要な戦略について考えていきましょう。
■受験資格の確認

労働衛生コンサルタント試験を受けるには、受験資格を満たしている必要があります。
受験資格は全部で27も存在しますので、まずは自分が労働衛生コンサルタントの試験を受ける資格があるのかどうかチェックしてください。
ただ、それぞれの資格を有していても、条件によって受験資格がないケースもありますので、注意が必要です。
たとえば、受験資格のひとつに「衛生管理者」がありますが、免許を受けていても「常時50人未満の労働者を使用する事業場」であった場合は受験資格がありません。
一方、資格の内容によって試験科目が免除されることもあります。医師免許を持ってれば、講習を受けるだけで全科目が免除されます。
これは極端な例だとしても、「作業環境測定士」の免許があると「労働衛生一般」と「労働衛生関係法令」の科目が免除されます。
実際、労働衛生コンサルタント試験の受験者には、試験を有利に進めるために、作業環境測定士の資格を取得する動きも見られます。
このように、受験資格は試験に大きく関わってきます。必ず受験資格の要項を確認してください。
■労働衛生コンサルタント試験について

労働衛生コンサルタントの試験は1年に1回です。令和7年度でいえば、最初の筆記試験が10月21日に設定されています。
したがって、いまこれから労働衛生コンサルタントの試験を受けようと思っても準備期間は3ヵ月しかありません。
試験は例年、10月中旬から下旬にかけて行われますので、そこを目安に勉強のスケジュールを計画すると良いでしょう。
特に労働衛生コンサルタント試験を目指す最初の年は重要です。
たとえば人事異動をきっかけにキャリアアップの一環として労働衛生コンサルタントを目指そうとしたとき、人事異動のシーズンとなる4月と10月では勉強に費やせる期間が大きく変わってきます。
試験を志すタイミングを考慮して合格するための戦略を立てましょう。
■試験の概要

ここからは、労働衛生コンサルタント試験についての詳細と、それに伴う戦略や勉強法を個別に見ていきます。
労働衛生コンサルタントの資格は、労働衛生分野における最高レベルの資格であり、合格率が30%未満という難関な国家資格です。ただやみくもに勉強するだけでは合格するのが難しい現状があります。
また、受験者の多くは、特定の職業に就きながら労働衛生コンサルタントの資格取得に挑みます。つまり、仕事の合間を縫って勉強していかなければならないので、効率よく効果的な勉強方法を考える必要が生じるのです。
それでは、労働衛生コンサルタント試験の細かな部分を確認しながら、対応策などを検討していきましょう。

<試験区分>
労働衛生コンサルタント試験には、「保健衛生」と「労働衛生工学」の区分があります。前者は主に健康管理面について、後者は環境・作業管理をメインしたもとのなっています。受験者はどちらかを選択して試験を受けることになります。
「保健衛生」の受験者には医者や看護師が多く、「労働衛生工学」のほうは製造業や建築業に勤めている方が多いです。
「保健衛生」の区分では、医療の専門でなくとも、社会福祉や医療保険業といった分野から挑戦するケースもあるので、こういった業界に勤めている方は優位性を発揮できる可能性が高まります。
<試験科目>
試験科目は、区分共通で出される「労働衛生一般」と「労働衛生関係法令」と、区分の専門科目となる「健康管理」か「労働衛生工学」の全3科目です。共通科目は択一式(マークシート)で、専門科目は記述式が採用されています。
「労働衛生一般」は30問、「労働衛生関係法令」は15問で、それぞれ1問正解につき10点となっています。
配点でいえば「労働衛生一般」のほうが重要そうに思えますが、この試験では合格基準が総得点のおおむね60%以上であることに併せ、1科目につき40%の正解率未満のものがあれば不合格になってしまいます。
これまで「労働衛生関係法案」は難易度が高い傾向にあるため、本科目によって足切りされるケースも多く見受けられています。
1問のミスに対するダメージ小さい労働衛生一般よりは、労働衛生関係法案」を多少重点的に勉強するほうが得策かもしれません。
一方で、医師資格を有する方が労働衛生コンサルタント試験を受ける場合には少し事情が異なります。
前述のように、医師免許を持っている方は講習を受ければ筆記試験が免除されますが、講習を受けていなくても「労働衛生関係法案」の1科目のみで受験できます。
しかしその場合、免除されている「労働衛生一般」は合格に必要な最低ラインとなる正答率40%、つまり60点と計算されます。
したがって、「労働衛生関連法案」で合格ラインとなる60%=18問正解の150点を取ったとしても、2科目合わせると24/45となり、60%ボーダーにわずかに届かない計算となってしまいます。
このように、必ずしも免除が合格へ有利に運ぶとはかぎりません。
たとえば産業医であるならば、専門知識を活かすことができる「労働衛生一般」による上乗せを期待し、あえて免除を受けないで受験する選択肢も考慮するなど、立場や環境に応じて対応することが大切です。
<試験範囲>
公益財団法人・安全衛生技術試験協会によれば、労働衛生コンサルタントの試験範囲については、以下のようになっています。当然ですが、科目ごとに異なるのでしっかり確認してください。
◯労働衛生一般
労働衛生概論/健康管理の概論/労働整理概論/作業環境管理の概論/人間工学概論/化学物質の管理/作業管理の概論/労働衛生保護具/労働衛生教育/労働災害の調査および原因の分析/安全管理概論/事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業差やが一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置を含む)
◯労働衛生関連法令
労働安全衛生法、作業環境測定法および、じん肺法ならびにこれらに基づく命令のうち労働衛生に係るもの
◯健康管理(保健衛生区分)
労働心理学/産業心理学/労働衛生学/健康診断および面接指導等ならびにこれらの事後措置/作業環境の管理方法/作業方法の管理/健康の保持増進対策/救急措置/快適な職場環境の形成
◯労働衛生工学(労働衛生工学区分)
作用環境の管理技術/作業環境における有害因子とその影響/快適な職場環境の形成
上記試験範囲について、該当するキーワードから参考になりそうな書籍や情報から知識を得るというのが、一般的な独学による勉強法の中心になると思います。それぞれの科目においては、法律・学問・実務など、カテゴリーごとにまとめて効率化を図るといった方法も有効ではないでしょうか。
■筆記試験対策

それでは、試験科目別にそれぞれの対策や勉強法などについて紹介していきます。
ただ、必ず合格できる必勝法や知識なしでも合格レベルまで到達できる裏技などは存在しません。
ひたすら反復学習したり、勉強するための時間をより多く確保するであったりと、基本的なことをコツコツやっていくことが合格に一番の近道であることは忘れないでください。
<労働衛生一般>
「労働衛生一般」科目のオーソドックスな勉強としては、「過去問をやり込む」があります。これまで出題された問題をまとめた試験問題を繰り返し取り組む方法です。
先に述べた安全衛生技術試験協会のホームページからは、過去2年分の問題がそれぞれの科目ごとにPDFファイルで作成されていますので、それを活用できます。
また、それ以前の過去問を取り扱っている問題集を購入することも可能です。こちらは、問題についての解説がついているので、より理解を深めることができます。
過去問を繰り返すことで自分の苦手な領域や知識の弱い部分がわかってくると思います。その場合には、次のステップとしてその内容に特化した書籍を読み、弱点を補う必要があります。
「労働衛生一般」はその名のとおり、広い範囲にわたる知識を求められますので、なるべく偏りのないように勉強したほうが良いでしょう。
ただ逆にいえば、深い知識がそれほど必要ないとも言え、「労働衛生関連法令」や「衛生工学」などのほかの科目を勉強していくうちに「労働衛生一般」の知識も増えていくようなケースも少なくありません。
<労働衛生関連法令>
こちらの「労働衛生関連法令」も、過去の問題を掘り下げていくやり方がオーソドックスなパターンとなります。
しかし、法令をきちんと理解していないと解けない問題も多く、「労働衛生一般」より求められる知識のレベルが一段上がるようなといった印象もあります。広さより深さに重点を置いたほうが良いかもしれません。
対策としては、「安全衛生法」に関する書籍を中心とした勉強が有効になるのではないでしょうか。基本となる法律を理解することで、相乗効果を期待できます。
また、「衛生管理者」や「作業環境測定士」といった似たような資格を取るための問題集や参考書も大いに役立つでしょう。どちらも業務や知識に共通箇所が多く、より基礎的に体系的に学べる機会となるはずです。
このように、少しアプローチを変えますと、単に「労働衛生コンサルタント」で調べるよりも数多く有益な情報に接触できる機会が増えます。
<健康管理(保健衛生区分)>
「健康管理」は、専門科目で記述形式の問題となりますので、これまでのようなマークシート方式の問題に対する勉強法では対応しにくい部分もあります。
もちろん、過去問もありますが、それだけを繰り返しやっていてもあまり効果的ではないでしょう。
しかも明確な答えが存在しないので、「解説」などの第三者による説明が非常に重要となります。
したがって、『まずはこれ!!労働衛生コンサルタント筆記試験対策問題集』などの問題集や参考書の購入は欠かせないところです。
<労働衛生工学(労働衛生工学区分)>
「労働衛生工学」も記述形式の問題となっています。
広い範囲で出題されるので対策しづらい印象もありますが、「騒音」や「振動」、「ハザード」といったキーワードを見出すこともできるので、その周辺の知識について確認するなどの準備が必要になります。
労働衛生コンサルタント受験生の必読書との呼び声もある『新やさしい局排設計教室』など、重要な書籍も存在します。

◎記述式問題について
記述式という問題形式に対する対策にも注意してください。それは時間です。
専門科目による記述式の問題は、「2問」となっていますが、実際は4つある設問のなかから2つを選択する形です。もっと詳しくいえば、問1と問2からどちらか1問、問3と問4のどちらから1門を選ぶようになっています。
問題の内容を理解し、それぞれどちらを選ぶかである程度、時間がかかります。さらに、計算を必要とする問題も存在しますので、時間配分は重要な要素となります。
記述式の試験時間は2時間取られていますが、1問で1時間くらいかかることもざらにありますので注意してください。
時間配分については、過去問で慣れるしかない部分もありますので、しっかり時間を図りながら問題を解いていく練習を行うと良いでしょう。
■口述試験対策

これまで紹介してきた労働衛生コンサルタント試験の内容は、いわば一次試験です。
上記の筆記試験に合格すると、次の「口述試験」に進むことができます。口述試験は、筆記試験と同じ区分に応じた試験科目が用意されています。
「保健衛生」は、「労働衛生一般」と「健康管理」の科目があり、「労働衛生工学」では、「労働衛生一般」と「労働衛生工学」の科目があります。どちらも範囲は筆記試験と同様です。
筆記試験の合格発表が12月上旬に行われ、合格者は翌年の1月に口述試験を受けるスケジュールとなっていますが、ここで注意すべきポイントがあります。
それは合格発表から口述試験までの期間がそれほど空いていないことです。つまり、合格発表を待ってから口述試験の準備をはじめても遅いことを覚えておいてください。
筆記試験が終わってすぐインターネットで解答予想を確認できますので、自己採点をし、合格の可能性が高いようなら記述試験の準備に入りましょう。
さて、肝心の口述試験勉強法ですが、口述試験における質問内容は確認できるものに公式の資料はありません。
自分で調べたり、関連書籍を購入したりといった対応が必要となります。そういった資料から質問の傾向を模索し、「想定問題」を作成することが一般的な勉強法です。
しかし、これだとかなりオリジナリティの高い対応となり、一か八かのヤマカン的な勉強となってしまうおそれもあります。そこで、「講習会」や「セミナー」などに参加する方法も選択肢のひとつとして考えてはいかがでしょうか。
合格者が激推しする講習会などが存在します。独学ばかりに頼るのではなく、客観的で効果を期待できる手段を活用すれば一発合格の可能性を高めることにつながります。
■「投資」も重要

資格を取得するためには、ある程度の投資も必要です。特に合格率の低い難関といわれる「労働衛生コンサルタント」に効率よく合格するためには、講座や講習の受講などは欠かせないところとなるのではないでしょうか。
現在では、どこかに出向いてリアルタイムで受講しなくとも、オンラインで好きな時間に勉強できるような環境も充実していますので、時間の有効活用としての相乗効果も期待できます。
ただ、講習などの受講を考えるにしても、思いつきでむやみやたらと申し込めば良いというものでもありませんので、試験までのスケジュールを逆算したりと効果のあるタイミングややり方を考える必要があります。
■経験者・合格者の“生きた”情報

労働衛生コンサルタントの試験について、その勉強法や試験対策を考えるうえで、参考になるのが実際に試験を受けた方や合格した方の話だと思います。
インターネットで検索すれば、数多くの事例にあたれますので、ご自身の性格や感性にあった「先輩」のメソッドやアプローチをうまく取り入れ、ディティールは自分好みにカスタマイズしながら試験合格を目指してください。
また、勉強法だけでなく、モチベーションの保ち方や力の抜き方など、長期にわたる受験勉強において参考になる情報がたくさんあるはずです。
「継続は力なり」。試験勉強において、これ以上の説得力のある必勝法はないでしょう。最後まで続けられるやり方で難関試験にチャレンジしてください。
■まとめ

「労働衛生コンサルタント」は、厚生労働大臣指定登録機関の登録を受けた国家資格であり、その試験は合格率が30%ほどという難関なものとなっています。
試験は1年に1回で、筆記試験と口述試験の2段階があります。筆記試験は2つの区分がある全3科目で、トータル60%の正答率を得られれば合格となります。ただ、1つの科目でも正答率が40%を下回ると不合格です。
所有している資格や歩んでいるキャリアによって筆記試験が免除される場合もありますので、受験資格の確認は重要です。
難しい試験ですので、対策や戦略を立てて臨む必要があります。ただ、試験の勉強自体はオーソドックスな内容で、過去に出題された問題を繰り返したり、そこで必要となる専門的な知識について、細部まで掘り下げていくものになります。
また、独学では限界となる場合もありますので、講習などに投資したり、経験者の意見を考慮するなど、柔軟に対応しながら勉強を進めていきましょう。
地道にコツコツと。これが一発合格への最善の方法であり、唯一の道かもしれません。
とはいえ、本記事で紹介したようなディティールについて検討していただければ、少しでも合格の可能性を高めることにつながるのではないでしょうか。この記事を参考に「労働衛生コンサルタント」を目指してください。