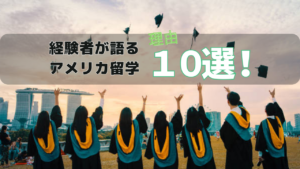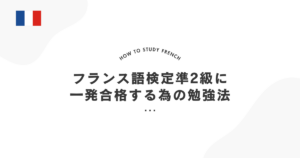【今こそ知っておきたい】ジェンダーレスとLGBTについて

昨今、耳にするようになった「ジェンダー」や「LGBT」といった言葉の本当の意味を説明できますでしょうか。
この記事では、「ジェンダー」や性のあり方について具体的に細かく解説していきます。
【今こそ知っておきたい】ジェンダーとLGBTのコト

ここ数年で一気に市民権を得てきた言葉に「ジェンダー」や「LGBT」があると思います。
昨年には「LGBT理解推進法」が成立したり、同性パートナーシップ同名制度を実施する自治体が増加したりなど、かなり注目のトピックになっています。
しかし、「言葉は聞いたことがあるけど」「社内で関連の講習を受けたけど」あまりピンとこない、人に説明できないという人も多いのではないのでしょうか。
この記事では、そのようなモヤモヤとした「わからない」という理解を解消するべく「ジェンダー」や「LGBT」の基礎基本について徹底的に解説していきます。
ぜひ最後まで読んで「人に説明できる」ことを目指しましょう。
そもそも「ジェンダー」って何?

それではここでいきなり2つのトピックのうちのひとつである「ジェンダー」について詳しく見ていきたいと思います。
この記事を読んでいる方の中には「ジェンダーって”性別”の最近の言い換えなんでしょ?」くらいに思っている人も多いと思います。
しかし、細かく見ていくと全くそんなことはありません。それでは、一体何が違うのか、解説していきます。
「ジェンダー」とは社会や文化によって作られた性別

見出しにある通り「社会や文化によって作られた」と言われてもすんなりと腑に落ちる人は少ないと思います。
では、どういうことか。実例を交えながら解説していきます。
例えば、「女性は結婚したら家庭に入るべきだ」「男は家族のために大黒柱となって働くべきだ」といった、”昭和的”な価値観から、今でも多い「赤いランドセルは女の子、青や黒は男の子」といった、世の中の慣習にしたがって、男女の役割が定着していっているのです。
これらに限らず、さまざまな側面で「男性らしさ」「女性らしさ」が求められるのが現代社会の構造になっています。
女子高校生がスカートを履きたくなくてパンツスタイルで登校するというのも一例かもしれません。
このように半ば無意識に「男性/女性らしさ」が刷り込まれ、出来上がった性別を「ジェンダー」というのです。
一方、身体的・生物学的な性別を聞かれる場合は「セックス」と呼び、「ジェンダー」とは違う考え方のもとに成り立っているので区別しておきましょう。
ちなみに、国連組織であるUN WOMANによると「ジェンダーとは、男性・女性であることに基づき定められた社会的属性や機会、女性と男性、女児と男児の間における関係性、さらに女性間、男性間における相互関係を意味」するものと定義されています。
日本のジェンダーギャップ指数は?

またニュースなどで「ジェンダーギャップ指数」という言葉を耳にした人も多いかもしれません。
ジェンダーギャップ指数とは、男性に対する女性の経済進出、労働参画や教育、健康などの比率を示したものです。
この指数が低いことが毎年報道されていますが、直近だと内閣府男女共同参画局の報告によると2024年6月時点で、日本は118位(146カ国中)という順位になっているのが現状です。
教育と健康の側面では、世界でもトップクラスに充実しているのですが、経済参画と政治参画において、他の先進国を大きく下回る結果となってしまっています。
実際、日本の女性議員の比率は2023年時点で約16.0%となっており、まだまだ男性社会が根付いているのが事実です。
一方で、ジェンダーギャップ指数のランキングが1位のアイスランドは2023年時点で47.6%を占めています。
女性の意見をより国の施策に反映させるためにも、政治への参画が活発になることは今後の日本の課題となるでしょう。
「ジェンダー」を構成する性の4要素

ここまで、「ジェンダー」という言葉について、そして日本における男女の現状について見てきました。
それでは一体自分の「ジェンダー」をどのように捉えれば良いのか、「性のあり方」を考えるうえで重要となってくる4つの要素について紹介していきます。
それぞれの考え方をしっかりと理解し、下記の要素をもとに自分の「性のあり方」について改めて考えてみるのも面白いでしょう。
性的指向

1つ目は「性的指向」です。
聞いたことがある人もいるかもしれませんが、簡潔に言えば「性的指向」とは「どのような性別の人に魅力を感じるか」を示す言葉です。
例えば、「自分は男性に恋愛感情を抱く」と感じた場合は、その人の「性的指向」は「男性」ということになります。
また、性的指向に合わせて、自分と異なる性別を好きになることを「異性愛」、同性を好きになることを「同性愛」、そして両方の性別を好きになることを「両性愛」と区別することもあります。
はっきりと性別を「男性/女性」と二分するのは難しいですが、自分がどのような性別の人に惹かれるのか、考えるきっかけになるでしょう。
性自認

2つ目は「性自認」です。
この言葉も、近年では話題に上がりやすくなっているため、聞いたことがある人も多いかもしれません。
「性自認」とは「自分の性別を何だと思っているか(自認しているか)」を指す言葉です。
その人が「私は女性だ」と認識していれば、身体的な性別が男性であっても、「女性」として生きたいと思う人も多いです。
このように、身体的・生物学的な性と性自認が一致しない人を「トランスジェンダー」と呼びます。「トランスジェンダー」については詳しく後述します。
「自分の性別にモヤモヤしていたけど、このモヤモヤに名前はついているのだろうか」と、さまざまなセクシュアリティについて調べてみるのも良いかもしれませんね。
性表現

3つ目は「性表現」です。
これは「自分がどのような性別の表現をするのか」という意味です。前述した、女子高生がスカートではなくパンツスタイルを選ぶのに少し近いイメージかもしれません。
もっと具体的に言えばマツコ・デラックスさんのような、「オネエタレント」と呼ばれる芸能人は、男性ではありますが、言葉遣いや服装、振る舞いは女性的です。
このような人たちは「女性的な性表現」をしているということができます。
他にも「ドラァグクイーン」といった、誇張した女性表現をすることを仕事にしている男性もいます。
身体の性

4つ目は「身体の性」です。
これが最もイメージしやすいかと思いますが、改めて説明すると、「その人の身体的特徴が生物学的に男性的であるか、女性的であるか」を指しています。
多くの場合、赤ちゃんの性別診断のときのように、生殖器によって判断されることが多いです。
もちろん、この「身体の性」にも例外はあり、男性と女性の両方の特徴を持って生まれる人もいるでしょう。
これら4つの要素で「性のあり方」は決まる

一概にとは言い切れませんが、基本的には上記で紹介した4つの要素から、自分のジェンダーを推定することができます。
例えば、「性的指向は男性」「性自認は男性」「性表現は女性」「身体の性は女性」といったパターンの人もいることでしょう。
ちなみにこの場合は「男性トランスジェンダーの異性愛者」と名前をつけることができます。
このように、4つの要素から選択してくだけでも膨大な性のあり方が存在しますが、それだけではすべてを表しきれません。
そのようなすべての「性的マイノリティ」を総称して、下記で触れる「LGBT」という言葉が使われるのです。
「LGBT」とは

では、「ジェンダー」とともに話題になっている表現である「LGBT」はどのような言葉なのか見ていきましょう。
「LGBT」はよく「性的マイノリティ」を総称する言葉として使われますが、もともとは「L・G・B・T」の4つの性のあり方をまとめたものに過ぎず、無数にある性のあり方を全て包括しているわけではありません。
なので、無闇に「あなたって”LGBT”なんだよね?」などと詮索しないことが推奨されます。
以下で、「L・G・B・T」がどんな性のあり方を指すのか、そして、それ以外の性も含めた「性的マイノリティ」を表す言葉はあるのかについて紹介していきます。
L(レズビアン)について

まずは「LGBT」の先頭にある「L(レズビアン)」についてです。
「レズビアン」は前述した「性の4要素」で説明すると、「性的指向が女性」「性自認が女性」の「同性愛者」の人を指します。
「性表現」や「身体的性」はここではあまり重視しません。なぜなら、「男性的な性表現」をしている人や、「身体の性は男性だが、性自認は女性」といった人もいるからです。
また、よく使われる「レズ」という略称は差別的な表現になり得るので、相手から使ってこない限りは使用を控え、「レズビアン」「ビアン」と呼ぶことをおすすめします。
G(ゲイ)について

続いて2つ目の「G(ゲイ)」についてです。
性のあり方の考え方はレズビアンと似ていて、「性自認が男性」「性的指向が男性」の「同性愛者」の人を指します。
レズビアン同様、使用を控えた方が良い表現として「ホモ」があり、差別的な意味を含むので注意しましょう。
また、TVなどで活躍している「オネエタレント」のように、全てのゲイが女性的な振る舞いをするわけではないことも頭に入れておくと、相手を傷つけることなく接することができます。
B(バイセクシュアル)について

3つ目は「B(バイセクシュアル)」についてです。
レズビアンやゲイと少し考え方が異なり、バイセクシュアルの場合は、自身の「性自認」にかかわらず、「性的指向」が「男性と女性」両方に向けられる人のことを指します。
有名人をあげるとメイプル超合金のカズレーザーさんがカミングアウトしていますね。
彼自身は「性表現」はどちらかといえば「男性的」ですし、「身体の性」も男性ですが、男性に惹かれることもあれば、女性に惹かれることもあるようです。
T(トランスジェンダー)について

最後に4つ目は「T(トランスジェンダー)」についてです。
これは主に「性自認」に関わる性のあり方で、自分の「身体の性」と「性自認」が一致していない人のことを指します。
例えば、「身体の性」が「女性」で生まれた人が「男性」の「性自認」を抱えている場合、「トランスジェンダー男性」と言います。(「トランスジェンダー」の後ろにつく性別は性自認の性別になります)
また、「性自認」に合わせて身体の手術を行うことを「性別適合手術」と言いますが、これは「本来の性別(性自認)に身体の性を合わせる」という意味になります。
なお「性同一性障害」は「性別適合手術」の診断のためのみ使用される表現なので、無闇にトランスジェンダーの人に使用するのは控えましょう。
その他の性のあり方

ここまで「LGBT」の4つの性について紹介してきました。
今でこそ「LGBT」は「性的マイノリティ」の総称として使われることも多く、「LGBT理解推進法」などで登場します。
しかし、前述した通り、本来「LGBT」は4つの性しか著しておらず、性のあり方は無限です。ここでは「LGBT」以外にどのような性のあり方があるのか、いくつかピックアップして紹介していきます。
まず1つ目が「Q(クエスチョニング)」です。これは「自分の性的指向や性自認が定まらない人のこと」を指す言葉で、よく「LGBTQ」や「LGBTQ+」と表現されることがあります。
特に「LGBTQ+」は「+」とつくため、「LGBTQ」以外の全ての性を包括した表現として使われます。
他にも「アロマンティック」や「アセクシュアル」などがあります。「アロマンティック」は、「他人に恋愛的な感情を抱かない人」を指し、「アセクシュアル」は「他人に性的な魅力を感じない人」を指します。
つまり、「レズビアンで、かつアセクシュアル」な人も存在することになります。
これらはほんの一例ですが、性のあり方は人の数だけあるといってもよく、マジョリティである「一般的な男性/女性」も数ある性の中のひとつに過ぎないということです。
まとめ:改めて性のあり方について考えてみよう

ジェンダーに関するさまざまな考え方やあり方について紹介してきましたが、これらを踏まえてもう一度「自分はどんな指向を持っているんだろう」「どんな振る舞いをしたいのだろう」といったことを考えてみるのも面白いかもしれません。
そうすることで、たとえマジョリティであったとしても、「自分は多くの属性のひとつに過ぎないのか」と思うことになるでしょう。
また、性のあり方について他人に詮索をすることは絶対に避けましょう。
相手にとっては隠したいことかもしれませんし、仮にカミングアウトしてくれたとしても、それを広められてしまうと嫌な思いをするでしょう。
ナイーブな問題ですので、しっかりと知識として頭に入れておき、ジェンダーギャップやLGBTに関することに少しでも貢献できるように心がけるのが良いかもしれませんね。