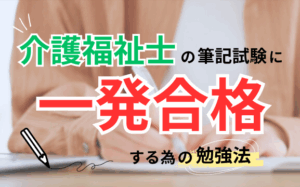【他にはない別格の味わい】高級魚・甘鯛の魅力と調理法を徹底解説!
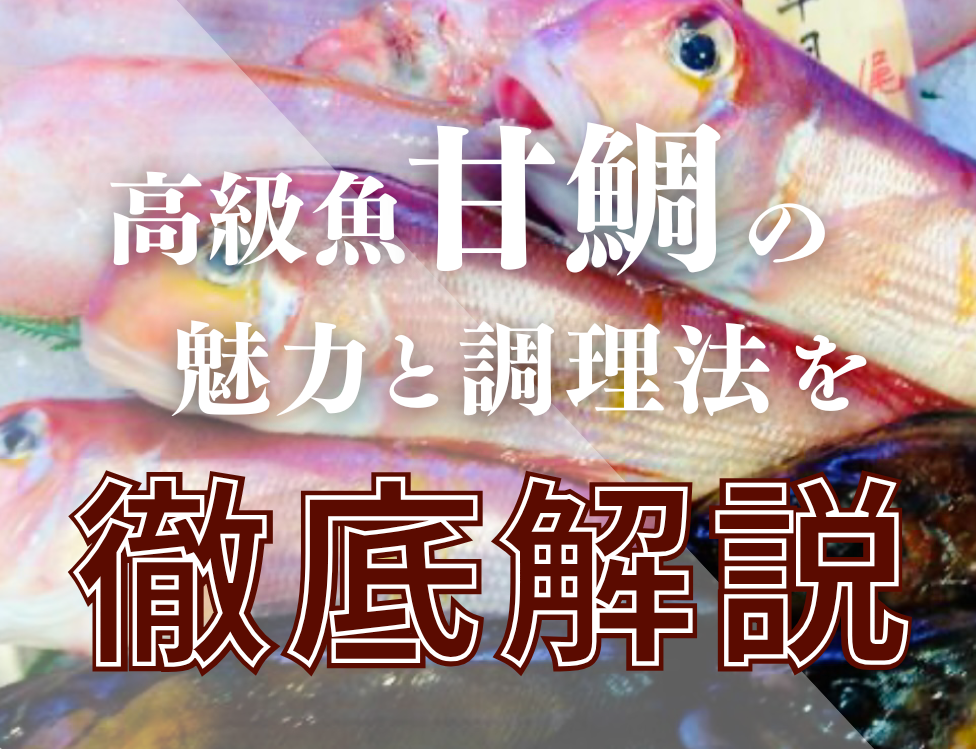
高級魚として料亭などで提供されることの多い甘鯛。
地域や漁獲の時期によっては、一般のスーパーでも見かけることがあります。
釣りをする方や魚に詳しい方にはよく知られた存在ですが、そうでない方にとっては「甘鯛とはどのような魚か」と聞かれても、すぐに答えるのは難しいかもしれません。
今回は、甘鯛の基本的な特徴や種類ごとの違いから、家庭でも楽しめる調理法やおすすめの食べ方まで、甘鯛の魅力をわかりやすくご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
甘鯛とはどんな魚?

「甘鯛(アマダイ)」という名前には「鯛」という漢字がついていますが、実際にはタイ科(Sparidae)には属していません。
「真鯛(マダイ)」などの“本当の鯛”はタイ科ですが、甘鯛は「キツネアマダイ科(Branchiostegidae)」という独自のグループに分類されます。
それでは、なぜ「鯛」という名前がついているのでしょうか。ここでは、甘鯛の名前の由来や生態について、わかりやすくご紹介します。
甘鯛の名前の由来
甘鯛という名前にはいくつかの説がありますが、一般的なのは、その上品な味わいに由来するというものです。砂糖のような甘さではなく、淡白で柔らかく、ほんのり甘みを感じる旨味から「甘鯛」と呼ばれるようになったとされます。
「甘(あま)」という言葉には、古くから「美味しい」「好ましい」といった意味があり、そこから、柔らかく上品な味わいというイメージが重ねられたとも考えられています。
昔の日本では「甘い=美味しい」という感覚が強かったことから「甘鯛=美味な鯛」というニュアンスも込められていたのでしょう。
また、見た目が似ていて味もよいため「○○ダイ」と名のつく、いわゆる“通称鯛”のひとつとして扱われています。なお、かつてはキンメダイ科に分類されていたこともありましたが、現在は独立したグループとして整理されています。
甘鯛の生態と特徴
甘鯛は、日本を含む温暖な海域に広く生息し、主に水深30〜200メートルの砂泥底でよくみられます。
昼間は海底でエサを探し、夜間には砂に潜って休む習性がある魚です。食性はゴカイや小型の甲殻類などの底生生物が中心で、口が下向きについているため、砂ごと吸い込んでエサを探すという独特の捕食スタイルが特徴です。
体型は細長く、側扁(そくへん)した形状で、うろこは非常に細かく剥がれやすいため、調理のさいには扱いづらい魚とされています。
しかし、その薄いうろこを活かした「松笠焼き(別名:うろこ焼き)」など、香ばしさを楽しむ調理法も人気です。
もしかすると、みなさんも一度は耳にしたことがあるかもしれません。甘鯛の簡単な調理方法はのちほどご紹介いたします。
さらに、甘鯛は「雌性先熟(しせいせんじゅく)」という特性を持っているため、最初は雌として成長し、後に雄に性転換することがあります。
自然界全体で見れば、こうした性転換はさほど珍しい現象ではありません。高級魚として扱われる理由のひとつには、その生態も関係しています。
甘鯛の寿命はおおよそ5〜7年程度で、成魚になるまでに時間がかかるため、過剰な漁獲によって資源が減少しやすい傾向にあります。
甘鯛の種類

甘鯛には「白甘鯛」「赤甘鯛」「黄甘鯛」の3種類があり、それぞれに味、見た目、価格、流通量などに特徴があります。以下で詳しく見ていきましょう。
白甘鯛(シロアマダイ)

・特徴:もっとも高級とされる甘鯛で「白川(シラカワ)」や「本アマダイ」といった名称でも知られています。味わい、見た目、価格のすべてにおいて最高ランクに位置づけられ、とくに料亭などの高級料理店で重宝される存在です。
・見た目:淡い白色から薄桃色で、全体に上品な印象。目は大きく、透明感があります。
・サイズ:全長30〜40cm前後、最大で50cmを超えることもあります。
・旬:晩秋〜冬(10月〜2月)。この時期は通常より脂がのっており、味の良さも最盛期です。
・漁法と流通:一本釣りが主流で、底引き網では身が崩れやすいため、手間がかかるが丁寧な一本釣りで獲られます。流通量が少なく、鮮度のよい状態で市場に出ることが多いため、高値で取引されます。
・食べ方:刺身、昆布締め、塩焼き、酒蒸し、椀物など、素材の味を活かした調理法に向きます。うろこごと焼く「松笠焼き」でも人気です。
赤甘鯛(アカアマダイ)

・特徴:もっとも一般的な甘鯛で、スーパーや鮮魚店などで目にする機会も多い種類です。味と値段のバランスがよく、幅広い調理法に向いています。
・見た目:赤〜朱色の体に、青白い縦線が体側に見られます。非常に目立つ体色で、もっとも一般的な見た目です。
・サイズ:成魚で全長約30〜40cm程度、最大で50cmほどになることもあります。市場で流通しているのは25〜35cmほどが主流です。
・旬:晩秋〜冬(11月〜2月)がもっとも美味とされ、とくに産卵後の時期は脂がよくのっています。
・漁法と流通:一本釣り、底引き網、延縄、刺し網などで漁獲されます。水揚げ量が多く、全国の市場やスーパーに広く流通しています。
・食べ方:煮付け、焼き物、揚げ物などで人気があります。鮮度の高いものは、刺身でも美味しくいただけます。
黄甘鯛(キアマダイ)

・特徴:市場に出回ることは少なく、やや地味な印象のある種類です。価格は安価ですが、一方で、味や質では評価が分かれる魚です。
・見た目:黄色がかった体色で、他のアマダイよりもややくすんだ印象があります。体側の縦線は不明瞭で、全体として地味な見た目です。
・サイズ:成魚でもやや小柄で、全長20〜30cm程度です。
・旬:明確な旬はありませんが、他のアマダイ同様、寒い時期(冬)にやや味がよくなる傾向があります。
・漁法と流通:底引き網での混獲が多く、他の魚を狙った漁で偶然に獲れることが一般的です。流通量もかなり限定的になるでしょう。
・食べ方:味は他のアマダイに比べると淡白で、やや水っぽい食感があるため、料理人の間では扱いにくい魚とされることもあります。脂が少なくさっぱりしているため、淡白な味わいを活かす蒸し物や酒蒸しなどには向いています。
水揚げ量で見ると、赤甘鯛 > 白甘鯛 > 黄甘鯛といった順番になります。
一般的には「水揚げ量が少ない=希少性が高く高級」と考えられがちですが、甘鯛の場合は少し事情が異なります。
実は、もっとも高値で取引されるのは白甘鯛。一方、水揚げ量が少ないにもかかわらず、安価なのが黄甘鯛です。
その理由は、黄甘鯛が、水っぽく脂が少ないとされ、味や質の面で他の甘鯛に劣ると評価されているからです。
このように、甘鯛は水揚げ量と価格が必ずしも比例せず、味や質によって価値が大きく左右される魚になります。
甘鯛の選び方と見分け方

せっかくなら、スーパーや魚市場では新鮮で美味しい甘鯛を選びたいものです。ここでは、鮮度を見分けるためのポイントや選び方のコツを紹介します。
鮮度のよい甘鯛の特徴
鮮度のよい甘鯛は、目が澄んでいて、光沢があり、身にハリがあります。全体的にみずみずしさがあり、臭みがないものが理想です。また、表面を軽く指で押したとき、身に弾力があるかどうかも重要なポイントです。
色・目・ウロコに注目
新鮮さを見分ける上で確認したい項目がいくつかあります。
まず、体色が鮮やかで色あせていないか、目が黒く澄んでいるかをチェックしましょう。
つぎに、うろこがしっかりとついているかどうかも確認してみてください
とくに注目すべきは、目のクリアさと、うろこ表面のぬめりです。目がクリアで、うろこにぬめりがしっかりと残っているものほど、新鮮な状態といえます。
ぬめりは水揚げ直後に多く、時間が経つと落ちていくため、これが新鮮さの重要な指標になります。
甘鯛の捌き方と注意点

捌く前は、たわしを使って軽くこすり、うろこのぬめりを取ります。
一本釣りだと、口の中に釣り具が残っている場合があるので、頭がついているものを捌くときは、怪我をしないように気をつけましょう。
身は柔らかいですが、骨は硬くてしっかりしているので、頭を落とすさいは、骨のつなぎ目をピンポイントで狙う必要があります。
中骨も硬いため、三枚おろしは、包丁が浮かないように力を入れて切り離しましょう。
上身を捌くときは、一気に切るのではなく、肋骨を一つひとつ押し切るように刃をいれると、綺麗に捌けます。非常に水分量の多い魚なので、洗いすぎは要注意です。
また、うろこの取り方には、主に以下の二種類があります。用途に合わせて使い分けましょう。
▼うろこのすき引き
「すき引き」は、魚のうろこを薄く削ぎ取る技術です。通常、うろこは魚の表面にしっかりと付いているため、すき引きで削ぐことにより、魚の身を傷つけずにうろこを取り除きます。
包丁やうろこ引き器を使って、表面のうろこを薄く取る作業です。甘鯛の場合、赤い部分が取れて白い部分しか見えなくなりますが、うろこが少なく、刺身などのお造りに向いています。
▼うろこのばら引き
「ばら引き」は、魚のうろこを広範囲に無駄なく取り除く技術です。魚の体に対して一度に広範囲にわたってうろこを取る方法で、うろこが全体的にばらけるように処理されます。
一般的に、すき引きよりもなじみのある取り方です。最近では、うろこ取り専用の調理器具が多く販売されており、安価でも手に入りやすくなりました。
すき引きと比較すると、身にダメージがかかってしまいますが、表面の赤い部分は綺麗に残るため、煮物などの料理に適しています。
ばら引きだと、多少うろこが残りやすいので、そのさいは抜きなどで取り除きましょう。また、腹部分は皮が薄いので、身崩れしないように注意するのもポイントです。
甘鯛の栄養価

甘鯛は脂肪分が少なく、上品な味わいが魅力の白身魚です。高たんぱく・低脂肪・低カロリーで栄養バランスにも優れており、健康志向の方やダイエット中の方、食事制限のある方にも適しています。
また、消化が良く胃にやさしいため、子どもや高齢者にも食べやすいのが特徴です。
甘鯛に含まれる栄養素には、体調管理や美容をサポートする成分が豊富に含まれており、免疫力の向上やアンチエイジング効果も期待できます。高脂肪食に偏りがちな現代の食生活において、栄養のバランスを整えるための心強い一品です。
▼主な栄養成分(100gあたり)
・エネルギー:97kcal → 低カロリーで、ダイエット中でも取り入れやすい。
・たんぱく質:18.3g → 筋肉や皮膚、免疫機能の維持に欠かせない良質なたんぱく質。
・脂質:2.3g → 脂肪分が少なく、あっさりとした味わい。消化にも優しい。
・ビタミンD:4.0μg → カルシウムの吸収を促進し、骨の健康をサポート。
・ビタミンB12:2.4μg → 赤血球の生成や神経機能の正常化に関与。
・セレン:42μg → 抗酸化作用を持ち、細胞の老化や免疫低下を防ぐ。
なお、上記は、甘鯛100gあたりの主な栄養成分(出典:文部科学省「日本食品標準成分表」)を参考にしたものです。
甘鯛の美味しい食べ方

甘鯛ならではの美味しい食べ方や、自宅でもできる簡単なレシピをいくつか紹介します。
柚庵焼き
柚庵焼きは、魚や肉を柚子の風味が加わった漬けダレに漬け込んで焼く、伝統的な日本の調理法です。漬けダレには、醤油・酒・みりんを同量で混ぜた「柚庵地(ゆあんじ)」に、柚子の絞り汁や皮を加えます。この柚庵地に漬け込んで焼くと、甘辛さと爽やかな香りがよく染み込みます。表面にうっすらタレが残る程度に焼くのがポイントです。
①タレ作り:醤油・酒・みりんを、1:1:1の割合でつくる。柚子などの柑橘系を入れる。
②漬け込み:30分〜1時間程度、柚庵地にしっかり漬け込む。
③焼き上げ:余分なタレを軽く落としてから、オーブンなどで焼く。
焼くときには金串を使うと身崩れしにくく、美しく仕上がります。魚のねっとり感を保ちながら、タレの風味がしっかり染みた状態が理想です。
また、同じ読み方として「柚庵焼き」のほかに「幽庵焼き」があり、以下の違いがあります。
・幽庵焼き → 柚庵地のみで、柑橘類は加えない。
・柚庵焼き → 柚庵地に加え、柚子、すだち、かぼすなどの柑橘類が入る。
若狭焼き
若狭焼きは、味噌や醤油のタレに漬けた魚を網焼きする伝統的な調理法です。とくに有名なのは鯖ですが、甘鯛でもよく使われます。タレに漬け込むことで、香ばしくコクのある風味が引き出されます。
【調理方法】
①タレ作り:醤油、みりん、酒、砂糖、時には味噌を混ぜたタレを作る。
②漬け込み:甘鯛にタレをしっかりと染み込ませる。
③焼き上げ:タレを染み込ませた甘鯛をオーブンで焼く。焼き目をつけた後、再度タレを塗りながら焼く場合もある。
▼「若狭くじ」と「若狭焼き」の違い
「若狭焼き」とよく混同される言葉に「若狭くじ」があります。名前は似ていますが、まったく異なる意味を持つ料理や食材です。「若狭くじ」とは、若狭湾(福井県)周辺で獲れる甘鯛のことを指します。この地域で獲れる甘鯛は非常に質が高く、食文化の一部として有名です。
漁業が盛んな若狭湾では、新鮮で美味しい魚が豊富に獲れるため「若狭くじ」と呼ばれ、高級な魚として珍重されています。脂がのっており、しっとりとした食感が特徴的です。
・若狭くじ:若狭湾で獲れる甘鯛。
・若狭焼き:若狭地方特有の焼き物調理法。
松笠揚げ

松笠揚げは、魚のうろこをそのまま残し、うろこごと揚げる料理です。うろこ部分が松ぼっくりのように立ち上がることから「松笠」という名前がついています。
【調理方法】
①下準備:切り身にした甘鯛は、うろこの部分には何もつけず、身にだけ片栗粉をまぶす。
②揚げる[前半]:皮目を上にして網の上にのせる。お玉で熱した油をかけながら、じっくり火を入れる。
③揚げる[後半]:身の8割ほど火が通ったら、残りの反対側を油に落として唐揚げのように仕上げる。
カラッとした仕上がりにするため、油の温度は180度が理想です。オーブンで焦げ目をつけけ焼きあげると、松笠焼きとして仕上がります。
なお、2〜3日経過して鮮度が落ちた甘鯛は、うろこが立たなくなりますが、表面を水で濡らすことで再びうろこが立ちます。
酒蒸し
甘鯛の酒蒸しは、酒の蒸気を利用してふっくらと蒸し上げる日本料理のひとつです。上品で淡白な甘鯛の旨みを引き立てる、素材の良さが際立つ調理法として知られています。
酒の力で臭みを取り除きつつ、しっとりとした食感に仕上がるのが特徴で、シンプルながら料亭でも提供されるほどの上質な一品です。
【調理方法】
①下処理:甘鯛に軽く塩をふり、10分ほどおいて余分な水分を出し、キッチンペーパーで拭き取る。臭みが気になる場合は霜降り(熱湯をかけて氷水で締める)をする。
②冷たいフライパンに甘鯛をいれ、日本酒をかけ回す。料理酒可。
②蒸す:鍋や蒸し器に昆布を敷いて、甘鯛をのせ、酒をふりかける。10〜15分ほど、甘鯛の厚みによって調整しながら蒸す。中火→弱火。
③仕上げ:蒸しあがったら、煮汁だけ取り除き、汁気がなくなるまで煮詰めてかける。刻んだ柚子の皮や、千切りの生姜をのせると、より香りが引き立つ。
昆布締め
甘鯛と昆布締めの相性は非常に高く、おつまみとしても最適です。白身魚の中でもとくに上品で繊細な甘みがあり、昆布のうまみ成分が加わることで、全体の味がまろやかに広がり、より深みが出ます。
①下処理
・甘鯛を三枚おろしにし、腹身と背身に分ける。
・血合い骨の部分は切り取り、皮を丁寧に引く。
・両面に軽く塩をふり、10〜15分ほど置いて余分な水分を出す。
その後、キッチンペーパーで水分をふき取る。
(腹側の銀皮はなるべく残すと、仕上がりが綺麗に)
②昆布の準備
昆布は、酒と酢をほんの少量加えた布巾で湿らせて戻す。
(戻しすぎると魚の水分を吸いづらくなるため、昆布の表面が少し乾いている程度がベスト)
③締める
甘鯛の身を昆布で挟み、サランラップできっちり包む。
(空気が入らないようにしっかりと密封)
④寝かせる
冷蔵庫で最低3時間、理想は1~2日ほど寝かせる。
時間をかけることで、ねっとりとした旨味が身にしみ込む。
⑤仕上げ
昆布から取り出したら、ぬめりが気になる場合は軽くペーパーでふき取る。
そのまま薄く切って、お造りやおつまみに。

刺身で食べる場合は、皮目だけを軽く炙ってお造りにすると、脂がのって美味しくいただけます。
とくに扱いが難しい白甘鯛は、アラから上品な出汁が取れるため、潮汁や味噌汁にぴったりです。
血合いを丁寧に洗い落としたアラを冷凍保存しておけば、必要なときに手軽に出汁を取れます。
取った出汁は、炊き込みご飯や味噌汁に使えるのはもちろん、醤油と合わせて魚介系ラーメンのスープとしても活用できます。
捌くのが苦手な方や、手間をかけたくない方は、塩焼きや煮付けでシンプルに楽しむのもおすすめです。
開きにして干物にすれば保存性も高まり、焼いたときには香ばしさと旨味がいっそう引き立ちます。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は、甘鯛につて、名前の由来や生態、鮮度を見分けるコツ、捌き方まで、さまざまな視点から魅力をお伝えしてきました。
種類によってもそれぞれ個性があるため、調理法を変えて楽しむのもよいでしょう。高級魚といわれるだけあって、味わいは格別。スーパーなどで見つけたときは、ぜひ手にとってみてください。
また、栄養面でも大変優れており、健康維持を意識した食事にもぴったりの食材です。