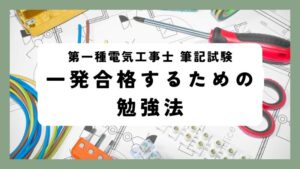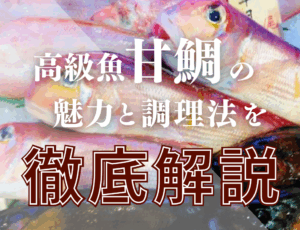【国家資格】介護福祉士の筆記試験に一発合格する為の勉強法
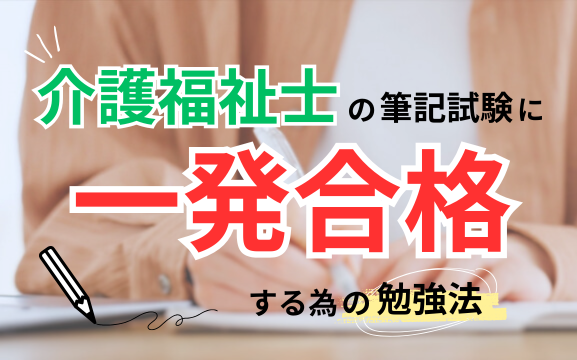
2026年1月に実施される第38回試験から、介護福祉士の国家試験に「パート合格制度」が導入されることをご存じでしょうか。
この制度では、試験が3つのパートに分かれ、それぞれのパートごとに合否が判定されます。
合格したパートの成績は2年間有効となり、次回以降の試験でそのパートを再度受験する必要はありません。
つまり、一度の試験ですべてのパートに合格できなかった場合でも、合格したパートの成績は持ち越すことができ、最長で3年かけて資格取得を目指せるようになりました。
簡単に言えば、これまでよりも介護福祉士の国家資格を取得しやすくなったということです。
とはいえ、一度の試験ですべてのパートに合格する「一発合格」が理想的であることは、言うまでもありません。実際、一発合格には、それに見合うだけの多くのメリットがあります。
では、介護福祉士の筆記試験に一発合格するためには、どのような勉強法が効果的なのでしょうか。
今回は、介護福祉士国家試験の筆記試験で一発合格を目指す方に向けて、目的や状況に応じた勉強法を詳しく解説します。
試験をこれから目指す方はもちろん「覚えることが多すぎて対策が立てられない」「苦手科目に手がつかない」と悩んでいる方も、ぜひ参考にしてください。
介護福祉士筆記試験一発合格のメリット

冒頭でもお伝えしたとおり、2026年第38回試験からパート合格制度が導入さるため、不合格となったパートについては再受験が可能になります。猶予が与えられた分、試験の難易度が下がったと感じる方もいるかもしれません。
しかし、パート合格制度が導入されたからこそ、一発合格の価値はこれまで以上に評価されるでしょう。
法改正による新たな出題範囲の追加や、出題傾向の変化など、試験の内容は今後も変化していくため、より戦略的かつ効果的な学習方法が求められます。
一発合格を目指すことには、以下のようなメリットがあります。
▼現実的なメリット
・再受験のコスト削減
・試験準備の手間軽減
・就職や転職に有利
・給与や資格手当の向上
▼精神的なメリット
・自己肯定感と自信の向上
・精神的負担の軽減
・周囲からの評価や信頼の向上
すでに介護職員として働いている方にとっては、一発合格によって早期のキャリアアップや収入増が期待できます。
資格手当などが支給されることで、毎月の給与が大きく変わることも珍しくありません。
また、学生の場合は就職活動を有利に進められるのはもちろん、施設によっては介護福祉士の資格取得を採用条件としているところもあります。
そのため、国家試験に一度で合格しておくことは、就職活動の強みとしてだけでなく、職場からの信頼を得る上でも大きなアドバンテージになります。
また多くの学生は、実務経験がまだありません。だからこそ、国家資格を取得すること自体が大きな自信やモチベーションにもなります。
介護福祉士筆記試験の概要

試験内容についてはご存じの方も多いかと思いますが、出題傾向や出題パターンとあわせて、改めて整理してお伝えします。
パート別出題数と科目
介護福祉士の筆記試験は全125問で構成され、以下の3つのパートに分かれます。
【 Aパート(60問)】
人間の尊厳と自立(2問)
介護の基本(10問)
社会の理解(12問)
人間関係とコミュニケーション(4問)
コミュニケーション技術(6問)
生活支援技術(26問)
【 Bパート(45問)】
こころとからだのしくみ(12問)
発達と老化の理解(8問)
認知症の理解(10問)
障害の理解(10問)
医療的ケア(5問)
【 Cパート(20問)】
介護過程(8問)
総合問題(12問)
介護福祉士筆記試験の合格基準

介護福祉士筆記試験に合格するためには、つぎの三つの条件を満たす必要があります。
▼総得点60%以上の得点
試験全体で総得点60%以上を取ることが基本的な合格基準です。目安としては、全125問中、75点前後を目指す必要があります。
▼すべてのパートで得点があること
すべてのパートで0点がないことが求められます。各パート内で少なくとも1問以上は正解しなければいけません。
▼各パート内の科目群で1問以上正解すること
各パート内に含まれるすべての科目群に対して、1問以上の正解が必要です。これが合格のための最低ラインとなります。
なお、上記の合格基準は一発合格を前提にまとめたものです。
初回受験時は全パートを受験し、合否は総得点で判定されます。不合格の場合、次回以降は不合格だったパートのみを再受験が可能です。
一発合格を目指すさいには、改正前と同様、総得点で60%以上を取る必要があるため、全体を通してバランスよく得点しなければいけません。
特定の科目で極端に低い点を取ってしまうと、一発合格が難しくなってしまいます。
また、各分野で1問以上の正解が求められるため、得意な科目では確実に1問以上正解し、苦手な科目にも一定の対策をしておくことが重要です。
介護福祉士筆記試験の出題傾向

試験はすべて選択式ですが、なんとなく選ぶだけでは確実に得点できません。
出題傾向を把握し、的確に答えられるよう準備しておきましょう。また、科目ごとの対策については、このあと詳しくご紹介します。
得点を取りやすい科目
▼人間関係とコミュニケーション
出題数は少なめで、問われる内容にパターンがあり対策が立てやすい科目。
▼医療的ケア
覚えるべき範囲が比較的限定されており、ポイントを押さえれば得点しやすい科目。
▼人間の尊厳と自立
暗記中心の問題が多く、知識を確実に覚えていれば得点に結びつきやすい科目。
出題形式とパターン
▼絶対表現・相対表現
「必ず」「全て」「絶対に」「一切」などの強い断定表現を含む選択肢は、誤答である可能性が高い。
例:認知症のある人への対応では、常に現実的な説明をして納得させるようにする→×
解説:「常に」「納得させる」といった断定は過度であり、本人の状態によっては「納得」よりも「安心」を優先すべき。
▼似ているが異なる用語
意味が紛らわしい用語は、混同しやすいため、正確な意味の理解が必要。
例:バイタルサイン/ライフサイン、清拭/洗身、身体拘束/行動制限など
▼状況として不適切な選択肢
内容自体は正しく見えても、状況に即していない場合には不正解となる。場面設定をよく読み、最も適切な対応を選択する。
例:食事介助中に利用者がむせたため、すぐに医師を呼びに行った→×
解説:誤嚥時の初期対応は、姿勢の調整や吸引などが基本であり、すぐにその場を離れるのは不適切。
介護福祉士筆記試験の目的別勉強法

介護福祉士の筆記試験では、出題の特徴をよく理解し、傾向を踏まえたうえで、適切な対策が必要です。
以下の項目より、科目別の対策法や学習スタイルに応じた勉強法、さらに効率よく学習を進めるために役立つおすすめのテキストをご紹介します。
月別の勉強法
介護福祉士の国家試験は、科目数も出題範囲も広いため、何から手をつけるべきか分からないという声をよく耳にします。
勉強を始める前に、まずは試験日から逆算し、余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。
4〜5月(出題範囲の把握と教材選定)
目的:学習の土台を整える。
▶試験科目・出題傾向を確認し、全体像をつかむ
▶テキストや問題集、アプリなど、学習ツールを決定
▶自分の生活リズムに合った学習スタイルを確立する
6〜7月(基礎知識の習得)
目的:重要語句・概念の理解を深める。
▶各科目の基本事項をテキストで学習
▶専門用語や頻出テーマの整理
▶簡易なまとめノートや暗記カードを作成するのも有効
8〜9月(初期演習と弱点の可視化)
目的:苦手分野を見極め、修正する。
▶過去問・模擬問題を使い、アウトプットを開始
▶分野別に解き、得意・不得意を明確にする
▶間違えた箇所の復習と再整理を重点的に行う
10〜11月(得点力の強化)
目的:合格点を確保できる実力に引き上げる。
▶科目別の重点対策を実施
▶出題頻度の高い項目に集中
▶模試形式で実践力を養成
12〜1月(最終確認と本番対策)
目的:得点を安定させる状態で本番を迎える。
▶知識の再確認と最終チェック
▶時間配分を意識しながら過去問演習
▶直前期は新しい範囲には手を出さず、既習内容の定着に集中
Aパート(60問)

科目別にみる勉強法
各科目にはそれぞれ特有の出題傾向があります。
人によって苦手な科目は異なりますが、特徴を把握し、それに合った対策を講じることで、効率的な克服が期待されます。
ここでは、全13科目の特徴と対策をまとめました。
注目すべきポイントや、どこに意識を向けて学習を進めればよいのかを明確にしておきましょう。
人間の尊厳と自立
▶特徴:出題数・配点は少なめだが、介護の根幹に関わる重要な分野。抽象的な概念理解が求められる。
▶対策:福祉理念や介護の原則を自分の言葉で説明できるようにすること。状況に応じて「尊厳とは何か」を考える練習を重ね、介護過程やコミュニケーションと結びつけて学習する。
介護の基本
▶特徴:倫理・制度・基本姿勢など多岐にわたるが、中心となる考え方は一貫している。また、現場とのギャップに注意。
▶対策:介護福祉士の役割、多職種連携など頻出テーマに重点を置く。過去問を使い、重要キーワードを繰り返し確認する。
社会の理解
▶特徴:法律・制度・歴史を中心に暗記量が多く、近年では時事問題の出題も増加中。用語が堅くとっつきにくい。
▶対策:用語の意味と背景を関連付けて覚えることが重要。制度の変更は図や表で整理し、時系列で理解する。一問一答形式のアプリやカード、教材を使った反復学習を行う。
人間関係とコミュニケーション
▶特徴:対人スキルを問う実践的な内容で、現場経験があっても誤答しやすい。共感力が問われる。
▶対策:相手の立場や感情を意識して、選択肢を判断する。専門用語より共感がカギ。模擬問題を通じて、実感を伴った学習を心がける。
コミュニケーション技術
▶特徴:技術的な視点と人間関係の要素を組み合わせた問題で、聴き方、話し方、非言語コミュニケーションが問われる。
▶対策:事例問題を通して、適切な対応を具体的に覚える。見守る、繰り返して受け止める、などの雰囲気をつかみ、場面を思い浮かべながらトレーニングする。
生活支援技術
▶特徴:問題数が多く、得点しやすい科目。動作の順番や適切な声かけなど、状況に応じた答えが求められる。場面設定が変わると答えが異なるため注意が必要。
▶対策:過去問を解き、正解パターンの感覚を身につける。動画教材や図解を活用して、具体的な支援動作を確認する。
Bパート(45問)

こころとからだのしくみ
▶特徴:生理学や解剖学に基づく医療職向けの専門用語が多い。出題パターンは決まっている。
▶対策:語呂合わせや図を活用して構造を楽しく覚えることが効果的である。心臓、消化器、神経系の構造を語呂で覚えると良い。生活支援とのリンクを意識して学ぶと知識が定着しやすい。
発達と老化の理解
▶特徴:ライフステージごとの特徴や加齢による変化と疾患の違いを問う問題が多い。
▶対策:年齢ごとの変化をライフサイクルで覚える。時系列で図表化すると、なお効果的。疾患との違いを過去問で確認し、加齢の正常な変化を理解しておくことが重要。
認知症の理解
▶特徴:症状やケア方法が多様で混乱しやすい。BPSDと中核症状の違いを理解しにくい。
▶対策:BPSDと中核症状の違いを図表で整理して覚える。事例形式で本人の気持ちを想像しながら答える訓練を行うと、実践的な理解が深まる。
障害の理解
▶特徴:障害の種類が多く、特徴や支援方法が混ざりやすい。見慣れない用語も出題される。
▶対策:障害別(身体、知的、精神)に支援ポイントを表で整理して覚える。障害者総合支援法や支援機関をセットで覚える。
医療的ケア
▶特徴:看護寄りの知識が多く、未経験者には難しく感じる。喀痰吸引や経管栄養の手順や、滅菌と消毒の違いが問われる。喀痰吸引のタイミング、指示者、観察ポイントに関する問題が多い。
▶対策:図解豊富なテキストでイメージ化して覚える。呼吸器や吸引について図を見ながら学ぶと理解が深まる。間違えた問題は理由を調べて理解を深める。「○○とは何か」を確認して抽象的なワードに惑わされないようにし、選択肢の言い回しに注意。
Cパート(20問)

介護課程
▶特徴:抽象的な選択肢が多く、ひっかけ問題が多いため、選択肢に迷いやすい。現場経験があっても迷う問題が出題されることがある。
▶対策:過去問解説を熟読し、なぜその選択肢が誤りなのかを、自分の言葉で説明できるようにする。根拠を明確に理解する。
総合問題
▶特徴:複数科目をまたいだ事例形式で、実践力と横断的知識が問われる。
▶対策:全体的な理解を深め、苦手科目を補う。模擬試験やまとめ問題で総合演習を行い、本番形式に慣れる。時間配分を意識して練習する。
出題数の少ない医療的ケアは、とくに注意が必要です。他の科目で高得点を取っても、医療的ケアの5問で点を取れないと不合格になります。
介護課程や総合問題では、専門用語と知識を踏まえた上で、状況に応じた選択を求められるため、読解力や国語力も重要です。
学習スタイル別の勉強法

通学、独学、通信講座など、学習スタイルによって効果的な勉強法は異なります。
それぞれの状況に応じて活用できる手段があるので、自分に合った方法を取り入れ得点を重ねていきましょう。
独学
▼教材は「最新版+信頼性重視」で選ぶ
古い教材は誤答の原因になるため、法改正に対応した最新版か要確認。
▼学習は“アウトプット重視”で進める
過去問を解きながら、答えの根拠まで説明できる理解を目指す。
▼「短時間×高頻度」の学習を習慣に
1日10~15分を数回に分けた方が、長時間より記憶が定着しやすい。
通信講座
▼サポート機能は積極的に使う
疑問はすぐ質問。動画解説・フォーラムなども活用して誤解の放置を防ぐ。
▼模試は“理解の見直し&本番対策”に活用
曖昧な知識の洗い出しや、時間配分の練習に必須。
通学制
▼授業と過去問を関連付ける
繰り返し出題されるテーマに注目。授業で扱った内容が過去問でどのように出題されているかを意識することで、記憶が定着。
▼質問できる環境を活用する
疑問点はその場で解消。生徒同士で話し合いも有効。
▼模試やテストは“本番モード”で解く
時間配分や試験形式に慣れることで、弱点の早期発見できる。
テキストを使った勉強法

一発合格を目指すためには、自分に合ったテキストを見つけることが非常に重要です。
とくに独学で勉強する場合、本屋に行っても種類が多く、どのテキストを選べばよいか迷ってしまう方も多いでしょう。
代表的な教材には、テキスト、過去問、予想問題、ワークブック、一問一答などがあり、細かく分類されています。
たとえばテキスト系であれは、見やすさや情報量のバランスに注目して選ぶのがおすすめです。
今回は、王道教材である「テキスト」と「過去問」から3つご紹介します。
介護福祉士模擬問題集2026
一般的な過去問集では、基礎的な問題から難易度の高い問題まで幅広く収められているため、傾向がつかみにくく、苦手分野の把握も難しくなります。
この模擬問題集は、毎年必ず出題される問題や頻出問題を集約しており、効率的に学習できる構成になっています。
重要なのは、出題傾向を理解し、毎年必ず出る問題や出題頻度が高い問題をインプットすることです。
介護福祉士国資ナビ
福祉用具や病気・疾患の名称など、覚えるべき専門用語が多く、似たような言葉も多いため、混乱しがちです。とくに用語の幅が広く、学習に苦労する方も少なくありません。
「介護福祉士国資ナビ」は、わからない専門用語を辞書のように調べるのに最適なテキストです。
たとえば「尿失禁」という言葉一つでも、切迫性尿失禁、腹圧性尿失禁、溢流性尿失禁、機能性尿失禁、反射性尿失禁と、5種類も存在します。
原因や特徴がそれぞれ異なるため、ひとつずつ調べることで、より確実に理解できるようになります。
介護福祉士過去5年問題集
ポイントは、年度ごとではなく項目ごとに解くことです。
年度ごとに取り組んでしまうと、科目や難易度がバラバラで、ただ答え合わせをしているだけになってしまい、記憶にも残りにくくなります。
一方、科目ごとにまとめて解くと、同じような問題を見比べやすくなり、出題傾向がつかみやすくなります。
ただし、ここで重要なのは、事前に『介護福祉士模擬問題集』などでインプットを済ませておくことです。
ある程度の知識が頭に入っている状態で取り組むことで、過去問演習の効果を最大限に引き出せます。
最近では、スマートフォンやタブレットで過去問を解けるアプリもあるため、育児と両立している方や働きながら学んでいる方にとっては、このようなツールを活用するのも一つの方法です。
まとめ

今回は、介護福祉士国家試験に一発合格するための、状況に応じた効果的な学習法についてご紹介しました。
学習スタイルは人それぞれ異なりますが、最終的に問われる知識や出題範囲に違いはありません。
重要なのは「暗記したかどうか」ではなく「内容を正しく理解し、自分の言葉で説明できるか」という視点です。
一問一問を丁寧に読み解き、何が問われているのかを意識することで、知識は確実に身につきます。
すでに現場で介護職員として従事されている方であれば、学習内容と日々の業務を結びつけることが、大きな助けとなるのではないでしょうか。
教科書に書かれた知識が、実務とリンクした瞬間、理解の深さと記憶の定着は格段に高まります。
国家試験に向けた準備は、決して短期間で済むものではありません。
しかし、目的意識を持ち、自分に合った方法で継続的に取り組めば、一発合格も十分に現実的な目標になります。
焦らず、一歩ずつ着実に。日々の積み重ねが、確かな自信と結果につながることを忘れずに、試験本番に向けた準備を進めていきましょう。