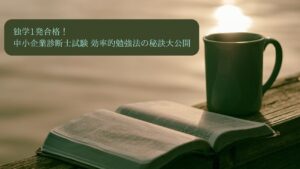これだけは押さえて!機械・プラント製図技能士1級合格勉強法

『機械・プラント製図技能士』って何か難しそう、そう思った方も多いでしょう。
機械・プラント製図技能士1級取得は簡単ではありません。
ですが、ポイントを押さえて効率の良い勉強法を知れば一級合格は目指す事が出来ます。
今回はその押さえるべきポイントをわかりやすく解説していきましょう!
機械・プラント製図技能士ってどんな資格?

技能検定制度の一種であり、都道府県職業能力開発協会が実施している学科と実技試験に合格して得られる資格。
〜技能検定とは〜
働く者が必要とされる技能のレベルを評価される国家資格の検定の制度。
合格すると合格証書が交付されて『技能士』と名乗る事ができます。
機械加工、ファイナンシャル、建築など131種類もの試験があります。
〜等級区分〜
1級〜3級に区分されます。
職種によっては難易度を分けないで行う単一等級もあります。
〜試験方法〜
学科試験と実技試験の両方が実施されます。
両方に合格しないと資格は得られません。
ただし、どちらか一方だけ合格した方は、不合格になった試験のみ受検する事が可能です。
合格すれば、『技能士』と名乗る事ができます。
〜技能のメリット〜
・自分の自信、長所になる
・実力がつく
・機械加工に関して詳しくなり、幅広い知識が得られる
〜技能検定のデメリット〜
・比較的難易度が高い
・実技、学科共に、勉強にかなりの時間を要する
機械・プラント製図技能士の概要

機械・プラント製図技能士とは機械やプラントの図面を書く技術を証明する為の国家資格です。
機械・プラント製図技能士は図面を書く能力の他に、機械や設計の技術も必要とされる事も多く、高度な知識が求められます。
〜受験資格〜
・1級 実務経験歴 7年以上
・2級 実務経験 2年以上
・3級 制限なしで受験可能
職業訓練の実施歴や学歴によって実務年数は異なりますので詳しくは、厚生労働省まで問い合わせてみると良いでしょう。
機械・プラント製図技能士を取得したらどんなメリットがあるの?

①国家資格の為、社会的地位が高くそれぞれの分野で評価されやすい
資格には国家資格と民間資格があります。
国家資格・・国の法律に基づき、個人の各分野における能力と知識が認定され、特定の分野の職業に従事する事が出来る資格
民間資格・・国の法律に基づくものではなく、社団法人や財団法人等の民間団体が独自に定めた能力や知識を判定したものを証明する資格
〜国家資格を持っていると業務できる職種〜

・医師
・看護師
・美容師
・薬剤師
・公認会計士
・技術士
・教師
『機械・プラント製図技能士』は国家資格になりますので、高い能力と知識が認定されており、この資格を取得しているだけで、良い人材と評価されやすいです。
②難易度の高い仕事を任されたり、業務の幅が広がる
機械やプラントの図面を作成する事が出来る国家資格者という肩書きがつく為に、企業や周囲からの信頼度や評価も高くなります。
製図のスキルは勿論の事、機械の専門知識や設計の能力とセンスなどが問われる為、機械・プラント製図技能士の資格を取得していると、幅広く業務を任される事が多いでしょう。
③必要としている業界が多く、就職先の幅が広がる

機械・プラント製図技能士の資格は技術者の為に必要としている業界が多いです。
例えば、機械、電気、自動車、建築など多岐にわたって能力ある人材が求められます。
自動車組立機械、機械加工、製品組立、半導体設計開発、医療機器の開発、電気機器の設計、鉄道車両の設計、ロボットの開発、その他技術開発など
これらの職業は、機械・プラント製図技能士の資格が必須となります。
機械・プラント製図技能士の業務内容とは・・?

1 打ち合わせ
クライアントとの打ち合わせをします。
その際図面を作成するうえでの内容や工程を話し合います。
ここで重要なのはその過程で必ず細かな所までヒアリングをする事です。
具体的に施工にあたって必要な修正や、製図のうえで重要なデザインなどの変更等、具体的な内容の聞き取りを行います。
ここで変更や調整部分の聞き取りをきちんと行えていない場合、あとから修正が必要となり困難な状況やイメージの相違が発生してしまい、お互いに納得する良い仕事が出来なくなります。
ヒアリングは大変重要な過程であり、機械・プラント製図技能士としてプロの仕事をするうえでは、非常に大切な部分といえるでしょう。
機械・プラント製図技能士が実際に作図していく工程で、未定な箇所は図面上に記載しておくと依頼者が見た際にわかりやすく、円滑にコミュニケーションが図れる為おすすめです。
作図段階で図面を作成する事は勿論ですが、人と人とのコミュニケーションは非常に重要な部分です。
どんな職業でもいえる事ですが、社会で円滑なコミュニケーションをとれている人は多くの場面で活躍できる為、信頼も高くなります。
2 作図
具体的な内容をヒアリングした後、作図に入ります。
打ち合わせの際に期日を設定しその日程に沿って作図を完成させます。
1の打ち合わせの際にも記載しましたが、作図工程で依頼者に再度聞き取りが必要ないように、後に問題点となりそうな箇所は事前に話し合っておきます。
図面作成は集中力と時間が必要となる為、手間になる事は極力避ける為です。
何か作業工程で問題が生じない限り、ここでは作図を書き上げる作業を優先します。
3 修正や再確認
作図が完成すると、依頼者に図面をチェックしてもらう作業です。
ここで、もし図面作成時に問題が発生した箇所については、再度話し合って解決案を出します。
なるべく打ち合わせの際は細かなチェック作業になりますので、対面で行う方が良いでしょう。
お互いに納得した形で、最終的には納品になります。
機械・プラント製図技能士の試験内容

1級から3級まであり、「機械製図手書き作業」、「機械製図CAD作業」、「プラント配管製図作業」の3つに分類されています。
※【1級〜3級】
学科試験
・製図一般
・材料
・材料力学一般
・溶接一般
・関連基礎知識
(選択科目)
・機械製図法
・プラント配管製図法
実技試験
・機械製図手書き作業
課題図となる機械装置を組み立てた状態の図面から、指定された部品図を手書きで作成する作業
・機械製図CAD作業
課題図となる機械装置を組み立てた状態の図面から、指定された部品図をCADで作成する作業
・プラント配管製図作業
指定されている配管図やP&Iダイアグラム、機器外観図や部品寸法表、配管計画図を基にして、指定された配管の配管組立図を作成する作業
※【3級】
・製図一般
・材料
・材料力学一般
・溶接一般
(選択科目)
・機械製図法
実技試験
・機械製図手書き作業
課題図となる機械装置を組み立てた状態の図面から、指定された部品図を手書きで作成する作業
・機械製図CAD作業
課題図となる機械装置を組み立てた状態の図面から、指定された部品図をCADで作成する作業
機械・プラント製図技能士の試験の難易度

機械・プラント製図技能士の試験は決して簡単ではありません。
出題範囲が広く、知識のスキルも求められます。
また、実技試験では高度な能力が必要とされます。
合格基準点が定められており、学科試験は100点満点中の65点以上、実技試験では100点満点中の60点以上が必須です。
機械・プラント製図技能士の試験の合格率
機械・プラント製図技能士の合格率は、年度によって差があり実技試験も難しい事から合格率は決して高くはありません。
2017年では、志願者6,041人に対して、合格者が2,121人で合格率は35.1%ですが、2020年では、志願者5,276人に対して、合格者が2,554人で合格率は48.4%と、年度によって難易度が変わるケースもあるので、試験に向けた準備と勉強が必要となるでしょう。
機械・プラント製図技能士1級に合格する為の攻略法とは・・?
機械・プラント製図技能士1級への道は決して平坦ではありませんが、十分な準備と対策を駆使していけば、合格する事ができます。
①実技に必要な道具を揃える

実技試験では課題図を読み取らなければいけない為に、道具が必要です。
・コンパス
・分度器
・三角定規
・円定規
・電卓
・三角スケール
・蛍光ペン
・ストップウォッチ
など
②実技試験の練習を念入りに行う
〜具体的な練習方法〜
・過去問の課題図の原寸をコピーしたものを用意する。
※(試験本番と同じものに触れる為に原寸で出力します)
↓
・ストップウォッチを用意し、時間を測る
実技試験では決められた時間でこなしていく必要がある為、勉強段階で時間を意識する事が重要になってきます。
自分で時間を決めてセットし、時間内にこなせるように何度も練習しましょう。
↓
・問題を読み込む
特に重要な部分は蛍光ペンでマーキングして、何度も問題文を読み込みます。
投影図の配置や断面指示などは特に注意してチェックします。
問題文に書かれている寸法(許容交差など)は赤ペン等で、書き込んでいきます。
↓
・課題図の中にある指定された部品をマーキングする
マーキングしておく事で作図する対象が明確になり、よりわかりやすくなります。
↓
・指定された部品の形状を読み取る(読図)
マーキングされた部品を頭の中で立体化してみましょう。
ここでは読図力を身につけます。想像力が必要とされますが何度も練習していくなかで、段々とコツが掴めてきます。
行き詰まった時には、課題図と解答図を見比べる練習から始めてみても良いでしょう。
↓
・採寸する
三角スケールを使用し、課題図に指定された部品を採寸したものを記入していきます。
↓
・図枠を作成する
問題文で指定された図枠を作成していきます。
↓
・指定部品の形状を作図してみる
実際に採寸した数値をもとにして、指定部品の作図をします。
軸対称部分は、CADのミラー反転やコピーを使用するなど効率良く出来る練習をしましょう。
↓
・寸法を記入する
寸法には優先すべき順序があるので、それを意識しながら採寸します。
①最外寸や基本形状の中心位置
②交差が伴う寸法
③穴寸法やその他の寸法
④RC寸法
↓
・検図をする
寸法漏れを防ぐ為に、検図の練習をしましょう。
↓
・模範解答図と比較して、自分で採点、評価してみる
寸法漏れや形状の違い、寸法の順序などを振り返り、自分の弱点を書き出して徹底的に復習をします。
③学科試験の対策を行う
〜具体的な対策方法〜
実技試験に力を入れるのは当然の事ですが、学科試験にも合格しなければ意味がありません。
学科試験は出題範囲が広いので、効率良く勉強をする事が求められます。
学科試験は真偽法、及び四肢択一法で行われます。
・真偽法
正解、誤りを答える解答法
・四肢択一法
正しいもの、または誤っているものを1つ選ぶ解答法
※ポイントは過去問を徹底的に解く事

過去問をとにかく多く解く練習をして、苦手分野を克服する事が重要。
〜過去問の入手方法〜
①中央職業能力開発協会の公式HPにて、過去2年分の過去問の閲覧が可能
②出版社から購入する
③周りに資格を取得した人がいれば、その人に借りる
過去問は過去2年分の把握をしていれば、学科試験は十分だといえるでしょう。
④参考書を熟読し、苦手な分野を強化する
実際に過去問を解いてみて、自分の苦手分野を見出し徹底的に強化します。
〜おすすめの参考書〜

1 機械製図CAD作業技能検定試験1・2級実技課題と解読例/河合優
製図に特化した技能試験対応の『機械製図CAD作業技能検定実技試験1・2級 実技課題と解読例』の第4版。
令和2年〜4年度の直近2年間の1・2級の実技課題と解答を詳しく解説。
2 機械製図CAD作業技能検定試験1・2級実技課題と解読例(第2版)/河合優
機械製図CAD作業技能検定実技試験1・2級実技課題の受検対策本。
直近3年間の実技課題の解読方法を丁寧に解説した受検対策問題集。
機械・プラント製図技能士1級合格勉強法〜まとめ〜

機械・プラント製図技能士は様々な業界で必要とされている人材であり、この資格を取得している人は高い技術と多くの知識が必要とされる為、活躍できる場面も多いです。
また資格は将来独立を目指す人、リモートワークを希望している人にも向いおり、場所を問わず仕事を請け負えるのもメリットの一つ。
この資格が向いている人の特徴は、きめ細かな作業が好きな方、数字が得意な方などに向いているといえるでしょう。
また製図段階で正確に伝える為に、製図の技能は勿論、製品の知識や理解力も要求されますので、コツコツと前向きに努力できる人が向いています。
勉強法は簡単ではないですが、苦手分野を克服すればあとは回数をこなすだけです。
この記事や参考書を駆使して、機械・プラント製図技能士1級合格を目指してくださいね。