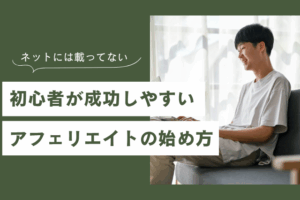ドラマの向こう側『オールドルーキー』に学ぶスポーツマネジメントの世界とは

スポーツマネジメントの世界
スポーツは単なる競技の場から、世界経済を牽引する巨大な産業へと進化を遂げました。
このダイナミックな変革の中心にあるのが、スポーツマネジメントです。
本記事では、スポーツマネジメントの定義から、その多岐にわたる業務内容や主要な組織、収益化、そしてこの分野で成功するために求められるスキルまで、詳しく解説します。
『オールドルーキー』が映し出す、スポーツマネジメントの真髄

日曜劇場の『オールドルーキー』というドラマをご存じでしょうか。
綾野剛さんが演じる元サッカー日本代表・新町亮太郎が引退後に入社したスポーツマネジメント会社「ビクトリー」で奮闘するドラマですが、華やかなアスリートの世界から一転、スーツ姿で選手の人生に真剣に向き合う新町の姿は、スポーツビジネスの奥深さ、そしてアスリートの「セカンドキャリア」というリアルな課題を鮮やかに描き出し、多くの視聴者の心を掴んだドラマです。
プロ選手の移籍交渉や、若きスケートボーダー秀島修平のマネジメントを通して、新町は単に競技成績を追求するだけでなく、選手一人ひとりの人間性や幸福、そして彼らを取り巻く複雑な環境に寄り添うマネジメントの重要性を痛感します。スポンサー獲得の泥臭い営業、選手の金銭感覚の管理、そして不祥事への危機管理。これらはすべて、スポーツマネジメントの重要な業務です。
『オールドルーキー』は、スポーツマネジメントが単なるビジネスではなく、アスリートの人生、夢、そして社会との繋がりを紡ぐ「人間ドラマ」であることを教えてくれました。このドラマをきっかけに、スポーツマネジメントの世界、そしてアスリートのセカンドキャリアというテーマに興味を持っていただけた方も多いのではないでしょうか。
ここからは、スポーツマネジメントの具体的な業務内容や、その裏側にある世界をさらに深く掘り下げていきます。
スポーツマネジメントとは

スポーツマネジメントとは、スポーツに関連するあらゆる活動を、効率的かつ効果的に運営・管理し、その価値を最大化していく専門家です。
具体的には、スポーツリーグやチームの運営、イベントの企画・開催、施設の管理、選手の育成・契約交渉、そして新しいビジネスモデルの創出など、多岐にわたる側面を包含します。
スポーツマネジメントの最終的な目標は、スポーツの持つ社会的・文化的価値を高めながら、経済的な持続可能性を確保し、関わる全ての人々(選手、ファン、スポンサー、地域社会)に利益をもたらすことにあります。
単なる運営業務を超え、経済的成長とプロフェッショナル化を推進する戦略的な役割を担い、選手、スポンサー、ファンの3者を結びつけ、ビジネスとして持続的に発展させるために不可欠な存在と言えます。
多様なステークホルダーの関係を最適化し、スポーツの持つ価値を最大化することを目的としています。
スポーツマネジメントの主要な業務領域
スポーツマネジメントの業務は非常に広範であり、専門性によって様々な役割に分かれます。
それぞれの領域が密接に連携し、スポーツ産業全体の発展を支えています。
チーム・選手・コーチの育成とマネジメント

アスリートが最高のパフォーマンスを発揮し、そのキャリアを通じて成功を収めるための包括的なサポートを提供します。
具体的には、選手のコンディショニングや栄養管理、メンタルケアといった日々のサポートはもちろん、より良い練習環境の整備も行います。
現役引退後のセカンドキャリア支援も重要な業務の一つで、選手が競技を離れた後も社会で活躍できるよう、研修や就職あっせんなど多角的にサポートします。
『オールドルーキー』の新町亮太郎も、まさにこのセカンドキャリア支援の最前線で奮闘していました。
また、選手が安心して競技に集中できるよう、代理人として契約交渉や移籍交渉、さらにはCM出演契約などの肖像権管理を代行することも重要な役割です。
チーム全体のマネジメントとしては、チームのスケジュール調整や遠征手配、選手寮の管理なども含まれます。
ゼネラルマネージャー(GM)は、チーム強化方針の策定、選手獲得、スポンサー交渉、メディア対応、選手との面談など、チーム運営の中核を担い、チームの方向性を決定づける重要な存在です。
スポーツイベントの企画・運営

スポーツイベントは、単なる競技の場ではなく、経済的利益の創出と地域社会の活性化という二重の目的を持つ戦略的な業務です。
オリンピックやW杯のような国際的なビッグイベントから、プロリーグの公式戦、地域の市民マラソン大会まで、その規模は多岐にわたります。
企画段階では、イベントのコンセプト立案、費用対効果の分析、資金計画、会場選定などが行われます。
運営段階では、広報活動や集客戦略の策定(チケット販売戦略、プロモーション活動など)、当日の会場設営、セキュリティ管理、ボランティアスタッフの配置と管理、緊急時の対応計画などが含まれます。
マーケティング、スポンサーシップ、広報活動

スポーツチームや選手のブランド価値向上、ファンエンゲージメントの強化、そして収益源の多角化を戦略的に連携させることで、ビジネスの持続的成長を牽引します。
マーケティングでは、ターゲット層の分析に基づいた戦略的なブランディングを行い、チームや選手の魅力を最大限に引き出します。
広報活動としては、メディア対応(記者会見、取材調整など)、プレスリリース作成、SNS運用を通じた情報発信、ファンクラブ運営によるファンとの継続的な関係構築などがあります。マスコットキャラクターの活用やファンイベントの企画なども、広報活動の一環です。
そして、スポーツビジネスの財政基盤を支えるのがスポンサーシップです。
企業のニーズを理解し、チームやイベントとの適切なマッチングを行い、Win-Winの関係を構築することが求められます。スポンサーシップ契約の獲得だけでなく、その効果を最大限に引き出すための広報PR戦略や、スポンサー企業との継続的な関係構築も重要な業務です。
また、ユニフォームやグッズの販売、ライセンスビジネスを通じて収益を最大化する戦略も、この領域の重要な一部となります。
地域スポーツ振興と新規ビジネス創出

スポーツは地域社会の活力源となり、人々の生活に豊かさをもたらします。
この領域は、地域住民の健康増進やコミュニティ形成を目的としたスポーツ活動の推進と同時に、そこから新たなビジネスチャンスを創出する業務です。
具体的には、地域のスポーツイベントやスポーツ教室の開催、スポーツを通じた青少年の健全育成プログラムの実施などがあります。
近年では、観光やIT、ヘルスケアなど異分野と連携した新規事業開発が注目されています。
例えば、スポーツツーリズムの推進、健康データを活用したパーソナライズされたトレーニングプログラムの開発、地域産品とスポーツイベントを組み合わせたプロモーションなど、スポーツの社会的・経済的価値を高める多様な役割を担います。
スポーツ施設管理

スタジアム、アリーナ、フィットネスクラブ、体育館などのスポーツ施設は、競技が行われるだけでなく、地域の人々がスポーツに親しむための重要な拠点です。
施設管理の業務は、施設の物理的な維持管理(清掃、修繕、設備の点検など)に留まらず、利用者の安全・快適性を確保し、ポジティブな顧客体験を創出する戦略的な役割を担います。
日常的な施設の保守点検や使用予約管理はもちろん、地域のニーズに合わせたプログラムやイベント(スポーツ教室、フィットネスプログラム、地域の大会など)を企画・運営することで、施設の稼働率を高め、収益を向上させることが重要です。
また、緊急時の避難経路の確保やAEDの設置、利用者の怪我に対する迅速な対応など、安全管理は最優先事項です。
老朽化対策や、環境に配慮した施設への転換も長期的な施設運営における重要な課題となっています。
スポーツマネジメントを支える主要な組織と役割

スポーツマネジメントは、多種多様な組織や専門家の連携によって成り立っています。
それぞれの役割が組み合わさることで、スポーツ界全体が機能し、発展していきます。
スポーツエージェント
『オールドルーキー』でもその存在感が大きく描かれたスポーツエージェントは、プロスポーツ選手の代理人として、選手のキャリアを全面的にサポートする専門家です。
彼らの主な業務は、選手とチーム間の契約交渉、移籍交渉、そしてCM出演やイベント参加などのスポンサー契約代行です。選手の肖像権管理や、税務・法務に関するアドバイスを行うこともあります。
エージェントは、選手の才能が最大限に評価され、適切な報酬と環境が提供されるよう交渉し、選手が競技に集中できる環境を整えることで、その能力を最大限に引き出すことに貢献します。
この役割には、スポーツに関する深い知識だけでなく、法律やビジネスに関する高度な専門知識、そして卓越した交渉術が求められます。
スポーツリーグ・統括団体
JリーグやBリーグのようなプロリーグ、または各競技の連盟や協会がこれにあたります。これらの組織は、競技の最高機関として、スポーツ界全体の健全な発展と公平な競争環境の維持を目的としています。
主な業務は、試合日程の調整、公式記録の作成と管理、競技ルールの管理、審判の育成と派遣など、競技運営の基盤を築くことです。
さらに、リーグ全体のブランディングやプロモーション活動を通じて、ファン層の拡大と市場価値の向上を図ります。
スポーツ振興事業や、ドーピング対策、ハラスメント防止などのコンプライアンス遵守も重要な役割であり、リーグや競技のガバナンスを確立し、社会的な信頼を確保する責任を担います。
プロスポーツクラブ(チーム)
プロスポーツクラブは、選手、コーチ、そしてビジネスサイドのスタッフが一体となって運営される組織です。
チーム代表/オーナーは、クラブの最高責任者として、対外的な顔となり、資金面の最終的な意思決定を行います。
ゼネラルマネージャー(GM)は、チームの強化方針の策定、選手獲得・放出、移材交渉、そして監督やコーチ陣の人事など、チーム編成と強化に関する中核的な業務を担います。
また、スポンサー交渉やメディア対応、選手との面談など、幅広い役割をこなすマルチプレーヤーです。
監督やコーチは、戦術の立案、選手の育成、日々の練習指導を通じて、チームの競技力向上に直接貢献します。
広報・マーケティング部門は、ファンサービスの企画、スポンサー対応、イベント企画などを通じて、クラブの魅力を発信し、集客と収益向上に努めます。
営業部門は、スポンサー獲得やチケット販売、グッズ販売など、クラブの資金繰りを支える重要な役割です。
その他、予算管理や事務処理を担う総務・経理部門、若手選手の才能を発掘するスカウト、育成プログラムを担当する育成担当、試合データを分析する分析担当など、多岐にわたる専門スタッフがそれぞれの役割を果たすことで、クラブは成り立っています。
フィットネスクラブのような地域密着型のスポーツクラブでは、フロント業務、トレーニング指導、施設メンテナンス、グループレッスン担当なども重要な運営業務となります。
スポーツ施設管理者
公営・民営を問わず、スタジアム、アリーナ、体育館、フィットネスクラブなどのスポーツ施設の運営と維持管理を担います。彼らの主な業務は、施設の保守・点検、清掃、設備の管理(照明、音響、空調など)、使用予約の管理です。
利用者が安全かつ快適に施設を利用できるよう、常に環境を整備する責任があります。
また、施設の稼働率を高め、収益を向上させるために、イベントの誘致や、地域のニーズに合わせたスポーツ教室やフィットネスプログラムの企画・運営も行います。
地域コミュニティにおけるスポーツ振興の拠点として、地域住民の健康増進や交流の場を提供するという社会的役割も担っています。
スポーツ関連企業
スポーツ業界は、上記のような組織だけでなく、多様な企業の参入によって支えられています。
スポンサー企業は、資金提供や製品・サービスの提供を通じて、チームやイベントを支援します。
スポーツ用品メーカーは、競技用品やウェアの開発・供給を通じて、選手のパフォーマンス向上に貢献します。
ディア企業は、試合の放映やニュース報道を通じて、スポーツの魅力を広く伝えます。
近年では、IT企業がデータ分析やデジタルコンテンツ配信で、コンサルティング会社が経営戦略やマーケティング戦略で、スポーツ組織の成長を支援しています。
これらの企業は、スポーツマネジメントの対象となると同時に、重要なパートナーでもあります。
スポーツマネジメントにおける収益化戦略と課題

スポーツビジネスの成功は、安定した収益基盤の上に成り立っています。
現代のスポーツクラブやリーグは、多角的な収益源を確保し、持続可能な経営を目指しています。
主な収益源
- 広告収入(スポンサーシップ): 最も大きな収益源の一つであり、企業からの協賛金が中心です。ユニフォーム、スタジアムの看板、イベントの冠協賛など、様々な形で企業ロゴを露出する対価として得られます。長期的なパートナーシップを築くことが重要です。
- 入場料収入: チケット販売による収入。シーズンチケット、単券、VIP席など多様な価格設定と販売戦略が重要となります。
- 物販収入: チームグッズ、ユニフォーム、記念品などの販売による収入です。オンラインストアの強化や、コラボレーション商品の開発も進んでいます。
- 放映権料: テレビ局やインターネット配信プラットフォームへの試合映像コンテンツの提供による収入です。特にプロリーグにとっては、極めて重要な収益源となっています。
- 移籍金: 選手の移籍に伴って発生するクラブ間の金銭のやり取りです。育成型クラブにとっては重要な収入源となりえます。
- アカデミー収入: 下部組織であるアカデミーの運営に伴う会費収入や、そこからトップチームに昇格した選手が将来移籍する際の移籍金の一部などが含まれます。
- 飲食販売: 試合会場やイベント会場での飲食物の販売収入です。
- デジタルコンテンツ: VR/AR技術を活用した没入型観戦体験、NFTやメタバースを活用した新たなファンエンゲージメントと収益化の試み(例:バーチャルハマスタ)など、テクノロジーを活用した新しい収益源が注目されています。
- ライセンス事業: チーム名やロゴ、選手の肖像などを商品化する権利を貸し出すことで得る収入です。
- 現在の課題:
現在のスポーツ業界の主要な課題の一つは、収益モデルの多角化と安定化です。チケット収入やスポンサー収入に過度に依存する状況から脱却し、デジタル技術の活用や地域連携を通じた新たな収益源の開拓が喫緊の課題となっています。特に、若年層のスポーツ離れや、少子高齢化による観客層の変化に対応するため、より魅力的なコンテンツ提供と、多様な収益チャネルの確保が求められています。
スポーツマネジメント業務に関連する法的側面、契約、倫理的課題
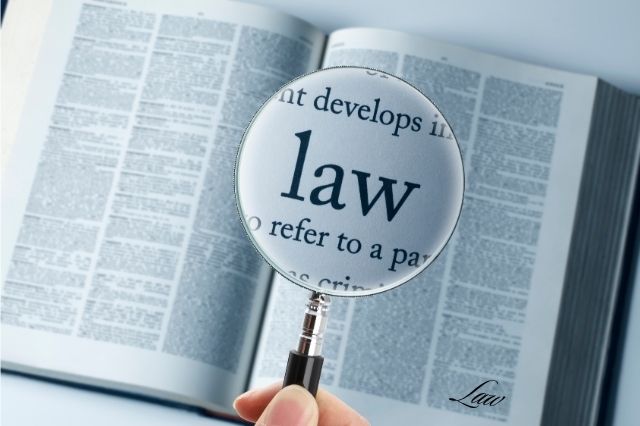
スポーツマネジメント業務は、アスリートの人生や多額の資金が関わるため、多くの法的・倫理的側面を伴います。適切なコンプライアンスと高い倫理観が、業界全体の信頼性と持続可能性を確保するために不可欠です。
- 法的側面・契約:
- 選手契約: 選手とチーム間、選手とエージェント間の契約は、労働法、民法、そして各スポーツ団体(例:Jリーグ規約)独自の規約に基づいて厳格に管理されます。契約期間、報酬、肖像権の帰属、負傷時の対応などが詳細に定められ、紛争を避けるための明確な条項が必要です。
- 肖像権・知的財産権: 選手の肖像権、チームロゴやエンブレム、イベント名などの知的財産権の管理と利用許諾は非常に重要です。無断使用は法的な問題に発展する可能性があり、適切なライセンス契約が必要です。近年では、SNS上での発信に関する選手の権利と責任も議論の対象となっています。
- スポンサー契約: 企業とのスポンサーシップ契約は、提供内容(資金、物品、サービス)、期間、金額、企業ロゴの露出範囲、独占権の有無などを明確に定める必要があります。契約違反があった場合の対応も盛り込まれます。
- 業務委託契約: イベント運営や施設管理など、外部に業務を委託する際には、委託内容、責任範囲、報酬規定、スケジュール管理、安全管理などを明確に記した契約書が必須です。特に、業務遂行中に発生した事故や災害に関する責任の所在、中途解約条件なども慎重に検討されます。
- コンプライアンス: スポーツマネジメントに携わる組織や個人は、独占禁止法(リーグ内での移籍制限など)、景品表示法(プロモーション活動)、個人情報保護法(選手やファンのデータ管理)、税法など、様々な法令を遵守する義務があります。不正行為や談合は、社会的信用の失墜に直結します。
- 倫理的課題:
- ドーピング問題: スポーツの公平性と選手の健康を脅かすドーピングは、マネジメント側が厳しく監視し、予防策を講じる必要があります。アンチ・ドーピング規定の徹底と教育が重要です。
- 八百長・賭博問題: 試合結果の公正性を揺るがす八百長やスポーツ賭博への関与は、スポーツの根幹を揺るがす行為です。関与者への厳正な対応と、その監視体制の構築が求められます。
- ハラスメント: 選手やスタッフに対するパワハラ、セクハラ、いじめなどの排除は、安全で健全な職場環境を提供する上で不可欠です。適切な相談窓口の設置や、ハラスメント防止のための研修が求められます。
- 選手の心身の健康管理: 勝利至上主義のあまり、選手に過度な練習や試合を強いることは、心身の健康を損なう可能性があります。選手の心身の健康を最優先するという倫理観が、マネジメント側には強く求められます。
- 透明性と説明責任: 組織運営や資金の流れ、意思決定プロセスの透明性を確保し、ファンやスポンサー、地域社会といったステークホルダーに対して、十分な説明責任を果たすことは、信頼構築の基盤となります。
これらの法的・倫理的側面への適切な対応は、スポーツ組織の信頼性と持続可能性に直結するだけでなく、スポーツが社会に与えるポジティブな影響を維持するためにも不可欠です。
スポーツマネジメント業界の現在のトレンドと展望

スポーツマネジメント業界は常に進化しており、国内外の社会経済情勢や技術革新の影響を受けながら、新たな可能性を追求しています。
- テクノロジーの活用:
- データ分析の深化: 選手パフォーマンス分析(例:走行距離、シュート成功率)、ファン行動分析(チケット購入履歴、グッズ購買データ)、マーケティング効果測定など、データに基づいた意思決定が加速しています。AIを活用した戦術分析や、怪我の予防なども進んでいます。
- デジタルコンテンツの多様化: 試合のライブ配信だけでなく、VR/AR技術を活用した没入型観戦体験(まるで会場にいるかのような体験)、NFT(非代替性トークン)を活用したデジタルコレクタブル、メタバース空間でのファンイベント開催など、新たなファンエンゲージメントと収益化の試みが急速に進んでいます。
- スマートスタジアム・アリーナ: IoT技術を導入し、チケットレス入場、キャッシュレス決済、座席からの飲食オーダー、パーソナライズされた情報提供など、来場体験の向上を図る取り組みが進んでいます。
- スポーツテック: ウェアラブルデバイス、AIトレーナーアプリ、オンラインコーチングプラットフォームなど、テクノロジーを活用してアスリートのパフォーマンス向上や、一般市民の健康増進をサポートする「スポーツテック」分野が急成長しています。
- グローバル化と市場拡大:
- 国際的なリーグや選手の移籍が活発化し、スポーツビジネスは国境を越えた展開が加速しています。欧州サッカーリーグの国際戦略や、NBAのグローバル展開などがその例です。
- アジアや中東、アフリカといった新興国市場におけるスポーツ需要の増加は、新たなファン層や投資機会を生み出しており、国際的な視点でのマネジメント戦略が不可欠となっています。
- ヘルスケア・ウェルネスとの融合:
- 健康志向の高まりや、予防医療への関心の高まりを背景に、スポーツは単なる競技だけでなく、人々の健康維持や増進、ライフスタイルの向上に貢献する要素として注目されています。
- フィットネス産業、医療機関、自治体などが連携し、地域住民の健康増進を目的としたプログラム開発や、スポーツを通じた疾病予防への取り組みが進んでいます。
- スポーツクラブが地域住民の健康拠点としての役割を強化する動きも活発です。
- サステナビリティと社会的責任(CSR):
- 地球環境問題への意識の高まりから、スポーツ組織も環境負荷の低減に積極的に取り組んでいます。エコフレンドリーな施設運営、廃棄物削減、再生可能エネルギーの導入などが進められています。
- 地域社会への貢献(CSR活動)は、スポーツ組織の社会的価値を高め、ファンやスポンサーからの支持を得る上で非常に重要です。スポーツを通じた教育支援、障害者スポーツの推進、地域イベントへの参加などが含まれます。SDGs(持続可能な開発目標)への貢献も、スポーツ界の大きなテーマとなっています。
- ファンエンゲージメントの深化:
- デジタル技術の進化により、ファンとの接点は多様化しています。単なる観戦にとどまらず、SNSでの交流、オンラインイベント、ファン投票企画など、ファンがより主体的に参加できる機会を提供し、エンゲージメントを深める取り組みが進んでいます。
- パーソナライズされた情報提供や、限定コンテンツの提供により、個々のファンのロイヤルティを高める戦略も重要視されています。
これらのトレンドは、スポーツマネジメントの専門家に対し、常に新しい知識とスキルを学び、変化に対応していく柔軟性を求めています。
スポーツマネジメントの専門家に求められる主要なスキルと資質

スポーツマネジメントの分野で活躍するためには、多岐にわたる能力と資質が不可欠です。
『オールドルーキー』の新町亮太郎も、自身のコミュニケーション能力や経験を活かしていましたが、実際の現場ではさらに幅広い専門性が求められます。
- ビジネス・財務スキル:スポーツマネジメントは、スポーツを「ビジネス」として成功させるためのものです。そのため、基本的なビジネススキルは必須です。
- 経営戦略: 事業計画の策定、市場分析、競合分析、SWOT分析といった経営的な視点と、それを具体的に実行する企画力、発信力、遂行力が求められます。
- 財務管理: 会計、税務の基礎知識は必須です。クラブやリーグの予算策定、日々の収支管理、資金調達(融資、投資家からの資金獲得など)の能力も重要です。スポーツ業界特有の収益構造(放映権料、移籍金など)を理解し、キャッシュフローを適切に管理する能力が求められます。
- マーケティング: ブランド戦略、広報戦略、デジタルマーケティング、スポンサーシップ獲得のための戦略立案と実行力が必要です。データ分析に基づき、ファンや顧客のニーズを的確に捉える能力が重要になります。
- コミュニケーション・交渉術:スポーツマネジメントは「人と人」との繋がりが非常に重要となる分野です。
- 高いコミュニケーション能力: 選手、コーチ、チームスタッフ、スポンサー企業、メディア関係者、ファン、地域住民、行政機関など、多様なバックグラウンドを持つステークホルダーと円滑な関係を築き、それぞれのニーズを理解し、調整する能力が不可欠です。
- 交渉術: 選手との契約交渉、スポンサー企業との契約交渉、移籍交渉など、スポーツマネジメントには交渉の場面が多くあります。相手の立場を理解し、BATNA(不調時対策案)やRV(留保価値)といった交渉の基本概念を理解した上で、双方にメリットのある合意を形成する能力が求められます。心理学的な側面(アンカリング、損失回避の心理など)を理解し、雑談などを通じて信頼関係を築くことも重要です。
- リーダーシップ:スポーツ組織を率いたり、大規模なイベントを成功させたりするには、強力なリーダーシップが不可欠です。
- ビジョン提示と目標設定: チームやプロジェクトの明確なビジョンを提示し、メンバーを巻き込みながら具体的な目標を設定する能力。
- チームビルディング: メンバー一人ひとりの適性を把握し、それぞれの能力を最大限に引き出しながら、目標達成に向けてチームとしての一体感を醸成する能力。
- 意思決定と責任: 困難な状況やプレッシャーの中でも、冷静かつ的確な意思決定を行い、その結果に対する責任を負う覚悟。状況に応じて、旗を立て、周囲を巻き込み、新しい仕掛けを生み出す機能が求められます。
- 分析・課題解決能力:
現代のスポーツマネジメントは、データに基づいた意思決定が主流です。
- 情報収集力・分析力: 膨大なデータの中から必要な情報を抽出し、論理的に分析する能力。データ分析ツールを使いこなすICT活用能力も重要です。
- 課題発見・解決力: 組織や事業が抱える問題点(集客の低迷、収益の頭打ち、チームの不振など)を的確に発見し、その原因を深く掘り下げ、具体的な解決策を立案・実行する能力。論理的思考力と創造性が求められます。
- リスク管理: 選手の怪我、不祥事、イベント中の事故、資金繰りの悪化、突発的なパンデミックなど、スポーツ業界には多くのリスクが存在します。それらを事前に予測し、対応策をシミュレーションすることで、被害を最小限に抑える危機管理能力が不可欠です。健康管理、個人情報保護、輸送対策なども含まれます。
- 倫理観と情熱:これまでのビジネススキルに加え、スポーツマネジメントの分野では特別な「資質」も求められます。
- スポーツへの深い愛情と情熱: スポーツそのものに対する強い興味と、その発展に貢献したいという情熱は、この仕事の原動力となります。
- 高い倫理観と誠実さ: 選手、ファン、スポンサーからの信頼を得るためには、公正性、透明性、誠実さを重んじる高い倫理観が不可欠です。特に、選手の人生やキャリアを預かる立場であるため、その責任は非常に重いです。
- 客観性: スポーツへの情熱を持ちつつも、ビジネスとして客観的に状況を判断し、冷静な意思決定を行うバランス感覚が重要です。
まとめ
スポーツマネジメントスキルは、大学のスポーツマネジメント関連学部やビジネススクールでの体系的な学習、そして実際の業界でのインターンシップや実務経験を通じて培われます。
スポーツマネジメントは、スポーツを愛し、その可能性をビジネスとして最大限に引き出し、社会に貢献したいと考える人々にとって、非常にやりがいのある分野です。
常に変化するスポーツ界の最前線で、能力を最大限に活かせる仕事が、スポーツマネジメントです。
この記事を通じてたくさんの方がスポーツマネジメントに対して興味や関心をもち、業界へ一歩足を踏み入れるキッカケになったり、『オールドルーキー』という名作ドラマを再視聴されるキッカケになれば幸いです。