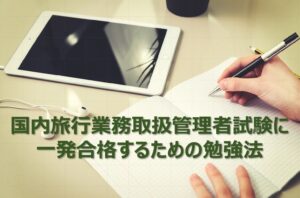利き手は補正するべきか?利き手の矯正とその個人的影響について

利き手はなぜ生まれるのか。
脳と利き手の関係から利き手矯正の歴史と風習、現代の考え方やクロスドミナンスの実践などを紹介。
利き手の矯正とその個人的影響
.png)
人間には「利き手」がある。
これは霊長類の中で人間だけにある特徴らしい。
そして地球上の9割の人が右利きで左利きはどこの国でも少数派なのだそうだ。
私はもともと左利きである。
幼いころは左手にクレヨンを持って一日に何枚も絵を描くお絵描き幼児だった。
ところが幼稚園に上がる少し前、祖母は右利き矯正を敢行した。
双方正座して紙をはさんで対峙し、祖母が「はい」と言ったら私が鉛筆をもってひらがなを書く。
その際に左手で鉛筆を持とうとするたび手の甲を叩かれる。
その訓練を経て気が付けば右で文字を書くようになっていた。
「やっと普通になった」それその時の祖母の思いだったに違いない。
野球でもそうだ。
右利きという「普通」にあこがれ始めていた私は、右利きだった兄に習って右バッターボックスに立つように心がけた。
しかしどうしてもボールを右手で投げることができなかったため、左投げ右打ちという希少な野球小僧が出来あがった。
-1.jpg)
高校時代のある日、あの幼い日の矯正の日々が頭の中の何かをねじ曲げて何かの通りを悪くしたのではないか、矯正がなかったら、英単語もすらすらと頭に入って決して忘れない優秀な頭脳に成長していたのではないか、成績が悪いのは利き手を矯正されたからに違いない。という根拠のない猜疑心が沸き起こり、左利きに〝逆矯正〟した。
そんなことにエネルギーを使うあまり大学浪人を経験することにもなったのだが、今もその疑念は晴れてはいない。
還暦を過ぎた私は左右どちらでも文字が書けるというどうでもいい特技を身に着けた。
パソコンの普及により文字自体を手で書く機会はめっきり減ってしまったが、左手で字を書く時は何となくだが脳とペンが直結してスムーズに文字が書ける気がしている。
今回,この機会を得て調べてみると、利き手の矯正には日本だけでなく各国に事情があり歴史があることが見えてきた。
果たして、利き手は矯正するべきなのかどうか、そして現代の考え方はどうなのだろう。
そんな思いをレポートにまとめてみた。
利き手が生まれる理由
-1024x779.jpg)
そもそも、なぜ利き手というものがあるのだろうか。
まだ科学的にも医学的にも完全解明されたわけではないのだが、ある研究者は理由の一つに脳の非対称性を挙げている。
多くの生物は左右二つの脳を持つが、右脳、左脳で働きに違いがあるのは人間だけらしい。
人の右脳は左半身をコントロールし、左脳は右半身をコントロールする。
理論や言語は主に左脳が司ることから、今左脳から出たその言葉を「手で書け」という信号は左脳から発信されると考えるのが自然なことで、結果右利きが多くなる。
一方、言語のプロセスに両方の脳を平等に使う人もいる。
中には完全に右脳だけを使う人もいるという。そうしたレアなケースの人が左利きとなるのだろうという考え方のようだ。
実際、手と脳の関係を調べたデータによると右利きの人の96%が言語系の処理を左脳でしていたのに対し、左利きはおよそ73%、両利きでは85%が右脳で言語系の処理をしていたとのことだ。
もう一つ、別の研究者は、胎内ではテストステロンという男性ホルモンが分泌されるのだがこのホルモンが利き手形成に影響するという説を唱えている。
胎児の段階でテストステロンが左脳の特定部位の発達を鈍化させ、右脳の対称部位を過剰発達させる。
その結果右脳は左脳より先に発達する。テストステロンの血中濃度レベルにより、左脳の後頭部の発達が異常に遅れ、左脳の正常な発達が妨げられることが左利きにつながるというのだ。
なにやら難しくてすぐさま逃げ出したくなりこのテーマを選んだことを後悔してしまうが、本来人間は皆右利きで何らかの異常事態が左利きを生むということなのだろうか。
この分野の研究者たちの中には左利きを「非右利き」と表現する人もいるということだ。
左利きであることのデメリットとして、右利きを基準に作られたこの世の中において、何かしら工夫しながら生活しなければならないことは多くのレフティが感じていることだろう。
しかしそれだけではない。言葉が出にくいという傾向があるという。
これまで、左利きは頭がよさそうとか器用そうなどと言われて踊らされていた感もあるが、言語障害があると聞くと穏やかではいられない。
慌てて『1万人の脳を見た名医が教える すごい左利き』(ダイヤモンド社刊)を書いた脳内科医の加藤俊徳先生関連のサイトをググってみる。
書かれていたのは、左利き独自の「ワンクッション思考」?
これか?! これが言葉を出にくくする元凶なのか。
ひるまずに読み進めてみる。
左利きは情報や考えをまとめて言葉にしようとするとき、ワンテンポ遅れがちになるという。(そういわれればそんな気もするが) 左脳は理論、言語を司るところで、右脳はイメージ情報を格納している場所といわれているが、右脳にあるイメージの情報はバラバラな状態で浮遊している。
一方左脳はグループやカテゴリー別にきちんと整理されている倉庫のようなものだそうだ。
右利きの人が何か言葉を発しようとする場合、きちんと整理された左脳庫にすんなり入って簡単に目的としていた情報を探し出してそれを言葉にすることができる。
しかし左利きの人はまずランダムな(乱雑な?)イメージ情報庫といわれる右脳庫に入ってから整然とした左脳庫に行かなければならないためアウトプットが遅くなるとのことだ。
少々脱線してしまったが左利きが生まれる理由は胎児のとき、あるいは出産時に脳に受けた傷が原因とするリポートもあった。この記事にも軽くショックを覚えた。
利き手の矯正の歴史とその背景
-1024x682.jpg)
人間の9割は右利きというが、国によってばらつきがあるようだ。
アメリカでの左利きの割合は1.8%。両利きは28パーセント。イタリアでは左利きは5.8%、両利きはおよそ30%。
反対に左利きが多い国としてはオランダ、ニュージーランド、ノルウェーが約15%と言われおり、わが国でも左利きが11%と世界平均よりやや高いというデータがあった。
そして国々で事情は違えども風習や文化の陰で左利きは容赦なく矯正されてきた。
日本に目を向けてみると、書道や剣術、箸使い、和服の着付けなど、伝統的な日本の習慣では右手を使うことが標準とされており、そもそも左利きへの対応という考え方自体が存在しなかった。
そのため左利きは「不自然」だったり「無作法」と見なされ、家庭や学校でも矯正されるのが一般的だった。
当時の日本社会における「伝統を重んじる」価値観や、集団の規範に従うことが最重要視されていたことが影響していたと考えられる。
-1-683x1024.jpg)
一方、西洋においても左利きに対する偏見や矯正の歴史がある。
特に中世ヨーロッパでは、左利きは宗教的に「悪」と関連付けられており、キリスト教の影響が強かったこの時代、右手は「神聖」や「正義」を象徴し、左手は「不吉」や「悪魔的」とされていた。
ラテン語の「左」を意味する単語 sinister(シニストラ) は、「不吉」や「邪悪」という意味も持ち、左利きに対する否定的なイメージが強かったことがうかがえる。
この宗教的な偏見は、日常生活にも多大な影響を与え、学校や家庭で左利きを矯正することが当たり前のように行われていた。
19世紀から20世紀初頭にかけての欧米の教育現場でも、左利きの子供に対しては、右手で書くよう厳しく指導され、左利きを放置すると「学習能力が劣る」「社会的に不利」といった考え方が支配的だったようだ。
ちなみに「インドの人は右手でご飯を食べ左手でお尻を拭く」子供の頃よく聞いた話だがこれは宗教的なことではなく緩やかな慣習で、左利きの人はその逆でやっても何ら問題はないのだそうだ。
利き手の矯正方法とその時期
-1024x731.jpg)
利き手矯正をするべきなのか、しないほうがいいのか、これは特に左利きの子をもつ親なら誰もが考えることだろう。
大人になってからでも矯正を考える人はいる。
その是非は別のページで紹介するとして、ここでは利き手を矯正するならどういう方法があるのかに絞って書き出してみる。
- 食事:箸やフォークを持つ手を替えて練習する。
- 字を書く:ペンを普段と違う手で持ち、簡単な線や図形を書く練習から始め、徐々に文字を書く練習に移行する。
- 歯磨き: 違う手で歯磨きを試みる。
- 身体洗い:石鹸を違う手で使う。
- スマートフォン:普段使わない方の手で電話をかけてみる。
・子どもの利き手矯正
子どもの利き手は4歳ごろに固定されると言われている。しかし、利き手矯正は、特に幼少期に無理に行われた場合、心理的なストレスを伴うことがあり、集中力の低下や情緒不安定を引き起こす可能性があるため注意が必要である。矯正時期としては概ね10歳ごろがよいとされている。その頃になると言語処理をする左脳の発達も落ち着き、左右の脳のバランスが取れてくるためこの時期が良いとのことだ。
・大人の利き手矯正
利き手を矯正することで記憶障害や空間失調症吃音障害などを引き起こすなど副作用が発生する可能性があることが報告されているため、無理な矯正は注意が必要だ。 しかし、利き手と反対の手を使うことで自制心の鍛錬や怒りの感情をコントロールする可能性もあるので全てを一度に矯正するのではなく社会生活をする上で必要に応じた柔軟な矯正が望ましいと多くの記事に書かれていた。
利き手に対する考え方の変化
-1-1024x682.jpg)
1950年代以降、欧米では利き手の矯正に対する見方は徐々に変化を見せ始めたようだ。
心理学や教育学の発展により、利き手は脳の左右差による自然なものであり個人の特性であることが理解されるようになってきたためで、無理な矯正が心理的な負担を引き起こすことが指摘されるようにもなってきた。
また、矯正がきっかけで起こる学習障害や精神的ストレスが問題視され、自然な利き手を尊重する風潮が広がりはじめたともいわれている。
少し遅れて、日本においても、高度成長期の終盤頃には(私の肌感覚でも)左利きに対する社会的な圧力は緩和され、左手で箸を持つことや左手で文字を書くことが徐々に受け入れられるようになりはじめたように思う。
特に現代では、利き手を無理に矯正することは教育的にも推奨されておらず、個々の多様性を尊重する考え方が主流となっている。
今季限りの引退も囁かれているスペインのスーパーテニスプレーヤー ラファエル・ナダル選手。
元コーチで叔父のトニ氏の話では、彼はもともとどちらの手でもラケットでボールを返すことが出来たそうだ。
だれも矯正をしたことはないと。彼の自然な選択が世界一の選手へと導いたのだ。
利き手を選ぶという考え方=クロスドミナンス
画像-769x1024.jpg)
そうはいっても社会はやはり右利きが基準であることは事実である。
陸上競技場のトラックを時計回りに回る種目はない。
野球において左利きが守備に就くことができる内野はピッチャーかファーストだけだ。(ベイブルースは左利きのキャッチャーだったそうだが)、バイオリンをはじめ古典楽器は右が標準仕様だ。(ギターはもちろん右利き用が主流だが左手仕様のものも数が増えてきた)カメラのシャッター、自動改札のタッチパネル、エレベーターのボタンもやはり右利きを基準に作られている。
-1-1024x768.jpg)
どこまで行っても左利きは社会生活においてマイノリティであることには違いはなく、右利きに合わせて矯正することが当たり前と思われていたのだが、最近にわかに脚光を浴びているクロスドミナンスという考え方があることを知った。
クロスドミナンスとは、左利きの人が、右利きのために作られたこの社会に順応するために、使う手を自らの意思で変えることを指す場合が多い。が、右利きの人が何か一部分だけ左手を使うようにすることにも対応する。
一般的にパソコンのマウスは右側に置かれている場合が多い。
したがって左利きの人もマウスは右で持つといった具合だ。日本語では「交差利き」と表現される。これはどちらの手も同じようにうまく使える人をいう「両利き」とは意味が異なる。
クロスドミナンスは後天性が多い、その理由は右利きに適応した社会を効率よく過ごすため左利きの人が右利きに矯正する割合が多いからだ。
スポーツにおいては言葉こそなかったがクロスドミナンスは古くから取り入れられてきた。
野球ではバッターは一塁に向かって走る。よって少しでも走る距離を短くするため左打ちに変える選手が多い。
最近では筋力バランスを良くするためという指導者もいるが、右打ちから左打ちへの転向は矯正ではなくクロスドミナンスの結果だ。
生まれつきであれ、後で身に付いたものであれクロスドミナンスであることが自分になじんでいるのであればいうことはない。
小学校の頃、えんぴつは右だけど、消しゴムは左手を使うとか、ハサミは右だけどカッターは両方使えるというクラスメートが何人かいた。
今思うと彼ら彼女らはまさにクロスドミナンスだったのかもしれない。
-1-1024x682.jpg)
両方の手を使うことで左右の脳が鍛えられ発達するため思考力向上、作業効率のアップにつながる。
本来右利きの人は右脳が活性化され「ひらめき」や「アイデア」が出やすくなる。など、そのメリットも高そうだ。
おわり
-1-1024x683.jpg)
右利きの人は論理的で分析的な能力を持つとか、左利きの人は空間認知や創造的思考があるなどと言われる。
だが、利き手がその人の性格や個性を決定するものではもちろんない。
個人の性格や個性は遺伝や環境、教育などの他の要因とも相互に影響し合い形成されていくものだ。
利き手の選択は自然に任せること、そして本人の意思に任せることも重要だと感じた。
今の世の中、利き手を変えることに「矯正」という字を使うのはもはや時代遅れかもしれないというのが感想だ。
私事だが、実はクロスドミナンスも両利き訓練も十分すぎるほどしっかり経験していたではないか。
しかしながら脳が活性化された実感はない。
祖母の「矯正」だ。
やはり祖母の矯正敢行がもう5~6年後であれば素晴らしい脳を持つ自分になっていたかもしれないと思うと悔やまれてならない。