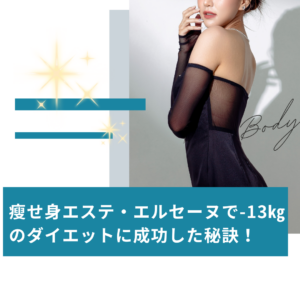医療秘書実務能力検定試験1級に一発合格する為のマル秘勉強法
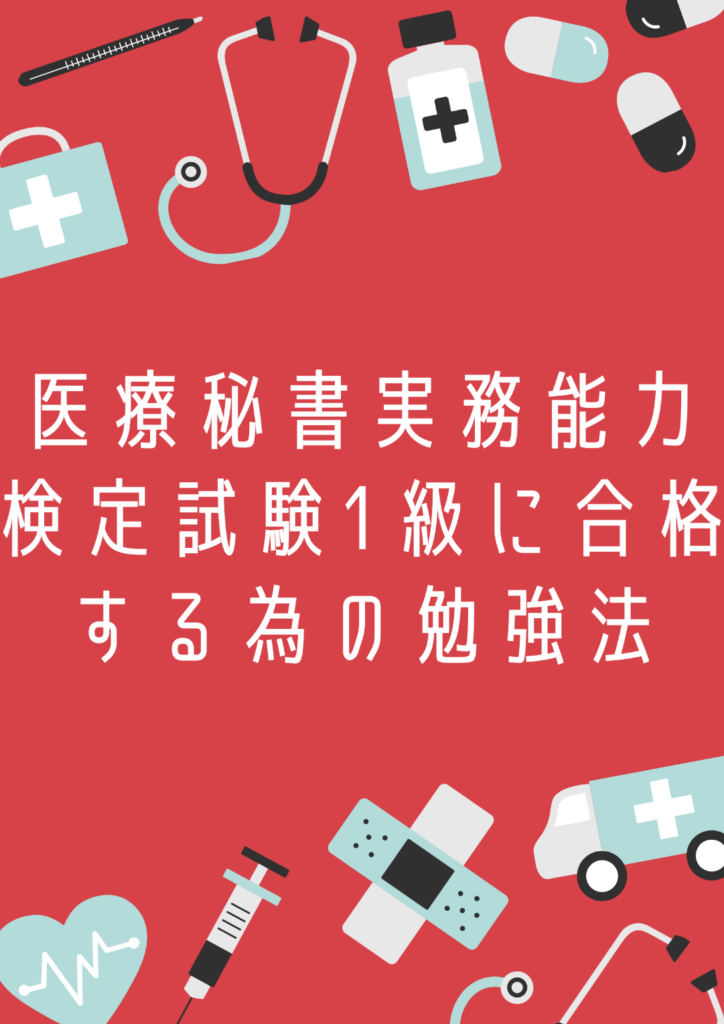
この記事では医療秘書として働く上で有利となる、医療秘書実務能力検定試験1級資格合格へ向けての勉強で気を付けたいポイントなどを解説いたします。
試験内容、難易度、合格率も含めた内容をまとめました。
現場で即戦力となれるよう頑張りましょう。
医療秘書とは?

秘書というと、一般企業では役員や社長をサポートする仕事のイメージがありますが、医療秘書は、医療機関で病院経営者や医療従事者をサポートすることがメインの仕事です。
医療従事者のスケジュール管理、電話やメール対応、各種手配など多岐に渡った仕事となっています。
また、病院内での職業で混同されやすい職業が2つあります。
1 医療事務
病院窓口の要となる受付や患者様対応、そしてレセプト作成スキルが重要視される診療報酬請求に関わる計算業務をメインにしています。
2 医師事務作業者
医師の行う事務業務のサポートをメインに行います。カルテ入力や診断書作成、レントゲン画像のデータ管理といった、医師が診察等で使用する書類やデータの作成、補助業務がメインの業務となっています。
このように、患者様への接客対応や計算業務、医師メインの補助業務に比べて、医療秘書とういう仕事は、医師や看護師、院長、取引先など院内院外問わず幅広い職業の方々との調整役を担うため、人との関わりが重要になる職業です。
調整や各職業の方と意思疎通をとるためには、事前に医療に関わる専門用語や略語を知識として身に着けておく必要があります。
医療秘書実務能力検定試験で勉強する範囲は、現場で活かせる知識が身に付きますので日々勉強に励みましょう。
医療秘書実務能力検定試験とは?
医療秘書教育全国協議会が認定する資格です。
3級、2級、準1級、1級と級位があり、この試験に合格すると医療秘書として働く上で必要とされる専門的な知識と技能を得ているとして議会から認定されます。
実際には、必ず必要な資格ではありませんが、医療機関で働くということは、人の命を預かる仕事ということです。
資格を有するための勉強を事前にしておくことで、専門用語が飛び交う現場での緊急サポート業務が必要になった時に必ず役に立つことでしょう。
また、医療秘書実務能力検定試験は民間資格のため、受講するために必須となる資格は存在しません。
よって、学校に入る必要はなく、独学で勉強して受験することも可能となっています。
3級~1級までの級位の中で初心者の学習しやすい3級から始め、段階的にチャレンジできる仕組みとなっているので、自分が勉強する環境の元、自分のレベルに合わせてスキルアップしていきましょう。
しかし、1級は一番高い級位ですので難易度が高く、実務経験を積んでからの受験がオススメです。
試験内容
医療秘書検定には、3つの領域があります。
領域Ⅰ:医療秘書実務、医療機関の組織と運営、医療関連法規
領域Ⅱ:医学的基礎知識、医療関連知識
領域Ⅲ:医療事務
となっており、いずれにしても1級問題は難易度MAXです。
答案形式
答案形式はマークシート形式とレセプト作成です。
試験時間と合格基準
試験時間は150分です。
合格基準は領域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲそれぞれに100点ずつ配点されている中で、3つの領域の正解合計が180点以上であること。
なおかつ、それぞれの領域の正解が60%以上の場合のみ合格となります。
各領域で満遍なく得点することが求められることが分かります。
各科目の勉強内容〈領域Ⅰ〉

①医療秘書実務
医療秘書として複雑な業務を判断、遂行する行動能力や、業務全般の適切な連絡調整並びに各種病院に関わる申請書や届出作成について専門的レベルの知識を得ているか判断する内容です。
特に病院では、個人情報の取り扱いや事務方含めて仕事のミスが一大事に直結する可能性が非常に高いです。
インシデントやヒヤリハットなどが起こった際に報告書、申請書を作成することにより次の業務で同じミスが起きないよう取り組む義務があります。
医療秘書だけではなく、病院で働く様々な職業の人が該当する事案もありますので、どんな場合に何が必要で、適切な行動パターンは何かを把握しておくとよいでしょう。
②医療機関の組織と運営
病院規模によっての組織の在り方、組織運営に関わる内容を理解しているか、経営分析等について処理する能力と医療情勢、社会情勢についての理解があるかを判断する内容です。
病院は基本的に、診療部門、看護部門、医療技術部門、事務部門の4つの部門に分かれています。
各部門が病院にとってどんな役割を担っているのか、病院はどんな組織構造の元で運営がなされているのか、規模と職業を絡めた全体像を把握しているかが注目ポイントとなっていますので、押さえておくようにしましょう。
➂医療関連法規
医療分野に関係する法規について民法を含めた知識を持ち合わせ、法律の取り扱いを心得ているか判断されます。
病院を運営していくにあたって、『医療法』という医療施設の開設、管理に関する事項が定められた法律があります。
この他に医師法、薬師法、臨床工学技士法など医療従事者の資格に関する法律など多種多様な法規が密接に医療機関に関係します。
この法律は、どのような規定が定められているのかを把握する必要があります。
もちろん、全て暗記することに越したことはないですが、少しハードルが高く感じてしまうかもれません。
そんな時は、答案形式がマークシート形式ということを最大限に活かしましょう。
問題で問われていることに対して違和感のない選択肢を選べるくらいの最低限の知識量を身に着けておくことを意識しましょう。
心折れずに勉強に取り組むことが一番大事です。
各科目の勉強内容〈領域Ⅱ〉

①医学的基礎知識

傷病や原因疾患、症状と治療方法などの人体の仕組み、臓器ついての広範な専門的知識を問われます。
医学の知識や解剖学、生理学や疾患、医療というジャンル全般での知識が特に問われる領域です。
出題される範囲が非常に幅広いので出題問題を予測して的を絞った勉強方法だと、失敗してしまう可能性があるので気を付けましょう。
また、人体構造や身体の各器官の役割を問われることもあるので、苦手だと感じる人は徹底的に勉強し、細かく対策していきましょう。
過去問題集では、傾向やどんな穴埋め方式がとられているのかを把握しておくとよいかと思われます。
②医療関連知識

医療、医療用語についての知識、薬効別薬品名に対しての適応症と関連した知識、診療録・看護録の内容理解を問われます。
医療関連知識は、特に実績経験がある人に有利な問題かと思います。
医療現場にいると、いたるところで医療用語が飛び交っているので業務をしていると自然と覚えていきます。
医療現場のスタッフと連携をとる際は、医療用語や薬品名を知っていないと業務にならないことがほとんどなので、現場にいる強みとして試験にも活かせること間違いなしです。
ただ、診療録や看護記録の定めについては、働いているうえで深く関わることは少ないかと思います。
法律と同じように目的や必要性、定めがあることを踏まえて、テキスト過去問題集での反復学習を忘れないように心掛けましょう。
各科目の勉強内容〈領域Ⅲ〉

①医療事務
社旗保険各法及び公費負担医療各法についての知識、レセプト内容の事務点検、レセプト作成、施設基準についての幅広い理解と知識、診断軍分類別包括支払制度(DPC)についての請求方法など医療事務業務の要である計算業務について、細かく問われる領域となっています。
医療事務に関する領域Ⅲの試験は、参考書やノート電卓を持ち込めます。
ただ、内容はⅠ、Ⅱに比べて医療秘書の仕事よりも、医療事務の仕事で必要になってくる知識ばかりなので特殊な科目です。
医療秘書としての実務ではあまり触れないところになっていますので、こちらもテキストを利用した反復学習での勉強方法が一番有効的です。
レセプトとは、医療機関が保険者に請求する医療報酬の詳細を記した明細書の名称です。
診療報酬明細書とも呼ばれています。
患者様が受けた診療内容やかかった費用の内訳が記載されており1か月ごとにまとめて作成されています。
現代では、医師や看護師がパソコンに残した患者様に対しての診療内容が反映されたレセプトを医療事務が添削していく流れとなっています。
検定試験のレセプト問題では、点数表を必ず持参して挑んでください。点数表がない状態だといくら勉強したとしても、絶対に解けません。
内容としては、対象患者様のレセプト内容が保険者に提出される内容として記載漏れがないか、誤った情報が記載されていないかを確認することとなっています。
患者氏名から疾患名、薬品名、診療日数、診療日、各保険点数と確認する箇所が細かくなっていますので、細部まで見落としがないよう気を付けましょう。
レセプトは、経営で重要な資金源となる費用の明細書となっているのでとても重要です。
幅広い知識が問われる本試験ならではの試験内容とも言えるでしょう。
過去問題集で、レセプトに関する作成や添削の問題数をできるだけこなすことがカギとなってくると思いますので、日頃からたくさん問題を解いていきましょう。

施設基準とは、厚生労働大臣が規定に基づいて定める基準です。
医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面などを評価し、医療機関が提供する医療サービスの質と安全を保障すること目的としています。
そして、一部の保険診療報酬の算定要件としても定められているので病院経営として得られる報酬も変わっていきます。
届出を提出する際に、該当の施設基準の条件を病院が満たしているのか、届出の記載方法は合っているか、締め切り期限はいつか、などを確認する必要があるので必要事項に関しての知識は頭に浮かべられるくらいにはしておきましょう。
診断軍分類包括評価(DPC)とは、入院患者様に対して扱われる診療報酬請求の1種です。
患者様の治療内容をもとに厚生労働省が定めた診断群分類点数に基づいて、1日あたりの包括医療費を算出する医療費の計算方式なので、請求業務の中でも複雑な仕組みとなっています。
他の請求方法との違いや診断軍分類包括評価(DPC)を使ったレセプトの請求内容が理解できるところまで勉強しましょう。
また、この計算方式を導入するにあたっても厚生労働省が定める施設基準を満たす必要があるので、必要条件も押さえておくとよいでしょう。
領域Ⅰ~Ⅱはマークシート方式での試験なので簡単かと思いきや、問題文の日本語のニュアンスが違う点や、似通った選択肢がある可能性が高いので過去問題集の問題文や答えを丸暗記は危険です。
ひっかけ問題の落とし穴があるかもしれないので、日頃から制度の仕組みや内容を理解できるよう心掛けましょう。
領域Ⅲは、医療秘書の実際の業務とはかけ離れているように感じますが、幅広く知識を身に着けておくことは医療秘書にとってとても重要なことです。
いつ、誰が、どんな質問してきてもスムーズに業務が遂行できるよう励んでいきましょう。
自分に適した環境で勉強しよう
言わずもがな、専門分野に特化した授業を受けることができるので勉強の努力量にもよりますが、一番合格への道が近い環境といっても過言ではないでしょう。
医療秘書を学ぶことができる専門学校に入校している人は、試験に特化したカリキュラムの元、授業内容の重要点を復習し自分の中へ落とし込むことを意識しましょう。
学校によっては、試験に備えて小テストが出題されるところもあるので、現在の知識量を計る意味で活用していくと、とても有効的です。
環境に甘んじることなく、日々テキストに向き合いましょう。
また、『病院実習』という病院での職業体験のようなカリキュラムを組む専門学校が多く存在します。
実際に病院で働かせてもらえる体験ができ、普段入れない場所を現場のスタッフさんが説明しながら見学させてもらえる貴重な体験もできるので、学生として訪問することの強みを活かし、現場の雰囲気を学びながら体験したことを試験に活かせるように励みましょう。
独学での勉強

一人で勉強することの難しさがありますが、一番費用をかけずに受験に臨むことができる勉強法です。
医療秘書検定自体は、独学でも合格可能な試験のため、まずはテキストと過去問題集を集めることなど勉強する準備から始めていきましょう。
ただし、3~2級のテキストはネットや書店で手軽に手に入りますが、準1級・1級の過去問題集などは医療秘書教育全国協議会の事務局にて販売しているので注意です。
直近過去5回分までの過去問題集が販売しているので、医療秘書教育全国協議会の公式サイトから申し込み方法を確認し、購入申請の手続きを踏みましょう。
独学だと1~2年ほど学習時間が必要になることもあります。
医療秘書の現場で実際に仕事をこなしながら資格の勉強をしても、決して遅くはありません。
実務経験を活かしながら知識を蓄えていくのも一つの方法かもしれません。
通信講座を利用しよう

医療現場で就業した経験が全くない場合、医療秘書技能検定を独学で行うことにハードルが高いと感じる人もいるでしょう。
そういった場合は、通信で受けられる講座を受講する方法をオススメします。
初心者でもスムーズに勉強できるよう工夫されたテキストや動画配信で講義を聴くことができるなど、専門の講師と一緒に学ぶことができるため万全のサポートの元、勉強に取り組むことができるでしょう。
ただし、独学の時と同様に1級試験の難易度は高いため、実務経験を積みながら勉強と試験に臨むことをオススメいたします。
合格率

1級合格率は25%前後です。
普段から反復学習を心掛け、実践経験を積んでいる方なら手が届かないわけではない数字だと思います。
本番特有の緊張感のある試験空間で、ケアレスミスなどしないよう気を付けましょう。