国内旅行業務取扱管理者試験に一発合格するための勉強法を徹底解説
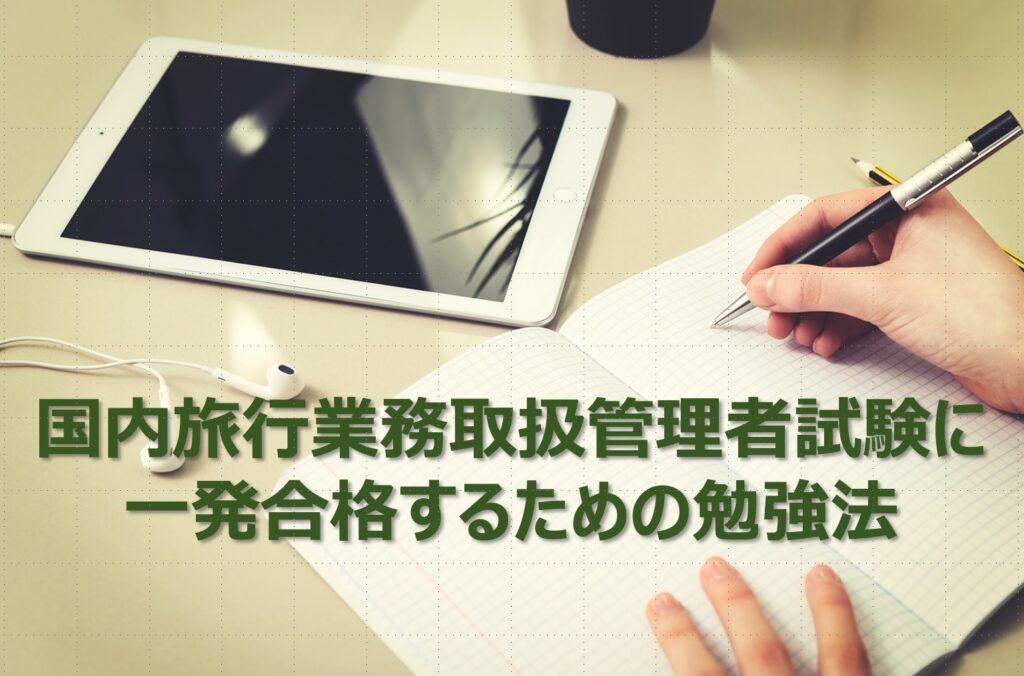
はじめに
-1024x682.jpg)
旅行業法の第一章「総則」第一条(目的)に「旅行業法は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする」と書かれています。
この法律は旅行業等を営む事業者を規制する法律です。同時に旅行者を保護することも目的にしています。
人の命を預かるということ、時に大きなお金を動かす場面があること、といった観点から、旅行業は誰でも登録さえすれば明日から出来てしまう事業ではありませんよ。
ちゃんと国家試験を受けて合格したものでないと旅行商品の販売はしてはいけませんよ。というのが日本の考え方です。
特に資格なく出来てしまう国もあるようですが、日本で旅行業登録をするためには国家資格を得た旅行業務取扱管理者を選定して登録することが義務付けられています。
また、営業所を複数箇所展開する場合には各営業所に1人以上の旅行業務取扱管理者を置く必要があります。
旅行業務取扱管理者資格には、国内、海外の両方の旅行業務を取り扱うことができる「総合旅行業務取扱管理者資格」と国内の旅行業務のみを取り扱うことができる「国内旅行業務取扱管理者資格」があります。
さらに地域の観光資源の活用促進を目的として2013年に「地域限定旅行業務取扱管理者資格」も新設されました。
このことでもこれからの旅行需要に対する国の期待がどれほどの事なのかが見て取れますが、本稿ではタイトルにもある通り「国内旅行業務取扱管理者試験」への合格に絞って進めていきます。
資格試験は社会生活でスキルアップやキャリアアップの必要性を感じて取得しようとする人がほとんどではないかと思います。(中には資格取得が趣味の方も一定数いらっしゃるとは思いますが)仕事を持ちながらのため時間に限りがあるのは皆同じでしょう。
試験範囲のすべての項目についての詳しい解説などは誌面の都合もあり出来かねますが、空き時間に一読いただければこの資格試験に対する取り組み方がおぼろげながらでも理解していただけるものと考えています。
ちなみに、第一章「総則」にある第一条(目的)は必ず出題されます。これを完璧に覚えるだけで4点はいただきです。
来年の9月には万全の体調で試験に臨んで、ぜひこの資格を勝ち取ってください。
目標設定と合格基準
-1024x576.jpg)
国内旅行業務取扱管理者試験には年によってばらつきはあるものの、だいたい毎年1万人前後が受験します。
合格率は30~40%程度。国家試験の中では中程度の難易度とされているようです。
試験はマークシート形式で、試験時間は120分です。科目は「法令」(25問100点)、「約款」(30問100点)、「国内旅行実務」(32問100点)の三科目。(問題数は目安)全科目合わせての得点率60%以上が合格点となっています。
実施主体は環境庁で一般社団法人全国旅行業協会が事務代行機関となっています。
受験までの凡そのスケジュールとしては、
・受験願書受付⇒6月下旬から7月上旬
・試験日⇒9月上旬の日曜日
・合格発表⇒10月下旬から11月
これらは年によって違いますので試験地と合わせてその年の関連ホームページなどを参考に正しい日にちを知っておくようにしてください。
費用は5,800円です。銀行振り込みになります。値上がりの可能性はゼロではありません。
勉強時間は人によって異なるでしょうが、とにかく覚えることが多いのでその年の3月くらいには始めることをお薦めします。
勉強方法
-1024x682.jpg)
1 資格スクール
費用はかかりますがスクールが立てたカリキュラムに沿ってその日その日習ったことを覚えていけばいいので、自ら学習スケジュールを立てる必要がない分覚えることに専念できます。近年の傾向にも詳しく、出題や回答内容についても丁寧に教えてくれます。本人の学習が遅れても必ず振り返りの機会がありますしスクールとしても合格率を上げる使命がありますので必死におしりをたたいてくれるでしょう。
2 通信教材
資格スクールほど費用はかからないかもしれませんが意志を強く持たなければ挫折しやすい選択です。YouTubeなどで無料の講義もありますし、教材の質は自分で確認しないと命取りになることもあります。全教科のプログラムがしっかり作られている教材であればスクールに通うより自分のペースで学習できる分、効率的かもしれません。
3 独学
そもそも独学を選択する人は、意志が強く独学で何かを成し遂げた経験のある人か、最初からやる気の薄い人かどちらかではないかと思います。独学を選ぶのであれば参考書は一冊に決めて、過去問を解くことにエネルギーを使うやり方が良いのではないかと思います。試験日から逆算して計画を立て、無理なく自分管理をしていきましょう。
サイトを検索すれば時間管理法や集中力の高め方など素晴らしいアドバイスがたくさん出てきます。あれこれ惑わされることなく、合格した後の自分の生活の変化を想像しながら楽しく勉強できる環境を作っていってください。
各教科の出題のポイント
-1024x683.jpg)
ここから先は一発合格を目指す本稿独自の〝他では知ることができない〟独断と偏見に満ちた感もある試験の最重要出題ポイントを教科ごとに見ていきます。
長くなりますので用語の解説は大胆に割愛します。
お手持ちの参考書や過去問題集などと照らし合わせながら読み進めて行ってください。
<法令>
最初にお話しましたように、旅行業法の第一章「総則」第一条(目的)は必ずと言っていいほど出題されます。出題パターンは「目的として該当するものを以下から選べ」といった時もありますが、多くは引っ掛け問題です。例えば目的の一つである「旅行者の利便の増進」を「旅行業者の利便の増進」として記しておいて、目的として間違ったものどれかを答えさえるものです。6つある目的は語句ごと丸暗記してください。また、そもそも旅行業法は旅行業者を規制するもの、旅行者を保護するものであることを強く意識づけておきましょう。
第三条(登録)に関して、旅行業の業務範囲は第1種、第2種、第3種、地域限定及び代理業の5種類で異なります。ここで多いのはそれぞれの違いを問う出題です。登録行政庁がどこなのか、各種の財産的基礎はいくらか、営業保証はいくらかなどです。財産的基礎は通帳にある金額であり、営業保証金は供託金を指します。また、各範囲で出来る業務を完全に理解しておきましょう。第3種で募集型企画旅行を行う場合、日本全国どこでもツアーが組めるわけではありません。出発地と帰着地は自らの営業所がある市町村、巡ることができる地域はその市町村とそこに隣接する市町村内だけです。
第11条の旅行業務取扱管理者の職務の10項も一言一句丸暗記が必要なほど重要です、ここでの出題で多いのは営業所の旅行業務取扱管理者が不在の場合について。契約の締結は一切できないが、「業務そのものが一切できない」わけではありません。
契約規則第13条(広告の表示事項)14条(誇大広告をしてはならない事項)も必ずと言っていいほど出ます。
第12条の9(標識の提示)で標識の提示場所について「『公衆』に見やすいように」提示する必要があるのですが、公衆という文字はここでしか登場しません。つまり他の出題で「公衆」という文字が出た場合はそれが間違いのサインとなります。
第13条(禁止行為)では、ここ十年で民泊が急増してきた関係で「宿泊サービスを提供するもの」についてよく出るようになりました。
第18条(業務改善命令)では観光庁長官ができる措置についてよく尋ねられますが、5つある項目は丸暗記が必須です。特に1項「旅行業務取扱管理者を解任すること」で解任部分を「解雇」と記されたりします。その場合は間違いとなりますね。
こうした引っ掛け問題のやり口はこの項に限らず他の設問でも過去問において随所に散見されます。しっかりと語句に反応するように練習しましょう。
旅行業に該当するかしないか問題も重要です。旅行業と判断するポイントは以下の3つです。
・報酬(お金をもらって)
・一定の行為
・事業(お仕事としている)
では、その中で一定の行為とは何でしょうか。これは以下の3つで、
・基本行為:輸送、宿泊
・その他のサービス:レストラン手配、ゴルフ場手配など
・便利なサービス:旅券代行、ガイドの手配など
となります。お金をもらってこれらの行為をおこなって事業をすることがすなわち旅行業なのです。
上の「基本行為」を行って営業する場合はもちろん旅行業が必要です。「基本行為+その他のサービスや便利なサービス」の場合も旅行業は必要です。「その他のサービス」だけの場合や「便利なサービス」だけの場合、旅行業は不要となります。
法令からは25問が出題されますので各項共しっかり覚えてください。また、設問内で「○○はかならず必要だ」などの語句が出たらちょっと疑う癖をつけておきましょう。前出例のような出題者のミスの誘い出しに乗らないようにしましょう。有効期限なども注意が必要です。旅行業登録の有効期限は登録のその日から起算して5年と決められていますが、更新登録は満了日の翌日から起算します。この起算日、期間問題は様々な申請シーンなどで登場します。起算日と合わせて日数を把握しておきましょう。
理解が難しい「弁済業務保証金」について出題されたら・・・捨てる覚悟も必要かもしれません。
法令はとにかく覚えさえすれば満点がとれる教科です。そのため本稿でも力が入ります。過去問や模擬試験で引っ掛けどころを発見してにんまり出来たら合格は目の前でしょう。
-1024x682.jpg)
<約款>
約款とは業者と顧客が、さまざまな取引を行うためにあらかじめ決められた約束事です。本来ならば、すべての取引は業者と顧客という当事者同士が話し合い、意見が一致した段階で契約を締結すればいいのですが、旅行業者が毎回このような手続きを大量の顧客を相手に交わすことは現実的ではありませんよね。そこで取引で予想される問題点をあらかじめ考慮してまとめた約束事が約款なのです。
出題は「標準旅行業約款」から80点分が出題されます。航空会社、バス会社、船会社、宿泊業者、JRの各約款からは一問ずつが出題されます。ただし、世間を揺るがすほどの大きな観光関連事故があった翌年などはその部分が厚く出題されることがあります。
標準旅行業約款のうち、約7割が「募集型企画旅行」に関する問題です。いわゆるパッケージ旅行についてです。法令同様、期限に関するものは出題されやすい傾向にあります。契約の締結、変更、解除などは起算日が旅行開始日の何日前なのか当日なのか、そこから何日間後にどのような措置がなされるか。といった内容です。覚えるしかありませんので確実に覚えておきましょう。
「旅程保証」からは2問出ます。難問が多いです。「契約内容に重要な変更が生じた場合に旅行業者は一定の変更補償金を旅行者に支払う」というのが旅程保証の概要です。旅行業者の責任でサービスが受けられなくなった場合は、旅程保証ではなく損害賠償にあたります。
旅程保証はオーバーブッキング状況で起こることが大半です。
「契約書面ではビジネスクラスだったがエコノミークラスに変更されたケース」などが旅程保証に該当します。この場合は補償金を払うだけでなく差額も払い戻します。こうした内容を旅行中の出来事例として記述する問題もあり、つい必要な語句を見落とすといった失敗に陥る場合があります。
ちなみに、ホテルに関しては格下クラスから格上ホテルに変更となった場合も旅程保証は発生します。
理由は変更前のホテル側近くに友人が住んでいるためこのツアーを選んだとか、ホテルの格ではなくそこのレストランが好きだったからこのツアーを選んだなど単純に金額的価値とは違う意識でツアーを選択したケースが考えられるからです。
-1024x686.jpg)
「受注型企画旅行」は、修学旅行などの団体旅行がこれにあたり、ここからは2~3問が出題されます。
その他、毎年2~3問必ず出題されるものに「特別補償規程」があります。旅行者が企画旅行中に生命、身体、手荷物に被った一定の損害に対して、あらかじめ定める額の補償金や見舞金を支払うことを指します。
様々なケースと補償対象があり覚えるのも一苦労です。メガネは補償対象になり得ますが、コンタクトレンズは対象にならないなど覚えやすいものもあります。
-1024x680.jpg)
<国内旅行実務>
乗り物の運賃と運賃約款に関する問題、それと地理問題を合わせて国内旅行実務です。
多くの人が直面する最大の難敵はJR運賃でしょう。
100点満点のうち、50点が地理。50点が乗り物に関する問題となりますが、場合によってはその50点のうちJR運賃の問題が25点分を占める年もあります。
区間距離や運賃表を覚える必要はありませんが料金算出におけるJRの理論を理解し、覚え、実践で使えるようになるためには相当の時間を要します。
新幹線も在来線もあり特急列車もあります。乗継割引の対象だったり、なかったり、大人だったり子どもだったり、シーズンによって違ったり・・・勉強方法で独学を選んだ方も、JR運賃に関しては有料の動画配信を受講したりYouTubeを丹念に見て理解を深めることをお薦めします。
国内観光地理における勉強のポイントは…正確に覚えることです。
各国立公園、世界遺産(自然遺産、文化遺産、農業遺産など)、主な工芸品・郷土料理・博物館などの文化施設、また温泉、半島、岬、山、湖、都市などと県名を結びつけて覚えることは必須です。主な祭りの開催月なども覚える必要があります。
ルート問題も出題者には人気です。白地図の線(ルート)上にない観光地を選ばせたりします。
県境付近の観光地を覚える場合はさらに注意が必要でしょう。
写真問題も好まれます。モノクロ写真を問題用紙に載せてこれは何かを選ばせます。
観光地と関連語句もよく出題されます。
観光地⇒「富士五湖」に対して、関連語句⇒「山中湖⇒最大、河口湖、西湖⇒クニマスの生息が確認された、精進湖⇒最小、本栖湖⇒最深。逆さ富士」
-1024x683.jpg)
観光地⇒「熊野三山」に対して、関連語句⇒「熊野那智大社、熊野速玉大社、熊野本宮大社の三つの神社の総称。熊野那智大社の奥に位置する那智の滝は直瀑としては落差日本一。日本三大名瀑の一つ」
-1024x682.jpg)
といった具合です。しかしこうした関連語句はヒントにもなっているので楽しく覚えられそうです。
地理は毎日コツコツ楽しみながら勉強することが合格への近道です。
おわりに
-1024x682.jpg)
試験時間120分に対して問題のボリュームは多めです。
時間があれば解答できたのに~、という声は毎年聞かれます。
試験までの最後の2週間は過去問題や模擬問題を時間内に解き切ることに徹してください。
もし、最後の1週間になってもJR問題で足踏みしているようであれば、思い切って捨てる選択肢もありです。(当日白紙提出はぜったいダメです。どこかをマークしておけば当たるかもしれません)その分、地理や法令など直前まで覚えることに徹してみてはいかがでしょうか。
試験は逃げません。一発合格が無理でも、二発目で合格すればいいではないですか!
そんな思いで心を軽くして試験に臨んでください。検討を祈ります。

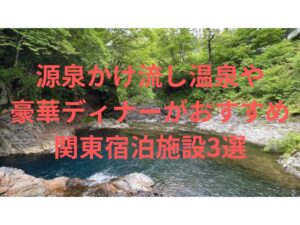
-1-300x200.jpg)