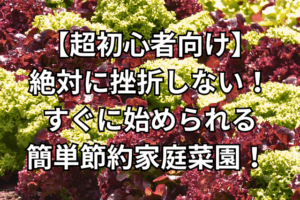日本化粧品検定1級に一発合格した体験記|勉強時間・教材・おすすめアプリを徹底紹介
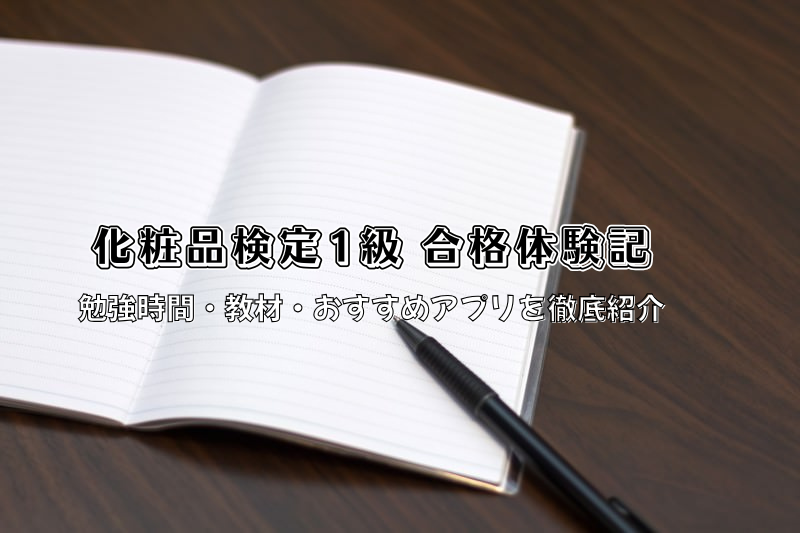
化粧品や美容の知識を証明する資格として人気の高い「日本化粧品検定」。その中でも最難関といわれる1級は、しっかりとした対策が求められます。
一方で、化粧品業界の経験がない方や独学で挑戦する方にとっては、どのように勉強を進めればよいのか迷うケースも少なくありません。
教材の選び方や勉強の進め方を誤ると、思うような成果が得られず、合格が遠のいてしまう可能性もあります。
そこで本記事では、化粧品検定1級に効率的に合格するための勉強法を詳しく解説します。
合格率や必要な勉強時間の目安、勉強に便利なアプリ、さらに筆者が実践した具体的な学習のコツもご紹介。
ぜひ参考にしてみてください!
化粧品検定1級の難易度とは?

化粧品検定1級は、幅広い出題範囲と応用力を問う内容で知られています。
2級に比べると暗記量が多く、業界経験者でも対策なしでは合格が難しいといわれるほど。
とはいえ、出題傾向を押さえて効率的に学習すれば、未経験者でも十分に合格を狙えます。
化粧品検定1級の出題範囲
化粧品検定1級の出題範囲は非常に幅広く、化粧品の成分や製造工程、皮膚の構造、薬機法をはじめとする法規、香料やメイクアップの知識、さらに美容の歴史やトレンドなど多岐にわたります。
- 化粧品の歴史
- 化粧品の原料
- スキンケア化粧品
- 男性肌の特徴
- メイクアップ化粧品の基本となる原料
- UVケア化粧品
- ベースメイクアップ化粧品
- ポイントメイクアップ化粧品
- アイメイクアップ化粧品
- ボディ化粧品について
- 毛髪と頭皮の構造と機能
- 毛髪の変化とトラブル
- ヘアケア化粧品について
- 爪の構造と機能
- ネイル化粧品とお手入れ方法
- 嗅覚のしくみと香りの種類
- 口腔と歯の構造
- サプリメントの基礎知識
- 化粧品と医薬品医療機器等法
- 化粧品・薬用化粧品・医薬部外品の効能と効果
- 化粧品の広告やPRのためのルール
- 化粧品の全成分表示
- 化粧品の安全性を守るためのルール
- 化粧品を安全に保つために
- 化粧品と肌トラブル
- 化粧品の官能評価
- 官能評価の実施例
基礎知識だけでなく応用力や理解力も問われる内容が多いのが特徴です。
化粧品検定の合格基準は?
日本化粧品検定1級の合格基準は正答率約70%以上。出題数は全60問(マークシート四択)で、制限時間は60分です。
なお、各回の難易度に応じて合格ラインが若干調整される場合があります。
化粧品検定1級の合格率は?

化粧品検定1級の合格率は、過去5回平均で約70%です。
範囲が広く応用的な内容も含まれますが、きちんと学習すれば十分に合格が目指せる水準といえるでしょう。
ほかの検定試験と比較してみましょう。
| 検定名 | 合格率(直近の平均) |
| 化粧品検定1級 | 約70% |
| 色彩検定2級 | 約72% |
| 秘書検定3級 | 約70% |
| 簿記検定3級(商工会議所主催) | 約50〜55% |
| 簿記検定2級(商工会議所主催) | 約20〜30% |
| 実用英語技能検定(英検)2級 | 約35〜40% |
近い合格率の検定は「色彩検定」や「秘書検定」があげられます。
検定試験としてメジャーな「簿記」や「英検」と比べると合格率は高めです。
化粧品検定1級の勉強時間・勉強期間はどのくらい?

化粧品検定1級の学習時間は、未経験者で50〜100時間が目安です。期間は6週間〜3か月程度が理想的。
例えば「毎日1時間ほど机に向かう」「寝る前に30分参考書を読む」といった形で、生活に合わせて無理なく学習時間を確保すると続けやすくなります。
週末は2〜3時間をまとめて取るなど工夫すれば、仕事や家事と両立しながら十分に準備が整えられるでしょう。
化粧品検定1級を合格するために必要なアイテム

化粧品検定1級合格に必要な主な教材をご紹介します。合格のためにはほぼマストといってもよいでしょう。
必須アイテム
公式テキスト『日本化粧品検定 1級対策テキスト コスメの教科書(第3版)』:化粧品の成分・薬事・皮膚構造など全分野を網羅。リニューアルにより図版も見やすくなっています。
公式問題集『日本化粧品検定 1級対策問題集(第3版)』:第3版に対応、問題集としてだけでなく補足知識のミニテキストとしても有用です。
購入の際のポイント
最新版の教材を使うことが重要です。特に、2025年11月からの最新出題形式に対応した第3版を選ぶようにしましょう。
予算を抑えたい場合は、中古の第2版以前を利用する方法もありますが、改訂点や法改正への対応が不十分な可能性があります。そのため、使用する際は必ず内容の差分を確認ししてください。
テキストを使った勉強法の概要

化粧品検定1級の学習を進めるうえで、公式テキストをどう活用するかが合否を左右します。まずは全体像をつかみ、ポイントを整理しながら繰り返し読むことが基本です。
1.1周目は全体を通読し、内容の流れを把握する
2.2周目は既存の強調を軸に“目印化”する
3.3周目以降は音読や書き出しで暗記を進める
4.薬機法やトレンドは最新版の情報を必ず確認する
5.直前期はマーカー部分を繰り返し読み返す
この流れを意識して学習を進めれば、効率よく知識を定着させることができます。
1.1周目は全体を通読し、内容の流れを把握する
化粧品検定1級のテキストは、幅広い分野が掲載されています。最初から細かく暗記しようとすると時間がかかり、全体像がつかみにくくなりがちです。
まずは1周目として、用語や詳細を覚えることを目的にせず、全体を通してざっと読むことを意識しましょう。
この段階では「この章はどの分野の話なのか」「どの項目がよく出題されそうか」といった大まかなイメージを持つことが大切です。
気になった箇所や難しいと感じたところには軽く付箋を貼る程度にとどめ、立ち止まらずに最後まで読み切ることを優先してください。
2.2周目は既存の強調を軸に“目印化”する
2周目は、テキストの強調箇所を中心に覚えるポイントを整理します。
難しいと感じた項目や後で見返したいページに、小さな付箋を貼っておきましょう。付箋には「要暗記」「要復習」など簡単なメモを添えると効果的。
1日30〜60分で数ページずつ進め、1〜2週間ほどで全体を一巡できるペースを意識しましょう。
3.3周目以降は音読や書き出しで暗記を進める
2周目で付箋を貼った箇所を中心に、3周目以降は暗記を意識した学習に切り替えてみてください。
出題頻度が高い用語や成分名、数字などは、ただ読むだけでなく声に出して音読したり、ノートや紙に書き出したりすることで記憶に定着しやすくなります。
暗記が苦手な項目は、ゴロ合わせを作ったり、スマホに録音してスキマ時間に聞き流したりするのも効果的です。
この段階で重要なのは、苦手分野を放置しないこと。
付箋を貼ったページや、繰り返し間違える用語を重点的に復習し、知識の穴を埋めていきましょう。
4.薬機法やトレンドは最新版の情報を必ず確認する
化粧品検定1級の出題範囲には、薬機法や美容トレンドといった情報が更新されやすい分野が含まれています。
法改正や新しい成分・技術に関する情報は試験に反映されることが多いため、最新版のテキストを使って学習することが重要です。
特に薬機法は、法律用語や数値が少し変わるだけで正誤が分かれる問題が出題される傾向があります。
公式テキストに加え、日本化粧品検定協会の公式サイトや公式SNSの情報もチェックしておくと安心です。
また、美容のトレンドや最新成分についても、新版のテキストでは内容が更新されている場合があります。
中古テキストを使う場合は情報が古い可能性があるため、改訂箇所を必ず確認しましょう。最新版をベースに学習することが、合格への近道です。
5.直前期は付箋部分を繰り返し読み返す
試験直前期は、新しい知識を詰め込むよりもこれまで学んだ内容を定着させることを優先しましょう。
2周目で付箋を貼った箇所や、3周目以降に付箋を貼った苦手ページを集中的に読み返すのがポイントです。
この時期はテキスト全体をまんべんなく見直すのではなく、重要箇所だけを繰り返すことが大切です。
問題集を使った勉強法の概要

化粧品検定1級の合否を分けるのは、知識を「使える形」にするアウトプット学習です。
公式問題集を繰り返し解くことで出題傾向を把握し、弱点をつぶすことができます。
1.まずは1周目として全問を解き、理解度をチェックする
2.間違えた問題や迷った問題には必ず印をつける
3.解説を読み込み、テキストに戻って知識を補強する
4.2周目以降は印をつけた問題を中心に繰り返し解く
5.直前期は模擬試験形式で時間を計って解き、試験慣れする
このサイクルを回せば、知識の定着と弱点克服が同時に進みます。
1. まずは1周目として全問を解き、理解度をチェックする
問題集を使った学習の最初のステップは、一度すべての問題に取り組んでみることです。
1周目の目的は、現時点で自分がどの分野を理解できていて、どの分野が苦手なのかを把握することにあります。
この段階では、正解率やスピードは気にせず、解けなくても構いません。重要なのは「間違えた問題を明確にする」こと。知らない知識や曖昧な用語が出てきたら、その場で解答解説をしっかり読み、テキストの該当箇所に戻って確認する流れを意識しましょう。
1周目で全体の理解度が把握できれば、2周目以降の学習方針が立てやすくなります。ここで焦って暗記しようとするよりも、「自分の苦手分野を見つける」ことを目的にしてください。
2.間違えた問題や迷った問題には必ず印をつける
1周目で全問に取り組む際は、間違えた問題や答えに迷った問題には必ず印をつけておくことが重要です。
間違えた問題はもちろん、正解したとしても「自信が持てなかった」「なんとなく選んでしまった」という問題も弱点の可能性が高いからです。
この作業を丁寧にしておくことで、2周目以降は印をつけた問題だけを重点的に復習する効率的な学習が可能になります。
結果的に弱点を集中的に克服でき、短期間でも合格レベルに近づくことができます。
3.解説を読み込み、テキストに戻って知識を補強する
問題を解いたら、必ず解説をじっくり読むことが大切です。
間違えた問題はもちろん、正解した問題であっても解説を確認することで新しい知識や出題の背景を学べます。
解説を読んでも理解が曖昧な場合は、必ずテキストに戻って該当箇所を確認しましょう。問題集とテキストを行き来することで、知識が体系的に整理され、記憶にも定着しやすくなります。
また、解説で新しく得たポイントや忘れがちな数字・用語は、テキストの余白に書き込むか付箋にメモしておくと、後で復習しやすくなります。
このプロセスを繰り返すことで、問題を「解ける」だけでなく、基礎から「理解できる」状態へ引き上げることができます。
4.2周目以降は印をつけた問題を中心に繰り返し解く
1周目で印をつけた問題は、自分の弱点が凝縮された重要ポイントです。2周目以降は印のついた問題だけを重点的に繰り返し解くことを意識しましょう。
ここでは、答えを暗記するのではなく、「なぜその選択肢が正しいのか」「なぜ他の選択肢は間違いなのか」を自分で説明できるレベルを目指すことがポイントです。
解けない問題や自信がない問題は、さらに印をつけて優先度を上げ、重点的に復習していきます。
繰り返し解くことで出題パターンが見えてきて、知識が確実に定着します。問題を解きながらテキストの重要部分を再確認し、理解を深めるサイクルを回すと、短期間でも効率的に得点力が伸びていきます。
5.直前期は模擬試験形式で時間を計って解き試験慣れする
試験が近づいてきたら、最後の仕上げとして模擬試験形式で問題を解く練習を取り入れましょう。
化粧品検定1級は60問・60分の構成です。本番と同じ条件で時間を測り、一気に解き切る練習をすることで、時間配分や集中力の持続感覚を身につけることができます。
模試の結果は単なる正答率を見るのではなく、どの分野で得点できたか・取りこぼしがあったかを分析することが大切です。苦手分野があれば、直前まで集中的にテキストと問題を復習し、知識の抜けを補いましょう。
また、模擬試験を繰り返すことで「問題文の読み方」「ひっかけ選択肢への対応力」など、実践的な感覚が養われます。精神的にも「解いたことがある形式」で挑める安心感が生まれるため、本番での緊張を和らげる効果もあります。
化粧品検定1級の勉強におすすめのアプリ

スマホを上手に活用すれば、スキマ時間も効率的な学習時間に変えられます。
ここでは、集中力を高めるポモドーロ式タイマーアプリ「Forest」と、暗記の定着に役立つ「暗記メーカー」の2つをご紹介します。
Forest
化粧品検定の勉強に役立つアプリとしておすすめなのが「Forest」です。
これはポモドーロ・テクニックを活用した集中力向上アプリで、25分の作業と5分の休憩を繰り返す学習法をサポートします。
アプリ内では集中時間に合わせて木が育つため、スマホを触らず勉強に集中しやすくなるのが特徴。
勉強の習慣化や時間管理にも役立つので、試験直前の追い込み期にもおすすめです。
テスト勉強用アプリ「暗記メーカー」
自分で問題集を作れるアプリです。
覚えにくかったところを問題として作成し、繰り返し解くことで、記憶が定着しやすくなります。勉強に飽きてきたときにポチポチと問題作りをしてみてもいいかもしれませんね。
また、ユーザー同士で作った問題集をシェアできるのが魅力。なんと化粧品検定1級の問題集もシェアされています。化粧品検定1級の勉強をするのに見逃せないアプリといえるでしょう。
化粧品検定1級に1発合格した私の勉強法

私は化粧品検定1級と2・3級を同日に受けて1発合格しました。勉強期間は2週間です。特に美容系の仕事をしていたこともありません。勉強方法によっては、2週間の合格も不可能ではないのです!
とにかく「反復」せよ!
勉強は、とにかく「反復」をしました。繰り返せば繰り返すほど覚えるのです。私の場合は黙読しました。なぜなら1周にかかる時間がもっとも短いからです。
音読やノートへの書き出しは記憶に定着しやすいと思いますが、1周にかかる時間が長い。ノートへの書き出し1周と、黙読10周は同じくらいの時間だと思うんですよね。でも後者のほうが覚える気がします。
音読や書き出しは必要なところだけをおこない、あとはとにかく反復回数を増やすことを意識しました。
取捨選択もしてしまう
とりあえず「合格」を目標とするなら、取捨選択をしてしまってもいいと思います。
たとえば、「香り」に関する部分。テキストには表がドンと載っているのみ。これをすべて覚えるのは至難の業です。
完璧に覚えたところで問題としてでてくるのは1問……多くて2問。そのためにリソースを割く必要があるか。私は「否」でした。「香り」に関しては完全に捨てました。
ただ、テキストに載っていることは大切な知識。テストが終わってからでいいので、ゆっくりと覚えていきましょう。
対策スクールを利用するのも方法のひとつ

一人では勉強が続かないと感じるなら、対策スクールの利用も有効です。
カリキュラムに沿って学べるうえ、講師の解説や質問対応で理解が深まります。
課題や模擬試験がペースメーカーとなり、締切が行動を後押しする点も利点です。
さらに、一緒に学ぶ仲間がいることでモチベーションも維持しやすくなるのがスクールの大きな魅力。
通学・オンライン・ハイブリッドから選べるため、予算や生活リズムに合う校舎を比較し、無料体験や説明会で相性を確認してから受講を検討すると良いでしょう。
まとめ

化粧品検定1級は範囲が広いものの、計画的に進めれば合格は十分可能です。
学習目安は50〜100時間。まず通読で全体像を掴み、2周目で要点をマークし、3周目以降は暗記と問題演習で仕上げましょう。
公式テキストと問題集は最新版を推奨します。独学が難しければスクール活用も有効。今日から一歩を始めてください。