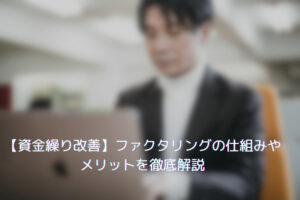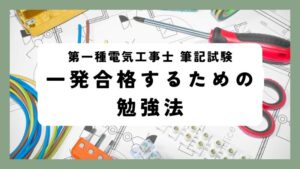紙とどう違う?タブレット学習のメリット・デメリットを解説
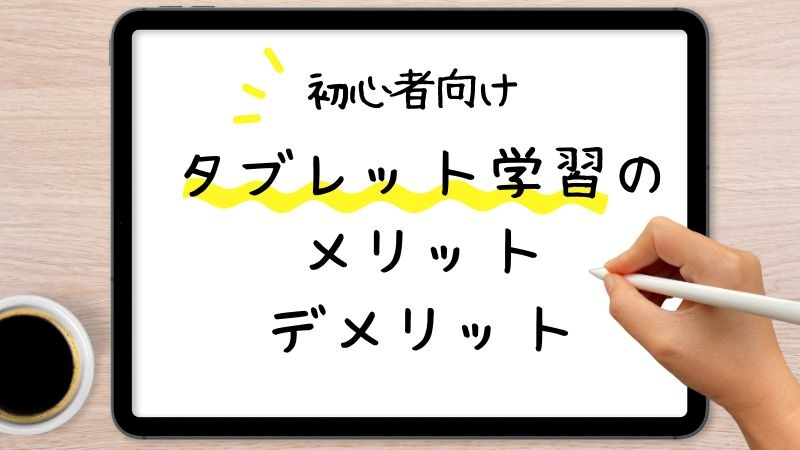
子どもの学習用に、タブレットを子どもに与えるべきか悩む人は多くいます。幼い子どもの場合、タブレット学習は発達への影響や依存のリスクもあるため注意が必要です。
この記事では、タブレット学習のメリットやデメリット、効果的な活用法を解説します。
記事を読めば、子どもの年齢や性格に合わせたタブレット学習の取り入れ方がわかります。タブレット学習は、適切な時間管理と使い方のルールを設けると、子どもの学習意欲を高めることが可能です。
タブレットを活用して、子どもの学力向上に役立てましょう。
タブレット学習のメリット

タブレット学習のメリットは、以下のとおりです。
- わかりやすい動画授業で理解が深まる
- 持ち運びが便利でどこでも学習できる
- 反復学習が簡単にできる
- 楽しく学べる工夫が多い
- 学習進捗の把握がしやすい
タブレットのメリットを理解すれば、より効果的に子どもの学習に役立てられます。
わかりやすい動画授業で理解が深まる
多くのタブレット学習サービスでは、プロの講師による動画授業が見放題となっていることが多くあります。
紙のテキストだけでは理解しづらい内容も、図やアニメーションを使った動画で解説されると、子どもたちにとってわかりやすくなります。
動画授業であれば子供は興味を持ちやすく、自分のペースで再生・停止・巻き戻しができるため、苦手な部分を繰り返し学ぶことが可能です。
タブレット学習サービスは、学年にとらわれず自分の理解度に合わせて、先取り学習や復習ができるのも魅力の一つです。
持ち運びが便利でどこでも学習できる

タブレット学習は、場所を選ばずに学習できる手軽さが魅力です。
タブレットなら、子どもの機嫌や状況に合わせて瞬時に学習を始められます。タブレットはコンパクトで、複数の教材がインストールされているので、多くの教材を持ち歩く必要もありません。
学習するときの気分に応じて、学習方法が選べます。タブレット学習を利用すれば、子どもは兄弟の習い事の待ち時間など、ちょっとした空き時間を有効活用して学習できます。
反復学習が簡単にできる
タブレット学習は、反復学習が簡単にできるのも大きなメリットの一つです。
AI技術を活用したアプリでは、子どもの理解度に合わせた問題が自動生成される仕組みがあります。子どもが学習するのに適切な難易度で学べるため、簡単すぎて飽きたり、難しくて挫折したりすることも少なくなります。
間違えた問題を自動で記録してくれるため、苦手な問題を重点的に復習することも可能です。タブレット学習は、ゲーム感覚で学習に取り組めるので、子どもも楽しんで学べます。
タブレットは紙のドリルと違い、消耗品ではないため経済的にも優れているのが特徴です。タブレット学習は難易度調整も簡単にできるため、子どものやる気に応じて調整するのもおすすめです。
タブレット学習を使って、子どもの成功体験を積み重ねながら、学習意欲を維持しましょう。
楽しく学べる工夫が多い

タブレット学習は、子どもが楽しみながら学べる工夫が豊富です。タブレット学習アプリには、アニメーションによる演出や、ゲーム感覚で進められるコンテンツが含まれています。
正解時の音やエフェクトによる達成感の演出も、子どもたちの学習意欲を高める要素の一つです。タブレット学習は、学習への抵抗感を減らす効果も期待できます。
親子で一緒に取り組める学習コンテンツも魅力的です。親子で一緒に学習に取り組めば、コミュニケーションの機会も増やせます。タブレット学習はバッジ収集やご褒美システムなど、モチベーションを維持する仕掛けも充実しています。
クイズ形式やミニゲームを取り入れた教材も多いため、勉強がつまらないという印象を和らげるのにも効果的です。低学年の子どもに、学習の入り口として活用するのも有効です。
学習進捗の把握がしやすい
タブレット学習では、学習データがすべて自動記録されているため、子どもの学習進捗を簡単に把握できます。
タブレット学習は、AIが子どもの理解度に合わせてくれるため、子どもの得意分野と不得意分野が一目でわかって便利です。多くのサービスでは、学習時間や正答率、得意・不得意分野などがグラフで表示される機能があります。
親子で学習の進捗を把握しやすくなっているため、苦手を克服しやすく、モチベーション維持にもつながります。タブレットの情報をスマホアプリと連携できるため、どこかでも手軽に学習進捗を確認できるのもメリットです。
複数の子どもがいる場合でも、それぞれの進捗を個別に確認できるため、一人ひとりの成長に合わせたサポートが可能です。学習の進捗を可視化すると成果を実感しやすく、子どもの自信にもつながります。
タブレット学習のデメリット

タブレット学習のデメリットは、以下のとおりです。
- 操作に慣れるまで時間がかかる
- 目の疲れや視力低下のリスクがある
- 紙に書いて覚える学習がしづらい
- 勉強以外のアプリに気をとられる
- 故障すると学習が中断される
メリットの多いタブレット学習ですが、デメリットもあるため利用する前によく検討しましょう。
操作に慣れるまで時間がかかる
低年齢の子どもにとっては、大人なら簡単にできるタップやスワイプなどの操作も難しいものです。小さな子どもには始めての体験なので、タブレットの基本操作を覚えるまで時間がかかる場合があります。
最初のうちは保護者が一緒に取り組むなどのサポートが欠かせません。タブレットに慣れないうちは、集中力が保ちにくいこともあります。
徐々にタブレットに慣れていくことで、子ども一人でも扱えるようになり、自立した学習スタイルへとつながっていきます。
目の疲れや視力低下のリスクがある

タブレット学習は子どもの目に負担をかけるリスクがあります。長時間の画面注視は、目の疲れや視力低下を引き起こす可能性が高いため、注意が必要です。
0〜6歳の時期にタブレットを長時間使用すると、近距離での画面凝視により、近視の発症や進行のリスクが高まります。タブレットの使用によってまばたきの回数が減少すると、ドライアイの原因にもなります。
就寝前にブルーライトを浴びると、睡眠リズムを乱すため利用する時間にも注意しましょう。画面の明るさや反射は目に負担をかけ、小さな文字のコンテンツは目の緊張を引き起こします。
悪い姿勢でタブレットを使用すると、目の疲れは悪化します。子どもがタブレット学習をするときは、定期的な休憩を取り入れ、適切な距離や姿勢を保ちましょう。
紙に書いて覚える学習がしづらい
タブレット学習では、書いて覚える学習をする機会が少なくなります。
紙に書いて覚える学習のメリットは、以下のとおりです。
- 記憶の定着を促進する
- 脳の活性化に役立つ
- 手先の運動能力が発達する
- ノートのまとめスキルが向上する
- 創造的思考力が育まれる
タブレット上では、指やスタイラスペンでタップやスワイプはできますが、紙に鉛筆で書く感覚とは異なります。タブレット学習では、鉛筆を正しく持つ練習や文字を書く感覚を身に付ける機会が減少するデメリットがあります。
タブレット学習では、手書きによって得られる達成感や満足感を得にくいため、紙を使った学習も合わせて行いましょう。自分の手で書いた文字や絵を見る感覚は、大きな学習意欲につながります。
勉強以外のアプリに気をとられる

子どもにスマホやタブレットで学習させると、勉強以外のアプリに気をとられることが問題です。子どもは自制心が発達途上なため、YouTubeやゲームなどの娯楽アプリの誘惑に負けやすい傾向があります。
0〜6歳の幼児は、カラフルな画面の動きや音に強く反応する特徴があります。学習用に与えたタブレットが、娯楽ツールとなってしまうので、利用状況には注意が必要です。
学習に関係のないアプリからの通知によって学習が中断されると、子どもの集中力が途切れます。勉強以外のアプリに気を取られると、子どもの知識の定着にも悪影響を及ぼす可能性があります。
タブレット学習により、勉強と遊びの境界があいまいになるため、集中力をどう保つかは大きな課題です。学習専用の端末として保護者が使用履歴を管理し、アプリの制限設定を行うなどの工夫をしましょう。
故障すると学習が中断される
タブレットでの学習中に故障やトラブルが発生すると、学習が突然中断されてしまうリスクがあります。幼い子どもが使う場合は、水濡れや落下による故障も起きやすく、高額な修理費用がかかる場合もあります。
タブレット学習で注意すべき故障やトラブルは、以下のとおりです。
- 画面割れ
- バッテリー問題
- システムエラー
- アップデート不具合
- ネットワーク障害
故障時の保証やサポート対応には時間がかかるため、試験前などの学習期間と重なると学習ができません。機種変更時のデータ移行がスムーズにいかない場合もあるため、定期的なバックアップも忘れずに行いましょう。
タブレット学習のデメリットを最小限にする方法

タブレット学習のデメリットを最小限にする方法は、以下のとおりです。
- 画面を見る時間を管理する
- 学習専用のアプリのみをインストールする
- ブルーライトカット機能やフィルムを活用する
デメリットに適切に対処することで、タブレット学習のメリットを最大限に活かせます。
画面を見る時間を管理する
タブレット学習を取り入れるときは、子どもが画面を見る時間を管理することが重要です。
長時間のタブレット学習は目の疲れや視力低下の原因になるので、2〜5歳の子の場合は1日1時間までに制限しましょう。学習時間を分割して、目を休める時間を確保するのも効果的です。
タイマーアプリを活用すると、時間管理が容易になります。タブレット学習は明るい時間に使用するよう心がけ、こまめに休憩時間を設けましょう。20分ごとに20秒間、約6m先を見ることで、目の筋肉をリラックスさせられます。
子どもがタブレットを使用しているときに、目をこすったりまばたきが多くなったりした場合は、休憩を取りましょう。就寝前の使用は避けてください。
タブレット学習と紙の学習、外遊びなどをバランスよく組み合わせると、デジタルデバイスの使用時間を自然と制限できます。
学習専用のアプリのみをインストールする

タブレット学習のデメリットを最小限にするには、タブレットに学習アプリだけを厳選してインストールするのが効果的です。
エンターテイメント系は、別のデバイスにインストールしましょう。学習に集中できる環境を作るには、年齢に合ったアプリ選びが重要です。
アプリのダウンロードには、親がコントロールできる設定をすると安心です。アプリストアへのアクセスをパスワードで制限すれば、子どもが勝手に新しいアプリをインストールするのも防げます。
通知設定はオフにしておくと、学習中の集中力を妨げないため効果的です。学習時間管理アプリを導入して、利用時間を制限するのも有効です。
定期的にアプリを見直し、使っていないものは削除しましょう。学習環境を整えると、子どもがタブレットを学習ツールとして効果的に活用できます。
ブルーライトカット機能やフィルムを活用する
ブルーライトカット機能やフィルムを活用すると、子どもの目の健康を守りながらタブレット学習を続けられます。
ブルーライトは目の疲れや睡眠の質低下の原因になるため、対策が重要です。ブルーライト軽減機能が搭載されているタブレットも、多くあります。
タブレット用ブルーライトカットフィルムや、子ども用ブルーライトカットメガネの使用もおすすめです。子どもには目の疲れを感じたら、保護者に伝えるよう促しましょう。
部屋の照明も適切に保ち、画面との明暗差を減らすのも目の負担軽減に役立ちます。視力の変化をこまめに確認すると、早めに対策が取れます。
タブレット学習を行っている子は、定期的に目の検診を忘れずに行いましょう。
タブレット学習が向いている人

タブレット学習が向いている人は、以下のとおりです。
- 自分のペースで学習を進めたい人
- 学習習慣が身に付いている人
自分のペースで学習を進めたい人
自分のペースで学習を進めたい人には、タブレット学習がおすすめです。
タブレット学習を活用すれば、時間や場所に縛られず、子どもの状態に合わせた学習ができます。タブレット学習なら、忙しい日や子どもの体調が優れない日は軽めに取り組み、余裕がある日はしっかり学習できます。
得意な分野は先に進み、苦手な分野は繰り返し学習できるため、子どもの機嫌や生活リズムに合わせた学習が可能です。
タブレット学習は通塾とは異なり、急な予定変更があっても柔軟に対応できます。子どもの集中力が高いタイミングでの学習をすると、効率よく知識を吸収できます。
学習習慣が身に付いている人
学習習慣がしっかり身に付いている子どもは、タブレット学習で大きな成果を上げられます。
学習習慣が身に付いている子どもの特徴は、以下のとおりです。
- 決まった時間に自分から学習を開始できる
- 計画的に学習できる
- 学習内容の自己選択と判断ができる
- 自発的に課題に取り組める
- 集中力を持続させられる
学習習慣が身に付いている子どもは、時間の区切りを自分で決めて守れるため、目の疲れなどの心配も少なくなります。
幼児期から学習習慣を育てるには、毎日少しずつ取り組む時間を作るのが大切です。最初は親が一緒に取り組み、徐々に子どもが主体的に学習できるよう導きましょう。
タブレット学習が向いていない人

タブレット学習が向いていない人は、以下のとおりです。
- デジタルデバイスに抵抗がある人
- 集中力が続かない人
デジタルデバイスに抵抗がある人
デジタルデバイスに抵抗がある子どもにとって、タブレット学習を始めるハードルは高く感じられます。
デジタル機器の操作に不慣れな人は、子どもに教えるのも難しいため学習サポートがスムーズに進みません。画面操作よりも、紙や実物に触れる感覚を大切にしている人も多くいます。
タブレット学習による目の疲れや、ブルーライトの影響も懸念すべきポイントです。デジタル機器への依存する可能性も気になるリスクの一つです。タブレット学習は短時間から始めて、徐々に慣れていきましょう。
親子で一緒に操作してみると、デジタル機器への抵抗感が和らぎます。
集中力が続かない人
集中力が続かない子どもには、タブレット学習が向いていません。
以下の傾向がある子どもは、タブレット学習に向いていない可能性があります。
- 通知やポップアップに注意が奪われる
- タブレット操作に夢中になる
- 学習アプリから他のコンテンツに移動する
- 短時間で飽きる
タブレット学習は紙の教材と違い、スワイプやタップなどの操作が多いため、気が散りやすいのが問題です。
タブレット学習を効果的に行うには、保護者が適切に管理と指導をしてあげましょう。
タブレット学習に関するよくある質問

タブレット学習に関するよくある質問は、以下のとおりです。
- タブレットと紙の学習はどちらが効果的?
- タブレット学習は幼児に悪影響がある?
タブレットと紙の学習はどちらが効果的?
タブレット学習と紙の学習は両方にメリットがあり、子どもの年齢や学習目的によって使い分けるのが最適です。
紙の学習は手を動かして書くことで脳に多くの刺激を与えられるので、記憶の定着に効果があります。紙のテキストは目の疲れも少なく、長時間集中して取り組むのに向いています。
タブレットは学習への興味を引き出しやすく、学習の記録や分析ができるのがメリットです。幼児期は、紙とタブレットの教材をバランスよく取り入れるのがおすすめです。
タブレットの楽しさで学習意欲を高めつつ、紙と鉛筆で書く体験も大切にしましょう。
タブレット学習は幼児に悪影響がある?
タブレット学習の幼児への影響は、使い方次第で変わります。タブレットは適切に管理すれば学習ツールとして有効ですが、使いすぎると悪影響を及ぼす可能性があります。
幼児期の子どもは実体験を通じた学びが重要なため、長時間の利用は避けましょう。
タブレットの長時間使用によるリスクは、以下のとおりです。
- 目の疲れや視力低下
- 姿勢の悪化
- 睡眠の質の低下
- 対人コミュニケーション能力の発達遅延
タブレットは適切に活用すれば幼児の学びを助ける強力な道具になります。
親がしっかりと管理し、子どもと一緒に使用しましょう。
まとめ

タブレット学習は、持ち運びの便利さや反復学習のしやすさなど多くのメリットがあります。しかし、目の疲れや紙で書く機会の減少などのデメリットもあります。
自分のペースで学びたい子どもや、学習習慣がすでに身に付いている子どもには、タブレット学習が最適です。デジタル機器に抵抗がある場合や、集中力に課題がある場合はタブレット学習が向いていない可能性があります。
タブレット学習のデメリットを軽減するには、学習時間の管理やブルーライトカット対策などの工夫が効果的です。タブレット学習を正しく活用すれば、子どもの学習意欲を上げられます。
子どもに合った方法で、タブレット学習を取り入れましょう。