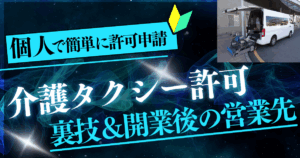4年間のひきこもり経験者が語る、超極私的「レジリエンス」の高め方
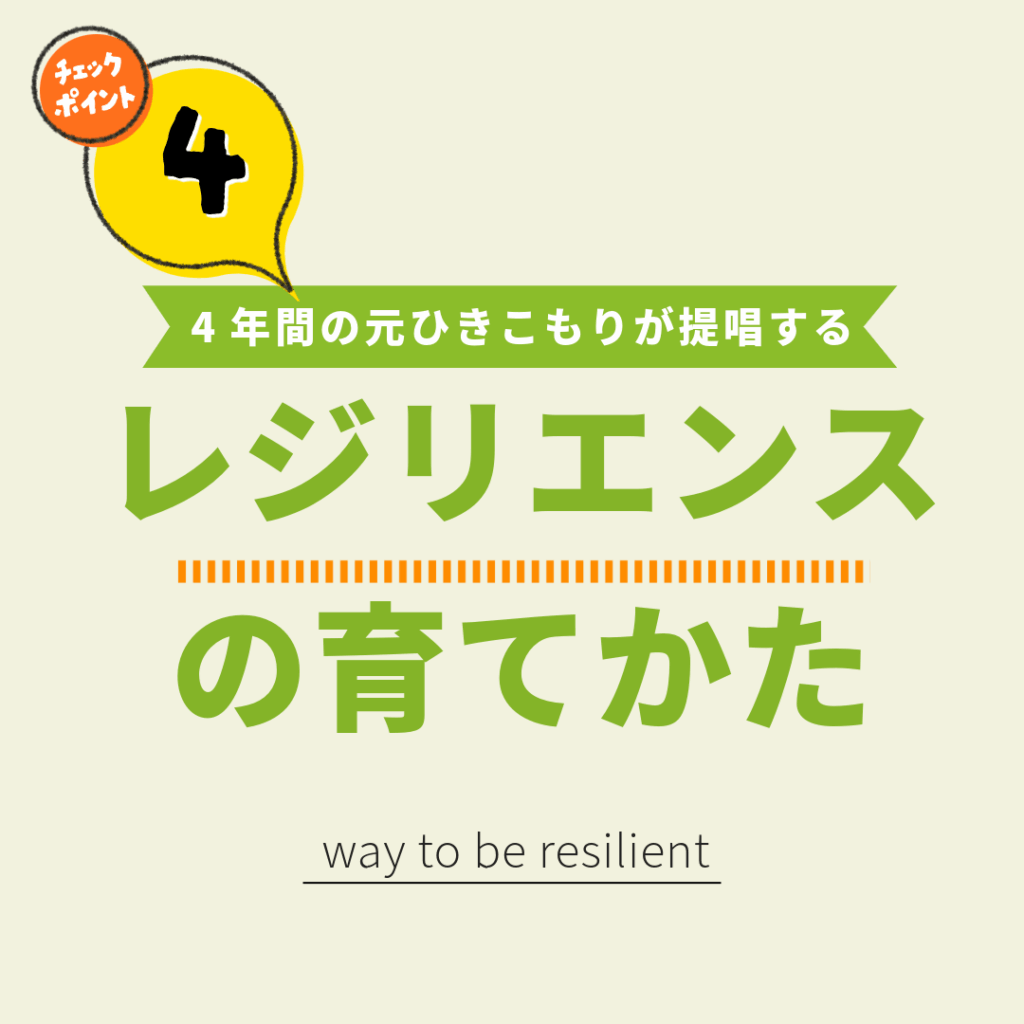
【はじめに】
当記事の狙い~レジリエンスの高め方をお伝えします!~
-1.jpg)
「レジリエンス(resilience)」という概念をご存じでしょうか?困難やストレス状態から立ち直る力をさし、日本語では「逆境力」や「精神的回復力」という言葉に該当します。
現代社会は先行きが不透明で不確実性や変動性の高く、今までの常識が非常識となる、「VUCA時代」と言われています。そういった時代背景から、レジリエンスがこれまで以上に注目されています。
筆者は20代に4年間のひきこもり生活を送り、その状態から大学進学・就職・結婚へと「普通の人生へ回復」(注1)しました。
当記事では、「回復」の過程でレジリエンスを高め、家族や友人からは「レジリエンスの塊」と称される筆者が、レジリエンスの定義からレジリエンス力を高めるための習慣をご紹介します。
(注1)「普通の人生」とは様々な考え方があるため、一概には定義できませんが。
【レジリエンスの定義】
.jpg)
レジリエンス(resilience)とは、元々はストレス(stress)と対になる物理学用語でした。
ストレスが「外力による歪み」と定義されるのと対になり、レジリエンスは「外力による歪みを跳ね返す力」として使われ始め、転じて精神医学用語となりました。
日本語では「精神的回復力」「逆境力」「抵抗力」「復元力」などと言われていますが、ストレスへの「折れやすさ」ではなく、「ストレスからしなやかに元に戻る力」を指します。
【なぜ、今、レジリエンスなのか?】
前述したとおり、現代はVUCAの時代と言われています。VUCAとは、V(変動性)、不確実性(不確実性)、複雑性(複雑性)、A(曖昧性)の略語ですが、そんな時代にレジリエンスが重視されている理由を深堀していきましょう。
VUCAとは?
Volatility(変動性):変化のスピードが速く、その幅が大きいこと
Uncertainty(不確実性):将来何が起きるか予測できないこと
Complexity(複雑性):要因が複雑に絡み合い、因果関係が見えにくいこと
Ambiguity(曖昧性):状況の解釈が複数存在し、何が正解かが明確でないこと
.jpg)
- 変化や逆境に直面する頻度が増えているから
生成AIに代表されるテクノロジー革新、地政学リスクや気候変動、コロナ大流行のパンデミックなど、これまでにない規模と速度で変化していく時代を私たちは生きています。
以前まで日本では終身雇用が当たり前でしたが、それは過去の話。安定を前提とした「予測と計画」に依存するだけでは限界があります。予想外の事態に直面しても立ち直れる力、つまりレジリエンスが不可欠となります。
- 不確実な状況で成果を出すための基盤になるから
同じストレスや困難に遭遇しても、レジリエンスの高い人は感情に押し流されず冷静さを保つことができます。それだけではなく、レジリエンスの高さから、困難にポジティブな意味づけをし、次の行動に移すことができます。
そんな人がチームにいたら、チームの雰囲気が明るくなると思いませんか?レジリエンスの高さは、チームや組織全体の生産力や持続力に繋がるのです。
- 人材の持続可能性を守るから
レジリエンスとは、単なる「ストレス耐性」や「精神論」ではありません。VUCA環境下では、常に不安やプレッシャー・変化対応が求められます。
「セルフケア」「ストレスマネジメント」「人とのつながりの活用」を通じて、心身の健全さを守る力がレジリエンスにはあるのです。
結果として、人は心身ともに健康的に、持続的に働き続けることができるのです。
- イノベーションや学びに直結するから
挑戦には失敗がつきものですが、失敗を恐れて動けない組織に成長性はありません。レジリエンスのある個人やチームは、失敗をポジティブな学びに変え、試行錯誤を続ける力があります。
そうしたトライアンドエラーは、イノベーション創出にもつながるのです。以上、論じてきたように、VUCA時代にはレジリエンスが必要不可欠なのです。
【コラム:レジリエンスとストレス耐性の違い】
レジリエンスと聞いて、「それってストレスに強いということ?」と疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、レジリエンスは「単なるストレス耐性」とは似て非になるものです。
・ストレス耐性とは、厳しい状況やプレッシャーの中でも崩れずに耐えられる力を指します。いわば「外部からの圧力をどれだけ受け止められるか」という‘’受動的な力‘’です。ただ耐えるだけでは、疲弊したり精神摩耗したり、心身をすり減らしてしまう危険もあります。
・レジリエンスは、「困難を乗り越えたあとに、回復し、学び、よりしなやかに成長する力」です。それは単なる受動的な受け身の忍耐ではなく、「しなやかに折れ曲がりながらも、もとに戻る、もしくは新しい形へ変化する」という能動的な力です。
【レジリエンスの一例~筆者が4年間ひきこもった理由~】
.jpg)
それでは、実際に「レジリエンスとはどのようなものなのか」という一例として、ここで筆者自身の体験談を話させてください。
筆者は浪人時代の19歳のころ、双極性障害Ⅰ型を発症しました。双極性障害とは、躁状態(気分亢進による性的逸脱・万能感・異常なハイテンション・観念奔逸・金銭的散財など)と、鬱状態を繰り返す精神気分障害です。
いわば、躁は「元気になりすぎる」状態で、鬱状態は「元気がなさすぎる」状態です。「気分の浮き沈みは誰でもある」「躁で元気になるならそれでも良いじゃん!」とお思いになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし躁状態の気分亢進は異常なものです。
自分は天才でノーベル平和賞を受賞する!自分は歌手になって天下とる!自分は村上春樹に次ぐ作家だ!といった妄想に憑りつかれる。上半身下着姿で外を走り回る。
気分がイライラするから公園にあった植木鉢の花を抜き取り、砲丸投げよろしく投げる。そしてその場を通報され拘束される。
「危ないやつすぎる・・・」「近づきたくない・・」と思ったそこのあなた。これはすべて筆者自身が起こした、沢山ある躁エピソードの一部です。警察に拘束されたあとは、閉鎖病棟に4か月の強制入院となります。
.jpg)
退院したあと、筆者は躁状態の反動として激鬱状態となります。
躁状態で周囲にかけた迷惑ややらかした様々な出来事への後悔から、自分の部屋に閉じこもり、希死念慮に襲われていました。対外的には「浪人生」という体でしたが、実際はただのひきこもり。
または現実逃避からネットの世界に入り浸る「閉じこもり」に近かったのかもしれません。お昼過ぎに起きて、もそもそとご飯を食べ、食べ終わったらすぐに部屋のベッドにこもりネットサーフィン。
朝方まで起きて、そこからまた寝る、という生活を繰り替えしました。
歯はたまにしか磨かず、お風呂に入るのは3日に一度。運動不足で24Kg太り、さらに自己嫌悪感を高めました。これが私の19~21歳に起きたことです。散々な青春時代でした。
あることを機に大学受験勉強に戻り、なんとか大学進学しました。しかし、大学生活を始めても、またも精神状態を崩し、2年間の休学。灰色の大学生活でしたが、休学を明けたあと、なんとか大学を卒業し、就職することができました。
31年の人生で計4年間自宅の部屋にひきこもっていた私は、当時「完璧人生終わった・・・」と自己否定感の塊でした。暗黙の時代。どこにも光を見出すことができない、辛く、苦しい4年間でした。
【レジリエンスの一例~私はどうひきこもりから立ち直ったのか~】
-2.jpg)
筆者がひきこもっていたのは、大学進学前の(仮)浪人生の2年間、そして大学進学後の2年間です。
一度ひきこもり状態から普通の人生へ回復したあと、またひきこもりとなり、そしてもう一度普通の人生へ戻った、という流れです。
それでは、どうやってひきこもり状態から普通の人生へ戻ったのか、その二度の立ち直りには、いくつかの共通点がありました。ここではそんな共通点をお伝えします。
①スモールステップを大切にする
-2.jpg)
まず重要なことは、最初の目標を大きくしすぎないということです。浪人時代にひきこもりをしたということで、私は最初の目標を「現役時代に合格した大学より良い大学に合格する」という大きなものに設定してしまいました。
しかし、実際は自己否定感よりネットに居場所を求め、ネットサーフィンの毎日。生活は昼夜逆転し、受験勉強のために参考書を開くどころか、ペンを握ることすらありませんでした。より良い大学に合格することなど夢のまた夢。
それでも、設定した目標を忘れることができず、引きこもっていても、さぼっている罪悪感から全く安心することができませんでした。
そんな大きすぎる目標と現実のしょうもなさに悩む私に、助言したのが父でした。ベッドにこもっている私に、父は「まず、勉強机のホコリを水拭きすることから始めてみよう」と言いました。
「そんなことが意味あるの?」と納得せずに実行してみましたが、拭いてみるとあら不思議。ベッドにこもりネットしかしていなかった生活から、「水拭きする」という目標を達成したことで、少し新しい風が吹いたのです。
水拭きしたことを父に伝えると、「それではまず机の前の椅子に5分座ってみよう」。それが終わると「じゃあ次は10分座ってみよう」、少しずつ時間を増やしていき、「じゃあ次はなんでも良いから、本を開いて5分眺めてみよう」と言いました。本を開くのが、10分となり、30分となり、1時間となり、気づいたら私は受験勉強を再開していたのでした。
この経験から、それがどんなに些細でも、どんなにしょうもなく見えても、「まず小さな目標を設定して、それを達成してみる」「達成したら自分を手放しで褒める」ことが大切なのだと気づきました。
この記事を読んでいる皆さんにとっての最初の小さな目標は何になるのでしょうか。私にとってそれは「まず机を水拭きする」ことでした。そして受験勉強をそのスモールステップから始めた私は、志望大学に合格することができたのです。
皆さんも、まずは小さな目標を設定して達成してみませんか。それが、挫折から立ち直るレジリエンスの始まりの第一歩です。
②日常の小さな習慣を大切にする
-2.jpg)
少しずつ受験勉強を再開した私ですが、相変わらず昼夜逆転・部屋でのひきこもり生活は続いていました。そこで日常の習慣として始めたのが、以下の3つです。
・「朝同じ時間にまず部屋の電気をつける」
これは自分ひとりきりでは達成できないので、父と母が毎朝つけに来てくれました。朝同じ時間に電気を点ける。眠くて二度寝したいときも、とりあえず同じ時間に起き上がって電気を消すだけでも、スモールステップのひとつです。
私は二度寝するまで時間が、少しずつ長くなっていき、昼夜逆転の生活を改善することができました。「とっくに大人なのに父母に頼りきりで恥ずかしくないの?」「甘えすぎ」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ここで重要なのは「人は一人きりではなかなか変わることができない」ということです。後述しますが、適切なタイミングで、適切な人に頼るというのも、レジリエンスを高める大切な練習なのです。
・お散歩にいく
ひきこもり経験のある方は共感していただけるかと思うのですが、とにかく体力が落ちています。そして季節の変わり目に立ち会わず日々が過ぎていく・・・。外に出ようと思うのですが、人目も気になるし、タイミングがつかめない。
そしてどんどん内向的になり、より外への第一歩が遠のいてしまう、という悪循環に陥ります。そんなときPokémon goがリリースされたのが、外に出る大きなきっかけとなりました。
人目の少ない夜にのみPokémon goをしに外に出ていたのですが、だんだんと前倒しになっていきました(これもスモールステップの一つですね!)。
「セロトニン」という神経伝達物質は、精神の安定や安心感・平常心を上げるなど、脳を活発に働かせる鍵となる脳内物質です。
日光を浴びるのはこのセロトニンを増やすことにもなります。ひきこもり状態の人でなく、お散歩はすべてのかたにおすすめな日課です。
・日記を書く
簡単にですが、その日に感じた出来事をパソコンに打っていました。これもスモールステップの机に向かう時間を増やしていく過程で、「机の前に座っているときに何をしよう?」→「そうだ!日記を書いてみよう」という思いつきから始まった習慣です。
ひきこもり状態から脱して10年の今でこそやっていませんが、日記をつけることは、後で読み返して自分の状態を測る「体温計」の役割となります。
また、日記やエッセイを書くことで、自分の感情を客観視することにもつながり、レジリエンス向上のために必要な「セルフモニタリング」(注4)にもつながります。
(注4)セルフモニタリングは自分のストレスサイン(睡眠・食欲・思考)を記録する上で重要です
③認知の歪みを治す
-1.jpg)
レジリエンスが低い方に多いのが、「失敗」をそのまま「失敗」として考えてしまう傾向があります。
前述のスモールステップの回でも触れましたが、当時の私は「この一年でひきこもりを脱して、絶対に現役のときより良い大学に合格して進学したい」という考えに囚われていました。
「一年で」で「なるたけ早く」、「現役のときより良い大学」で「偏差値が高い大学が良い大学」という認知に歪みがあったのです。決心は人を前にする燃料となることもありますが、かた過ぎる決心は人をがんじがらめにすることもあります。
そんな私に父は「人生100年時代なんだから、この挫折から立ち直るのに10年はくれてやろう」という時間軸を教えてくれ、母は「今年は受験会場に行くのを目標にしよう」という価値観を伝えてくれました。
出来事を「失敗」ではなく、「経験」と捉える柔軟な認知へのリフレーミングを大切にし、完璧主義より「六~七割主義」と考える姿勢がレジリエンス力を高めることへ繋がりました。
完璧主義でレジリエンスの低い人の特徴として、100点でなくれば0点という極端な考え方をするという傾向があります。
ネガティブにならず、しかし無理やりポジティブになろうとせず、「これはこれで良いだ」とありのままの自分を受け入れるところから、レジリエンスは始まります。
④人に頼る
-1.jpg)
レジリエンスを高める、というと自分ひとりの意志だけで精神的な面から強くなれば、と考えてしまうかもしれません。意志によって高める、というのはあながち間違いではありません。
しかし、それは自分ひとりだけの闘いでは決してありません。適切なタイミングで適切な人に頼るのは、むしろレジリエンスを高めるための必要不可欠なポイントでもあります。
カウンセラーによるカウンセリングを受ける、精神的にまいっている場合は心療内科を受診する、などという方法もありますが、そこまで思いつめなくても大丈夫。
家族や友人に話を聞いてもらう、雑談したりするだけでも、十分心の負担は軽減します。
気分が落ち込んだ場合はじっくり聞いてくれるこの友人に、気分をガラッと変えて心弾むことをしたい場合は、笑い飛ばしてくれるポジティブなあの友人に、と頼る先を増やしていくことが重要です。
【最後に】
.jpg)
いかがでしたでしょうか。極私的レジリエンスの高め方として、以上4つをおすすめしました。
- スモールステップを大切にする
- 日常の小さな習慣を大切にする(朝同じ時間に電気を点ける、お散歩に行くなどでも◎)
- 認知の歪みを治す
- 人に頼る
何より大切なのは、「変わりたい」「立ち直りたい」という自分の本音に素直になり、自分を信じることです。レジリエンスは才能ではなく、育てられるスキルです。小さな習慣や意識の積み重ねで確実に育てることができます。
筆者は実際にこの経験を積んだあと、大概のことには動じなくなり、友人や家族からは「レジリエンスの化け物」と呼ばれるまでになりました。
自分の経験をこのように言語化し、開示できるようになったのも、レジリエンス力を育てたから。
今回ご紹介したレジリエンスの高め方は、極私的です。しかし、たかが一例されど一例。VUCA時代を生きている皆さんに、少しでもこの記事がお役に立てることを祈っています。
最後に、筆者の好きな言葉をご紹介します。
「つまずいたのは 誰かのせいかもしれないけど 立ち上がらないのは 誰のせいでもない」
ご拝読ありがとうございました!