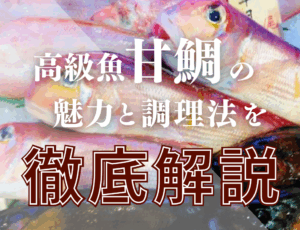【2025年4月最新】アメリカで検索急増中の注目ワークアウトTOP5を解説!

フィットネストレンドの発信地・アメリカでは、コロナ禍をきっかけに、「鍛える」から「整える」へと健康に対する考え方が変わってきています。
そんな中、米Googleが毎年発表している検索レポート「Year in Search(年間検索ランキング)」では、今アメリカで注目を集めているワークアウトが明らかになりました。
今回は、検索数が大きく伸びた話題のワークアウトTOP5をご紹介。
人々のリアルな関心が反映されたデータをもとに、今の時代に合ったトレーニングスタイルを紐解いていきます。
第5位:Boat Workout(ボートワークアウト)

水の上で全身トレーニング!今注目の“ボートワークアウト”
第5位にランクインした「ボートワークアウト」は、実際のボート上で行うエクササイズや、ボートを漕ぐ動きを取り入れたトレーニングとして注目を集めています。
バランスを取る動作の中で自然と全身の筋肉が使われるため、特に脚・背中・腕・体幹といった主要な筋肉を効率よく鍛えられる、機能性の高いワークアウトです。
このユニークなトレーニング法が広まり始めたきっかけは、TikTokやInstagramなどのSNS。
流行に敏感な10〜30代の間で人気が高まりましたが、バランス感覚を養いたいヨガ愛好者や、体幹を重視するアスリートなど、上級者層からの支持も集めています。
さらに「ボートワークアウト」は、夏のアウトドアシーズンになると、SUPヨガ(スタンドアップパドルボードヨガ)や水上トレーニングといった“水上フィットネス”の一環としても注目され、アメリカの多くのメディアで紹介されました。
楽しく全身を鍛えられる新感覚のワークアウトとして、今後ますます人気が高まっていきそうです。
ボートワークアウトの基本的な動作

●Catch(キャッチ)
膝を曲げ、前傾姿勢でハンドルを握ります。背筋はしっかりと伸ばし、肩と腕の力を抜いてリラックスさせましょう。
●Drive(ドライブ)
脚の力でしっかりと押し出しながら、体を後方に引き、ハンドルを胸元まで引き寄せます。この動作では、脚・背中・腕の筋肉を同時に使うため、全身を効率よく鍛えることができます。
●Finish(フィニッシュ)
脚を完全に伸ばした状態で、ハンドルを胸の下あたりまで引き寄せます。背中はやや後ろに倒し、腕は肘を曲げた状態でハンドルを保持します。
●Recovery(リカバリー)
腕を前に伸ばしながら、体を前傾させ、膝を曲げて元の姿勢に戻ります。このリカバリーフェーズでは、筋肉をリラックスさせて、次のストロークに備えます。
これらの動作を繰り返すことで、全身の筋肉をバランスよく鍛えることができる。
第4位:28 Day Calisthenics Workout(28日間のチャレンジ型体操)

ビフォーアフター続出!今注目の体操チャレンジ
自重を使った筋力トレーニングを28日間にわたって行う「28 Day Calisthenics Workout」は、体幹の強化や全身の引き締めを目的としたプログラム。
期間と目標が明確に設定されているため、「最後までやり切った」という達成感が得やすく、近年は“チャレンジ系ワークアウト”の代表格として人気を集めています。
なかでも注目を集めたのが、TikTokでの広がりです。「#28daycalisthenics」のハッシュタグには3,000万件以上の投稿が集まり、世界中のユーザーが参加。
「1日目」「14日目」「28日目」と、体の変化を記録したビフォーアフターの写真や動画を投稿する動きは、今や新しいフィットネス文化のひとつになりつつあります。
このワークアウトに挑戦するのは初心者が中心ですが、「とりあえず28日間やってみたい」「自分にもできるか試してみたい」と、前向きな気持ちで始める人が多いのが特徴です。
また、「途中で挫折した…」といった失敗談やリタイアの様子も投稿されており、リアルな記録が共感を呼んでいます。こうした“過程を共有する”というスタイルは、SNS時代ならではのフィットネスの楽しみ方と言えるかもしれません。
28日間チャレンジ:3日間のサンプルメニュー

Day 1:全身基礎トレーニング
- 手足を大きく開いて跳ぶ有酸素運動:2分間
- アームサークル(腕回し運動):各方向1分間
- レッグスウィング(脚を前後に振る運動):各脚1分間
- 腕立て伏せ:3セット × 10〜15回
- スクワット:3セット × 15〜20回
- プランク(全身を支える体幹トレーニング):3セット × 20〜30秒
- リバースランジ(後ろ足を引いてしゃがむトレーニング):3セット × 各脚10回
- ストレッチ:トレーニングした筋肉を中心に実施
Day 2:休息とリカバリー
- 軽いウォーキングやストレッチを行い、体をリラックスさせる。
- 十分な水分補給とバランスの取れた食事を心がける。
Day 3:上半身強化
- アームサークル(腕回し運動):各方向1分間
- ショルダータップ(肩にタッチする体幹トレーニング):1分間
- ジャンピングジャック(手足を同時に開いてジャンプする運動):2分間
- 腕立て伏せ:3セット × 12〜15回
- 椅子を使った腕立て伏せ(後ろ向き):3セット × 10〜12回
- スーパーマン:3セット × 15〜20回
- マウンテンクライマー(腕立て伏せの姿勢で足を交互に素早く引き寄せる運動):3セット × 20〜30秒
- ストレッチ:上半身を中心に実施
第3位:LE SSERAFIM Workout(ルセラフィム ワークアウト)

“アイドルみたいに鍛える”が新常識?最新K-POPワークアウト
息を呑むようなキレのあるパフォーマンスで知られる、韓国発の人気ガールズグループ・LE SSERAFIM(ルセラフィム)。
1stフルアルバム『UNFORGIVEN』(2023年5月リリース)は、韓国の音楽チャートで1位を獲得し、全米でもBillboard 200のトップ10入りを果たすなど、グローバルで高い評価を得ました。
「肉体の限界に挑戦する」という信念を掲げる彼女たちは、鍛え抜かれた身体と圧倒的な表現力で、世界中のファンを魅了しています。
そんなルセラフィムにインスパイアされた「ルセラフィム ワークアウト」は、“アイドルと同じトレーニングに挑戦する”という新しいムーブメントを生み出しています。
ストイックな運動メニューであるにもかかわらず、TikTokをはじめとするSNSでは、多くのファンがその内容に挑戦する様子をシェアしており、大きな話題を呼んでいます。
楽しみながら身体を動かす「エンタメ×フィットネス」のスタイルは、もはや現代のトレーニングの新しいかたち。
エクササイズが「やらなければならないもの」から「やってみたいもの」へと変わりつつある今、ルセラフィム ワークアウトはその流れを象徴する存在となっています。
「ルセラフィム ワークアウト」のメニューは以下の内容で構成

- ジャンピングジャック(手足を同時に開いてジャンプする運動) 100回
- バーピー (しゃがむ→腕立て→ジャンプを繰り返す運動)100回
- ジャンプスクワット(スクワットの姿勢からジャンプする運動) 10回 × 2セット
- プランククロール(楽曲「Fearless」に合わせて)(プランク姿勢で腕を交互に前に動かして進む運動)
- プランク・アップ&ダウン(プランク姿勢から腕立て伏せの姿勢へ上下する運動) 10回 × 2セット
- プランクツイスト(プランク姿勢で腰を左右にひねる運動) 10回 × 2セット
- 腹筋運動 25回 × 3セット
第2位:Indoor Walking Workout(室内ウォーキング ワークアウト)

月間1万件検索!話題の「室内ウォーキング」って?
Googleの検索データによると、「室内ウォーキング ワークアウト」は月間で最大1万件の検索数を記録し、注目を集めています。
室内を歩くだけというシンプルな内容ながら、有酸素運動としての効果が高く、誰でも取り組みやすいフィットネスとして人気。
YouTubeをはじめとするSNSでは、「22分で脂肪を燃やす室内ウォーキング」や、「60代からの室内8000歩プログラム」など、年齢層や目的に応じた多彩なコンテンツが投稿されています。
専門家による指導動画も数多く公開されており、自宅で質の高いトレーニングが可能です。
在宅勤務の普及を背景に、「外に出なくても健康管理ができる」という発想が定着しつつあることにも注目。忙しい日々の中でも、スキマ時間を使って運動不足を解消できる点が支持されている理由のひとつです。
また、運動初心者でも取り組みやすく、ダイエットを始めたばかりの方や、産後のリハビリを目的とする女性などからも注目を集めている。
とくに評価されているのが、その“継続のしやすさ”。特別なシューズやウェアを準備する必要がなく、天候にも左右されないため、自宅の一角で気軽に始めることが可能。
歩くペースや時間を自由に調整できるため、無理なく継続できる点も魅力です。
朝のウォームアップや夜のリフレッシュなど、1日10分程度からでも効果を実感しやすく、音楽や動画を楽しみながら行える“ながら運動”としても生活に溶け込みやすくなっています。
「室内ウォーキング ワークアウト」の基本的な運動方法

1. その場足踏み(マーチング)
- その場で足踏みを行い、腕を大きく振ることで、心拍数を上げ、有酸素運動の効果を高める。
2. もも上げ(ハイニー)
- 膝を腰の高さまで持ち上げるように足踏みを行う。腹筋や股関節周りの筋肉を強化するのに効果的。
3. サイドステップ
- 左右に一歩ずつ足を踏み出す動作を繰り返す。下半身の筋力強化やバランス感覚の向上に役立つ。
4. お尻キック(バットキック)
- かかとでお尻を蹴るように足を後方に引き上げる。太ももの裏側やお尻の筋肉を鍛えるのに効果的。
5. 腕をぐるぐる回す運動(アームサークル)
- 腕を大きく回す動作を加えることで、肩周りの柔軟性を高め、上半身の血行促進にもつながる。
第1位:Somatic workout(ソマティック ワークアウト)

がんばらない運動がいい。自分を癒す“ソマティックな習慣”
第1位にランクインした「ソマティック・ワークアウト」は、身体の内側に意識を向けながら、ゆっくりとした動きで心と体のつながりを高めていくエクササイズです。
筋力の向上や見た目の変化を目的とするのではなく、身体の緊張をほどき、ストレスや感情の解放を促すことに重きを置いています。
「ソマティック(身体感覚)」に焦点を当てたワークアウトが検索上位に入った背景には、単なるシェイプアップではなく、“心と体の調和”や“自己回復力”といった新たな価値観の広がりがあります。
ヨガや太極拳、フェルデンクライス・メソッドなども、こうしたソマティックな要素を含む代表的な実践法とされており、心身のバランスを整える手段として再注目されています。
コロナ禍以降、リモートワークやSNS疲れといった精神的なストレスを抱える人が増える中、「リラックスしながら整える」というアプローチが支持を集めています。
過去数年にわたって人気を博したHIIT(高強度インターバルトレーニング)などの追い込み型ワークアウトから、穏やかで内省的な運動へと関心が移りつつあるのも、興味深い変化といえるでしょう。
「ソマティック・ワークアウト」は、ストレスマネジメントやウェルネスへの関心が高い層に支持されており、TikTokやYouTubeではマインドフルネス系のエクササイズ動画として広がりを見せています。
とくに20〜40代の女性を中心に、「痩せたい」「鍛えたい」といった外見重視の動機よりも、「心を整えたい」「自分に優しくしたい」といった内面的な目的から取り組むケースが増えているようです。
また、過去にハードなトレーニングで挫折した経験のある人が、無理なく続けられる健康習慣として取り入れる例も目立っており、年齢や運動経験を問わず幅広い層に受け入れられています。
「ソマティック・ワークアウト」の基本的な運動例

1. Body Scan(ボディスキャン)
- 静かに座るか横になり、足先から頭頂まで順に身体の各部位に意識を向ける。
2. Pandiculation(パンディキュレーション)
- あくびをするように、筋肉をゆっくりと収縮させた後、自然に緩める。筋肉の緊張をリセットし、自然な動きを回復させる。
3. Somatic Stretching(ソマティック・ストレッチ)
- 背中を丸めたり反らせたりする「キャット・カウ」など、ゆっくりとした動きを行う。筋肉の緊張を和らげ、柔軟性を高める。
【総括・これからのワークアウトはどう変わる?】

今回のランキングから見えてくるのは、「運動=キツいもの」というイメージが少しずつ変わりつつあるという点です。
最近のフィットネストレンドでは、「家でできる」「気軽に始められる」「自分のペースで進められる」といった“やさしさ”に価値を置くスタイルが広がっています。
コロナ禍を経て定着した“おうち時間”の中で、ジムに通わなくてもできる運動や、自分の気分や体調に合わせて取り組めるメニューに人気が集中。
体を鍛えるだけでなく、ストレスを和らげたり、気持ちを整えたりする。そんな“心のための運動”が、多くの人に求められるようになってきました。
なかでも、1位となった「ソマティック・ワークアウト」は、まさに“心と体を同時にケアする”運動法です。
体の内側に意識を向けながら、ゆっくりと動き、深く呼吸することで心身をリセットしていきます。「無理をしない」「がんばりすぎない」という考え方が、今の時代の空気感と自然に重なっているのかもしれません。
そしてもう一つ、見逃せないのがSNSとの親和性です。
運動の成果を写真や動画で共有する「ビフォーアフター」投稿や、「#28daychallenge」のようなチャレンジ企画が、参加者のモチベーションを後押ししています。
ただ成果を見せるだけではなく、「日々のプロセス」を記録し共有することで、共感や励ましが生まれているよう。
また、K-POPアイドルのトレーニングに挑戦する「ルセラフィム ワークアウト」のように、エンタメと運動が融合したスタイルも登場。
“推し”と同じトレーニングに取り組むことで、運動そのものが「趣味」や「楽しみ」へと変わってきているのも、現代ならではの現象と言えるでしょう。
「室内ウォーキング」のようにスキマ時間でできるメニューや、「ボートワークアウト」のような新感覚フィットネスも人気を集めており、忙しい日常の中でも続けやすく、楽しく取り組めることが、多くの人に選ばれている理由となっています。
フィットネスは今や、“鍛えるため”の行為から“自分を整えるため”の時間へと、その役割を変えつつあります。
我慢や根性で乗り切る時代は終わりを迎え、気持ちよく体を動かすこと、自分のリズムで向き合うこと、そして“自分らしい方法”を見つけることが、これからのフィットネスの軸になっていくはずです。
さらに注目したいのは、フィットネスが「個人のストーリー」として語られるようになった点です。
単に「筋肉をつけた」「体重を減らした」という成果だけではなく、「1日目と28日目で自分がどう変わったか」「忙しい育児の合間に取り組んだ15分」など、“日々の体験そのもの”が共有され、共感を呼び、次のチャレンジへとつながっていきます。
年齢やライフステージに応じたメニューの多様化も、現在のトレンドを象徴するポイントです。
たとえば、更年期女性に向けたホルモンバランスを意識した運動や、シニア層に向けた転倒予防トレーニング、さらには子どもと一緒に取り組めるファミリー向けのプログラムまで、“ひとりひとりに合ったフィットネス”が急速に増えています。
これは、「万人向けの正解」から、「個人の暮らしに寄り添う提案」へと大きく舵を切っている証といえるでしょう。こうした動きを受けて、フィットネスは“意識が高い人だけの習慣”ではなく、“暮らしの一部”として自然に定着しつつあります。
たとえば、料理や洗濯と同じように、日常の中に「ちょっとした体のケア」を組み込む。数分でも「今日、自分のために動けた」という感覚が、自信や安心感につながっていくようになっています。
アメリカ発のこうしたフィットネスの新潮流は、今後日本をはじめ世界中へと広がっていくでしょう。
トレンドを追うだけではなく、自分に合ったスタイルを探し、自分の暮らしに取り入れていく。そんな“心地よい運動との向き合い方”が、これからのフィットネスには求められているのかもしれません。