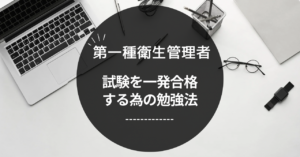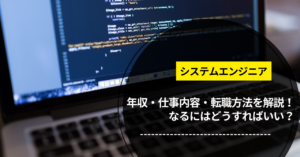リラックス効果抜群!お風呂好きに贈る入浴剤ランキングBEST10
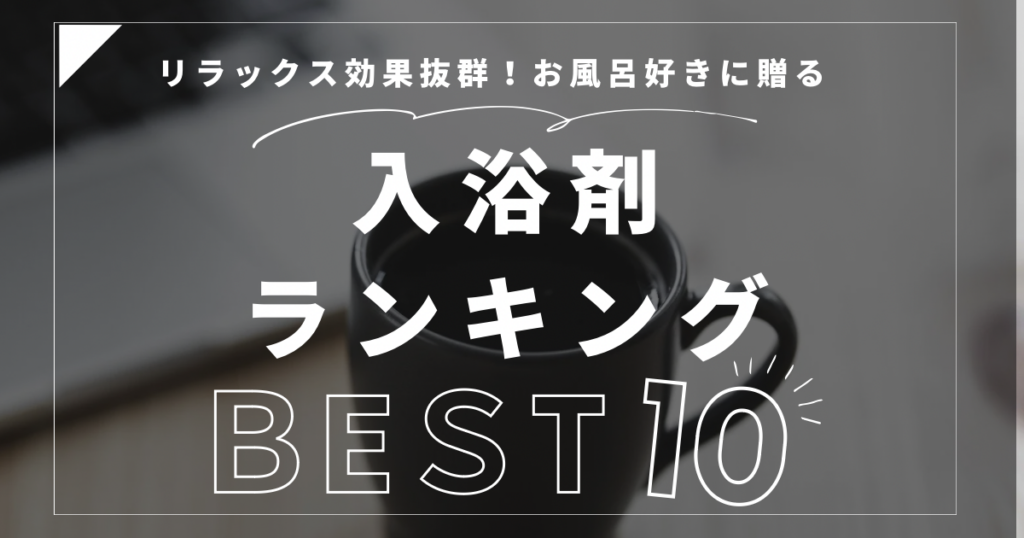
バスタイムが大好きな人におすすめの入浴剤をランキング形式でご紹介し、2024年最新の入浴剤情報をお届けしています。
リラックス効果や香り、効能などを比較して、あなたにぴったりの入浴剤を見つけてみてくださいね。
1.入浴剤の効果とは?

入浴剤には多種多様な効果が期待できますよね。
日頃のバスタイムをいつも以上にリラックスできるものにするために、その効果と仕組みについて詳しく説明していきます。
①保湿効果: 入浴剤にはお肌のうるおいをケアする成分が多く含まれています。体中の角質層の隅々までうるおいが届き、モチモチ肌になります。
②血行促進効果: お湯の温熱効果による血行促進を補助し、血流を改善します。血行が良くなれば疲労物質が排出され、疲れが取れます。
③保温効果: 入浴剤は肌表面のたんぱく質とくっついて全身に絹のようなヴェールをつくります。そのためお湯から出た後も熱が逃げず、湯冷めもしにくくなります。
④清浄効果:成分によっては皮脂や汚れを落す清浄効果を高めるものがあります。重曹や酵素が配合された入浴剤は、なめらかでクリアなつやつや肌を形成します。
⑤リラクゼーション効果: 入浴剤には芳香療法に繋がるものもあります。心地よい香りを嗅ぐことで体の芯から安心感やリラックス感を得ることができます。
⑥清涼効果: 夏場は清涼効果のある入浴剤が効果的です。汗ばむお風呂上がりも、べたべた感が吹き飛ぶような爽快感がたまりませんね。
このように入浴剤は種類によって、多種多様な効果を持っています。
好みやその時の体調に合わせて選び、ステキな入浴時間にして下さい。
2.入浴剤のリラックス効果

日々の生活の中で溜まっていく身体の疲労や精神的な疲労が抜けきれない方は少なくないですよね。
入浴剤は、香りや色などによって癒しの効果を得ることができるため、リラックス効果が非常に高く、身体に対する保温効果が高いものや、疲労回復に非常に効果があると言われています。
特に、炭酸ガス入りのシュワシュワする入浴剤には血管の拡張作用があり、血流を促進する効果もあるため、老廃物を効率よく排出してくれます。
疲労回復の効率を高めるためには、ぬるめのお湯にゆっくり浸かるとより効果的といわれてます。
3.入浴剤の美肌効果

入浴剤には、肌の角質層を整えてツヤツヤにするものや、保湿をして肌をしっとりモチモチにさせる美容効果があるものもあります。
肌をしっとりツルツルにするなら重曹や酵素が入った入浴剤が、保湿をしたいならセラミド、ヒアルロン酸、酒粕、米ぬかが入っているものもあり、どれもオススメしたい内容となっています。
また、美肌効果がある温泉由来の成分が入った入浴剤もたくさん販売されています。
4.おすすめの入浴剤紹介

ここからはぜひ読者の皆様におすすめしたい入浴剤についてランキング形式紹介し、併せてと香りの種類についても紹介させて頂きます。
①人気のブランドランキング
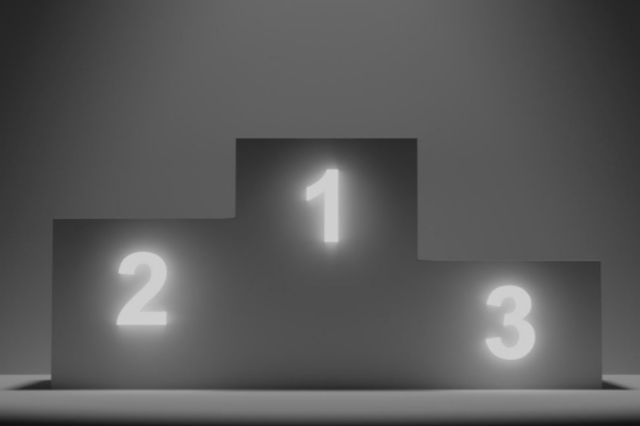
のんびりと風呂で過ごしたいときに使いたい入浴剤。
温浴効果による疲労回復効果を持つ薬用タイプやスキンケアタイプと言ったように数多くの種類がありますが、口コミだけでは選べないという方も多くいるのではないでしょうか?
ここからは、効き目にこだわった商品をメインにランキング形式で紹介します。
頑張った自分へのご褒美、またお友達や大切な人へのギフトとして、素敵な時間を過ごせる入浴剤を見つけてくださいね。
【1位】ボトルワークス「アンプルショット 薬用リセットスパ バスタブレット」
お休み前に疲労をほぐす、薬用炭酸バスタブレットです。
ビックタブレットから発泡される炭酸と有効成分がお湯に溶け込み、温浴効果を高めて血行を促進。
カラダの芯まで温めて、日々の疲れも確実にリセットされる入浴剤です!
とてもなめらかでしっとりとした肌ざわりのお湯が特徴で、優しいローズの香りが印象に残ります。
ご自宅でスパ気分が味わえるのは最高です!
【2位】別府温泉 薬用 湯の花
別府明礬温泉 薬用「湯の花」は大分県別府市の別府明礬温泉の「湯の花」を使って作られている入浴剤です。
その名の通り「医薬部外品」として販売されており、一定の効果・効能に有効な成分が含まれている入浴剤です。
現地の温泉に近く、満足度もお墨付きの逸品です。
一度入ってみると、その再現性にビックリさせられます。
湯上がり後も、心地良い温かさとしっとり感を肌で感じること間違いなし。
自宅で別府温泉を味わえる、最高の逸品となっております。
【3位】PR IL-CORPO(イルコルポ) シーボディ ミネラルバスパウダー
保温性にとても優れたミネラルバスパウダーの商品です。
豊富なミネラルが発汗作用を促し、体内の代謝をあげて脂肪を燃焼しやすい体質作りが叶います。
またユーカリを基調とした爽やかでスッキリしたタラソな香りが、心体ともリラックス効果を高めること間違いなしです。
【4位】Sea Crystals(シークリスタルス) エプソムソルト
エプソムソルトとは硫酸マグネシウムのことを意味します。
特徴としては塩ではないので浴槽を傷めることもなく、無色無臭なので香りが苦手な人にもおすすめしたい一品です。
国産というところもこの商品の強みで、バブちゃんでも安心して使用できる浴用化粧品となっています。
【5位】花王 バブ 6つの香りお楽しみBOX
読者の皆様にとっても馴染み深い商品ですよね。
人気がある6種類の香りがセットとなった大容量タイプの商品です。
この商品の特徴は大きな粒がゆっくり溶けながら発泡することで炭酸が溢れ出します。
繊細な沢山の泡が効果を高めます。
疲労回復・肩こり・腰痛・冷え性への効果が期待できる内容となっています。
保湿成分が多く含まれているので湯上がり後の肌はしっとりなめらかになること間違いなしです。
【6位】Kneipp(クナイプ) バスソルト サンダルウッドの香り
この入浴剤は天然岩塩に2種類のハーブを配合したもので、心身ともに安らぎを感じるバスタイムを楽しむことができます。
イライラした気分や、落ち着かない気分を鎮めたいとき、不安や緊張をほぐしたい時に使用すると効果的です。
毎日頑張っているそこのあなたにおすすめです。
【7位】バスクリン くつろぎの宿 しっとりごこち
バスクリンのくつろぎの宿シリーズは、温泉気分を味わえる濁りと湯の感触が特徴の入浴剤です。
この商品は、そんなくつろぎの宿シリーズのなかでも特に保湿力が高く、お風呂あがり後もベールをまとったようなしっとり感が持続するものとなっています。
肌が荒れがちな冬の時期にもありがたい温泉ミネラルが大量に含まれているため、スキンケア効果も得られるのでおすすめです。
【8位】花王 キュレル 入浴剤
「お肌への優しさが欲しいしけど手頃な入浴剤が欲しい」という人には、『花王』が提供する “キュレル入浴剤” がおすすめです。
セラミド機能成分やユーカリエキスの潤い成分が角層の奥深くまで浸透し、冬場のカサカサ肌をしっとりモチモチに保湿してくれます。
さらに、コメ胚芽油を配合することで、肌荒れや湿疹への効果も期待できます。
詰め替え用もあり、経済的な負担が少ないこともお買い得で助かりますね。
【9位】第一三共ヘルスケア ミノン薬用保湿入浴剤
お風呂に入れるとまるでクリームのような湯触りへと変化する全身を優しく包む入浴剤です。
低刺激、弱酸性、アレルギーテスト済みで、敏感肌やアトピー肌の人でも安心して使用できるものとなっています。
有効成分として、デリケートな肌に優しく潤いを与えるアミノ酸保湿成分と湿疹を和らげるグリチルリチン酸2Kが配合されています。
そのため、強烈な乾燥肌にも『ミノン』の入浴剤が活躍します。
【10位】サボン バスソルト ローズ
このバスソルトは、ミネラルいっぱいの死海の塩に、エッセンシャルオイルと可憐な花びらが入った商品となっています。
お湯をはった浴槽にひとつまみ落とせば、死海のミネラル分がたっぷりと溶け出します。
ぬるめのお湯でゆっくりと入浴することで発汗作用が高まり、内側からキュッと引き締まった状態にしてくれます。
汗をたくさんかくことで代謝も上がります。
②香りの種類など

世の中には多種多様に及ぶ香りがありますが、一般的に大きく7つのジャンルに分けられるとされています。
(1)オリエンタル:濃厚な甘さや樹木を感じる神秘的な香り
(2)ハーブ:爽快感や清涼感を感じさせる香り
(3)ウッディ(樹木):森林浴をしているような、すがすがしさを感じる香り
(4)フローラル:まるで花畑にいるような甘く華やかな香り
(5)シトラス:柑橘系のみずみずしい香り
(6)スパイス:ピリッとするような、刺激的な香り
(7)樹脂:重厚感を感じる甘い香り
7つのジャンルは花や果実、樹木などから構成されていますが、それぞれの特徴を把握しておけば、入浴剤はもちろん、アロマや香水などの香りを選ぶ時にも役に立ちますよね。
また、香りを嗅ぐことで気持ちが落ち着いたり、モチベーションが上がったりする効果もあります。
好きな香りを選ぶのはもちろんですが、自分のイメージした通りの匂いや、その時の気分に合わせて香りを選ぶことが最高のバスタイムを過ごすための秘訣です。
5.入浴剤の選び方

入浴剤の効果は多種多様に及びます。
その日の気分によって、またどのような効果が欲しいかなどによって使い分けると良いでしょう。
例えば季節に合わせて使い分けるのも良いですよね。
汗ばむ季節には清涼感や爽快感のある入浴剤がおすすめですし、冷える季節には保温効果が期待できるものを選ぶのが妥当ですよね
①自分に合った入浴剤の選び方
入浴剤は使用目的や成分に応じて、「医薬部外品(薬用入浴剤)」または「化粧品(浴用化粧料)」に分別できます。
医薬部外品の入浴剤は、温浴効果による疲労回復や肩こり、冷え性、肌荒れなど、法律で承認を受けた効能効果が期待できます。
一方、化粧品としての入浴剤は配合成分によって、皮膚に潤いを与える保湿効果や皮膚の汚れを落としやすくする効果などが期待できます。
②用途に応じた入浴剤の選び方
入浴剤にはその用途に合わせた様々な使い方があります。
その種別についてご紹介します。
(1)お風呂上がりの乾燥をどうにかしたい
保湿効果をより実感したい方には、保湿成分が入ったバスミルクやバスオイル系浴用化粧料をおすすめします。
米胚芽油、ホホバオイル、セラミド、ヒアルロン酸など含有される成分は製品によりますが、赤ちゃん用や敏感肌用と記載されたものにすれば間違いないです。
無香料・無着色など、特に皮膚への低刺激に配慮され、保湿効果が高いことが多いためです。
(2)かかとやひじなどの角質ケアをしたい
かかとやひじなどのガサガサをどうにかしたいという方は、酵素が入った浴用化粧料を選ぶと良いでしょう。
酵素の成分で古くなった角質が分解され、汚れを落としてくれる効果が期待できるからです。
酵素はパパイン酵素、米ぬかなど多種多様です。
「かかとのガサガサが気になる」という時には、1週間に1回ペースで使用してみるとよいでしょう。
(3)疲労回復、冷え性・肩こりを良くしたい
保温効果を実感したいなら、「炭酸ガス系」と液体の「薬湯風呂系」の薬用入浴剤がおすすめです。
炭酸ガス入りの入浴剤を使うと、温浴効果により、血管が広がり血流が増加、全身の新陳代謝が促進され疲労回復効果や痛みの緩和効果などにつながります。
炭酸濃度が60ppm以上あれば血流が良くなるという研究報告もありますので、ひとつの目安にしてみてはいかがでしょうか。
6.入浴剤の使い方

入浴剤を使用する際は、自分の肌質や目的に合ったものを選ぶことが重要となってきます。
例えば肌の乾燥が気になる方は保湿成分が豊富なものを、疲れを取りたい方にはリラックス効果のある成分が豊富に含まれたものを選ぶと良いでしょう。
さらに、入浴剤の香りや色も気分をリフレッシュさせるポイントになります。
自分の体質や目的に合った入浴剤を選ぶことが、心地よいバスタイムを演出する鍵となるのです。
入浴剤を効果的に使う方法
①ぬるめのお湯に入れる
お湯の温度は約38〜40℃で設定し、ゆっくりのんびりと時間をかけて浸かりましょう。
ぬるめのお湯にゆっくりと入浴することで、就寝前に自律神経が整われて、睡眠の質が向上すると言われています。
熱いお湯を好まれる方もいますが、実は湯温が高すぎることで入浴剤の有効成分が薄れてしまい効き目が悪くなることも。
更に、体への負担がかかってしまうなど、リラックスとは逆の影響を受けることもあるのです。
②入浴する前に溶かしておくべき
入浴剤は入浴する前に湯船に入れ、完全に溶けてから浸かるようにしましょう。
入浴剤は、お湯に完全に溶けてこそ効果を発揮します。
特に炭酸ガス系の入浴剤は、お湯に入れると「しゅわしゅわ~」となり、溶けている最中の泡に効果がありそうに見えますよね。
ですが、実は泡が確実にお湯に溶け込むことで効果を得られるため、溶け切るまで待ってから入浴するのがおすすめです。
また、溶けた炭酸ガスは時間経過によって抜けきってしまいます。
入浴剤を溶かしたら、2時間以内には入浴することをおすすめします。
③上がる前に洗い流さない
入浴剤を入りの湯船から出た際は、シャワーで洗い流すことはおすすめできません。
特に保湿効果入りの入浴剤には、肌の表面に絹のようにヴェールが形成され、肌の乾燥を防いでる状態です。
ついついいつものようにシャワーで洗い流しいたいところですが、保湿効果が弱まったり、逆に肌の乾燥が進行してしまうことも考えられます。
湯船から出た後はタオルでさらっと水分を拭き取るくらいにしましょう。
ただし万が一ですが、入浴剤で肌に異常が出た際は、早急に洗い流しましょう。
7.入浴剤の注意点

入浴剤は、リラックスしたい時や疲れを取りたい時に使用する人が多いでしょう。
しかし、入浴剤には種類や効果が多種多様である反面、使用法を守って正しく使わないと逆効果になることもあるのです。
実際に使用する前に商品のラベルや説明書をよく読み、指定された量や浸かる時間を守ることが大切です。
また、肌トラブルやアレルギーのある人は事前に医師に相談し、インターネットで調べることをおすすめします。
肌トラブルの予防法
入浴剤によってはアレルギー反応や肌トラブルを起こしてしまう方もしばしばも居ます。
入浴剤に含まれる香料や着色料、防腐剤などが原因となり、かゆみや発疹、赤みなどの症状が出ることもあります。
特に敏感肌やアトピー性皮膚炎の方は注意するべきです。
入浴剤のトラブル防止のためには、以下の点に注意しましょう。
①湯温を高くしすぎない
②使用前に少量を手や足につけてパッチテストを行う
③成分表示をよく読んで自分に合わなそうなものは避ける
④使用後は保湿クリームなどを活用し肌の乾燥を防ぐ
⑤使う回数や量を控える
まとめ

豊かなバスタイムを演習するために様々な入浴剤について紹介させて頂きました。
入浴剤を安全に使用するために、自分に合ったものを選ぶことや正しい使用法を守ることが大切だということを忘れないように。
肌トラブルやアレルギーがある場合は医師に相談することも忘れたらいけません。
日頃の疲れを癒すため、リラックスや疲労回復に役立てるために、入浴剤を有効的に活用していきましょう!