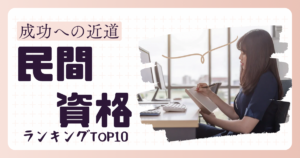【2024年】お花見で満開の桜と写真を楽しむための方法
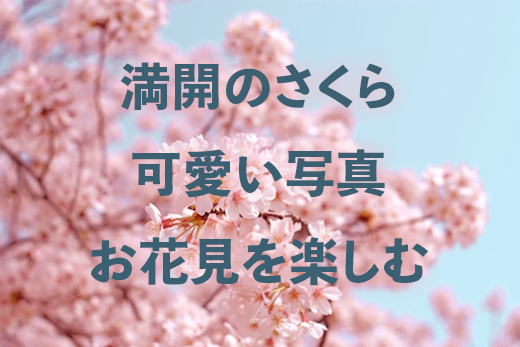
桜の品種と開花の目安、子どもと桜をうまく写真に写すコツをまとめました。
新入園、新入学の思い出や春の思い出に可愛い子どもの写真を撮りたいけれど、上手に撮れるか心配な方は必見です。
ソメイヨシノだけじゃなく早咲きや遅咲きなど様々な種類の桜を見つけて満開の桜を親子で楽しみましょう。
最後には桜のイベント情報も載せているのでお花見を楽しみましょう。

もうすぐお花見シーズンですね。
お花見といえば桜並木の下を散歩したりドライブしたり、ピクニックやバーベキュー、屋台で美味しいものを買って食べたりする楽しみもありますよね。
ところで、桜には種類があることをご存知ですか。
ソメイヨシノという種類は聞いたことがあるのではないでしょうか。
他にもカワヅザクラ、ヤエザクラなど耳にしたことがあると思います。
種類によって咲く時期が少しずつ違うので、それを知っていれば何度も満開を楽しむことができます。
桜の色味も白に近いものからピンクの濃いものまで様々で違う魅力があります。
全部の品種は多すぎて紹介できませんが、都内で見られる有名な桜や珍しい桜をピックアップしました。
せっかく綺麗に咲いている桜とお花見を楽しんでいる子どもの様子を写真で撮ろうと思った時、木の上の桜と一枚の写真に収めるのは難しいですよね。
記事の後半にはうまく写真を撮るコツ、テクニックをまとめています。
桜に関するイベント情報もあります。
今年はソメイヨシノだけじゃないお花見を、いつもとは違う撮影テクニックを使って楽しんでみるのはいかがでしょうか。
1.2024年の開花予想

2月22日に今年の開花予想第5回が発表されています。
この発表によると東京の開花予想日は3月22日です。
今年は例年に比べてやや早い予想です。
満開まではだいたい6日から9日間なので3月30日か31日の土曜日と日曜日にはお花見をする方が多くなると予想されます。
全国の開花予想では、名古屋は3月19日、福岡は3月21日、大阪は3月24日、仙台が4月3日です。
鹿児島の3月30日をのぞいて例年より早い予想がされています。
この開花予想はソメイヨシノの開花の予想です。
大きなソメイヨシノの木がピンク色一色になる様子は見応えがありますね。
特に桜並木やたくさんのソメイヨシノの木が集まっているお花見スポットと呼ばれているような場所では、見上げると一面が春の青い空とピンク色になっていて春ならではの色がとても素敵です。
ライトアップされた夜桜も魅力的ですよね。
今年も満開のソメイヨシノが楽しみです。
2.桜の品種

お花見といえば満開のソメイヨシノを愛でるのが一般的ですが、満開の期間があっという間でうまく休日に当たらなかったり、お天気が悪くてお花見できずに散ってしまったという経験はありませんか。
散ってしまって風に舞う桜の花びらも素敵ではありますが、やはり満開の桜を楽しみたいですよね。
実は桜は品種によって1月中旬から5月初旬まで楽しむことができるのです。
ソメイヨシノとはまた違う魅力がある桜もたくさんあるので、ソメイヨシノのお花見ができなかったとしても諦めてはいけません。
春の間には何度も満開の桜を愛でるチャンスがあるのです。

写真はカワヅザクラ(河津桜)です。
カワヅザクラは早咲きの桜としてとても有名です。
大きな花と濃いピンク色が特徴で1月下旬ごろには開花して1ヶ月ほど花が咲き続けます。
2月中旬ごろに例年満開になっています。
この桜は最近あちこちで見かける桜の一つですが、元は自然交配種と考えられているそうですよ。
東京では江戸川区の河川敷沿い、西ヶ原みんなの公園などで見られます。
カンヒザクラ(寒緋桜)も早咲きの桜です。
この桜はカワヅザクラよりもさらに花の色が濃いピンク色をしています。
花は小さく下向きに咲き、花びらが散るのではなく落下するのが特徴です。
早咲きの桜として有名で東京での開花時期は3月初旬ごろになることが多いようです。
皇居東御苑、井の頭公園で見られます。
暖かい地域に植えられていることの多い品種で、沖縄などでは1月中旬ごろから開花しているようです。
トイザクラ(土肥桜)は日本一早咲きの桜と言われています。
例年12月下旬にはつぼみが出て1月中旬から2月中旬が見頃となっています。
赤みの強い花を咲かせる木と薄いピンクの花を咲かせる木があり、同じ品種でもその木によって咲かせる花の色が違います。
今年の見頃は残念ながらすでに終わってしまっています。
この桜は伊豆の土肥で見られます。
土肥では土肥桜に関するイベントも毎年開催されていますので、来年以降、ぜひ行ってみてください。

写真はシダレザクラ(枝垂れ桜)です。
シダレザクラが好きな方は多いのではないでしょうか。
枝が細く垂れ下がっていてその枝にたくさんの花をつけます。
シダレザクラにも種類があるのでご紹介します。
花の色味が強いのでベニシダレ(紅枝垂れ)と呼ばれるシダレザクラは、濃いピンク色の花が垂れた枝に咲きます。
とても写真映えする桜です。
花びらが重なったヤエベニシダレ(八重紅枝垂れ)は八重咲きのベニシダレです。
ベニシダレと比べると花にボリュームがあり、フワフワとした花が特徴です。
ベニシダレの開花時期はソメイヨシノよりほんの少しだけ早いです。
ソメイヨシノと比べて1週間ほど早い年が多いようです。
例年だと3月下旬ごろに開花から見頃まで迎えます。
ヤエベニシダレの開花時期は4月中旬から4月下旬とソメイヨシノより少し遅めの開花時期になっています。
東京では日比谷公園、明治神宮外苑で見られます。
オオシマザクラ(大島桜)は聞いたことがありますか。
伊豆半島周辺で見られる品種のためオオシマザクラという名前です。
白っぽい花びらのサクラで、この品種は観賞用や防腐樹として植えられる品種ですが、一番有名なのは桜餅の葉っぱです。
この品種の葉っぱが塩漬けになって使われていることが多く、サクラの良い香りがします。
開花時期は3月下旬から4月上旬です。
東京では隅田公園、小金井公園などで見られます。
ここまでは早咲きの品種を紹介しました。
すでに見頃から満開を迎えている品種もありますので、満開の桜を一足先に楽しむことができるでしょう。
ここからは遅咲きの品種です。

ヤエザクラ(八重桜)と呼ばれる花びらが重なった咲き方をするサクラがあります。
ヤエザクラの品種の一つにシロタエ(白妙)という品種があります。
花びらは10枚から20枚でその名前の通り白い花びらが特徴です。
カンザン(関山)という品種はシロタエとは対照的で濃いピンク色をしているヤエザクラです。
花びらは20枚から50枚が重なって咲くので、ボリュームが魅力的な品種です。
食用に塩漬けにされている花はこの品種が多いようです。
ソメイヨシノの次に多い品種とも言われていてよく見かける品種です。
ギョイコウザクラ(御衣黄桜)というサクラもあります。
黄緑や黄色に近い色味の品種です。
15枚程度の花びらが重なった花で春が終わり夏を感じてしまうような桜です。
シロタエやカンザンは、例年ソメイヨシノが終わった頃に開花をして4月下旬まで花を咲かせています。
ギョイコウザクラはそれよりも少し遅く5月初旬ごろまで咲いていて、最も遅い桜と言われています。
ギョイコウザクラの中でも珍しいウコンという桜は黄色がかった桜で、全国でもあまり見られない桜ですが東京の新宿御苑で見ることができます。
東京でヤエザクラは靖国神社、代々木公園などで見られます。
最後に桜の代表、ソメイヨシノ(染井吉野)を紹介します。
おそらく知らない人はいないくらい有名な桜で、日本にある桜の木の中で一番多い品種です。
桜の開花情報はソメイヨシノの開花の情報で、季節になるとニュースなどにも取り上げられています。
大ぶりな枝に咲く薄ピンクの花はとても綺麗で全国各地に植えられています。
開花時期は4月上旬ごろが目安で、花が散るまでの期間が短く、開花からわずか2週間ほどで散り始めてしまいます。
東京でもあちらこちらで見かけることが出来ます。
3.子どもとお花見の写真の撮り方

満開の桜をバックに写真を撮るのもお花見の楽しみの一つですよね。
でも、お花見スポットでは満開の桜を求めて多くの人が集まり、ゆっくり写真を撮っているような雰囲気ではないところも多いです。
子どもと桜と桜の写真が撮りたくても満足のいく写真が撮れないこともあると思いますが、これから紹介するコツを意識して撮ればスマホでもカメラでも今年は可愛い桜の写真が撮れます。
低い木のある場所を選んだり、子どもを抱っこして桜との高さを合わせて撮るテクニックを使うと子どもと桜が綺麗に写ります。
顔が下を向かないように撮ると顔が陰にならずに撮れるので更に良い写真になります。
この方法は大人が二人必要です。
抱っこする人と写真を撮る人と分けて危険のないようにしてください。
桜を手前に持ってきて花をフレームのように使って撮る方法もあります。
桜の間から子どもにピントを合わせて撮影します。
背景にも桜が写っているとさらに良いでしょう。
前の桜はボケて綺麗な色で写ります。
屋台などが出ていたり人混みの中だったり写ってほしくないものは、体で隠したり写らないアングルで撮ると良いです。
桜と子ども以外の色が目立つ色であった場合、そちらに目がいってしまい残念な写真になってしまいます。
どうしても写ってほしくない物が隠しきれないときは、しゃがんで下からのアングルで撮ると写りにくくなります。
下から見上げるように子どもを撮ると桜が背景になり、被写体の表情なども写ります。
あまり周りに人がいなければ、子どもと撮影者の距離をとった上で下のアングルから撮影するテクニックもあります。
子どもの全体と桜の木全体を撮ることができます。
入学式や入園式で新しい制服などのフォーマルな服を着ている姿は、ぜひ全身の姿を残しておきたいですよね。
桜の木の近くでなくても桜との写真は撮れます。
桜の木とは距離をとって子どもに立ってもらい、背景に桜の木が写るように撮影します。
近くに行けばたくさんの人が写ってしまうような場所でも体で人混みを消すように撮影できます。

まだ立つことのできない赤ちゃんや、歩けない赤ちゃんと桜を撮りたい時は、桜の木と撮ることにこだわらずに落ちている桜の花や花びらを利用して撮るのも一つです。
大人が桜の花を手に持っているのをじっと見ている姿も可愛らしいですよね。
桜が写真の中に写り込むように持つのがコツです。
興味を持って手を伸ばすことのできる赤ちゃんなら、桜の花びらを赤ちゃんの周りに集めてあげて、それを触っている姿も可愛いです。
赤ちゃんの目線にカメラの高さを合わせて撮ると、初めての桜に興味津々な表情を写すことができるので記念になります。
桜の花は赤ちゃんの口に入るサイズなので撮影するときは誤飲に気をつけてください。
撮影は昼間、特に午前中の日の高いうちにお花見写真を撮るのもテクニックの一つです。
夜桜もとても綺麗ですが、夜景を撮るときはシャッターのスピードが遅くなり、少しでも動くとブレの原因になります。
子どもが被写体となる場合動いてしまうのは仕方ないことなので、明るい時間が撮りやすいです。
それに、日中の機嫌の良い時間帯に写真を撮った方が可愛い表情の写真が撮れるでしょう。

余白を意識したアングルで撮ることを意識してみるとバランスの良い写真になります。
桜をめいっぱい写真に写したくなってしまいますが、青空や芝生などで余白を作ることによって桜の色が目立ちます。
水辺に植えられている桜も多いので、川や湖などの水辺で余白を作っても綺麗です。
桜の対角に子どもを写すような構図で撮ると写真がまとまります。
お花見といえば美味しいグルメも楽しみの一つです。
お団子や花見弁当と一緒のポーズで写真を撮っても面白いです。
顔の近くに料理を持ってきて背景に桜が来るように下からのアングルで撮ります。
一枚の写真の中に、桜とお花見を楽しむ様子のどちらも写すことが出来る方法です。
花びらや花を身につけてみると、また違った写真ができます。
髪に桜の花をつけてみたり手のひらいっぱいに桜の花びらを載せて撮っても良いです。
毎年同じアングルで撮ると子どもの成長の記録になりますね。
洋服の色はナチュラルな色や黒、紺、グレーなどのフォーマルで使うような色を着ると更に桜が目立ちます。
桜の花の色は光の加減によっては花の色が白くとんでしまうことがあるので、撮影時に暗く感じてもフラッシュたかないで撮りましょう。
それでもまだ写真が白っぽくなってしまったら、写真の編集をしてみます。
「ホワイトバランス」「光彩」「色調」をいじってみましょう。
触りすぎると不自然な写真になってしまうので、なるべく自然に見える範囲で動かしてみると桜の色がうまく出た写真ができます。
人が多い場所での撮影は周りの人や撮影者、子どもの安全に注意してお花見と撮影を楽しんでください。
4.例年、東京で開催されている桜祭り

桜との撮影をゆっくり楽しみたい方は、遠くまで行かなくても近所の桜で十分楽しむことが出来ます。
でも、あちこちで開催されているさくら祭りも楽しみたいですよね。
都内で例年開催されている桜のお祭りをピックアップしました。
千代田区では「千代田のさくらまつり」が開催されます。
昨年は桜のライトアップがされたり千代田区内の桜の名所を走ってくれる周遊バスが走ったりするそうです。
商店街などによる関連イベントもありました。
2024年は3月24日から4月4日まで開催される予定です。
中央区の「SAKURA FES NIHONBASHI」では江戸桜通りのライトアップや福徳の森でのライブの開催、屋台の出店や街の各店舗で春限定のメニューが登場するなどして盛り上がります。
あちこちの店舗で「桜のれん」と呼ばれる桜色ののれんが出され、街全体が桜色になります。
2024年は3月15日から4月7日までの期間で開催予定になっています。
墨田区の東京スカイツリータウンでは「東京ソラマチ さくらまつり」が毎年開催されています。
ソラマチ広場には桜の造花が飾られ、春ならではのテイクアウトフードを楽しむことが出来ます。
キャラクターとのグリーティングやスカイツリーが桜色になるライトアップなどイベントが盛りだくさんです。
2024年は3月1日から4月7日まで開催される予定です。
各イベントは期間中の異なる日に開催されていますので、お目当てのイベントがいつ開催されているのかを確認してからお出かけしてみてください。
まとめ

お花見を毎年楽しみにしている筆者ですが、自分たちの休日と満開の日と天気の都合が合わずにお花見できない年もありました。
今年は思いっきりお花見を楽しみたいと思っています。
同じように2024年のお花見を存分に楽しみたい方の参考になればと思いまとめました。
2024年の満開の桜を楽しみましょう。